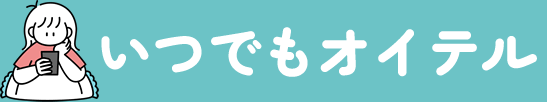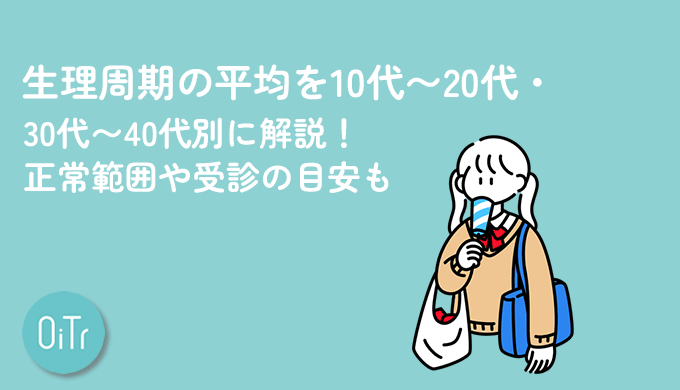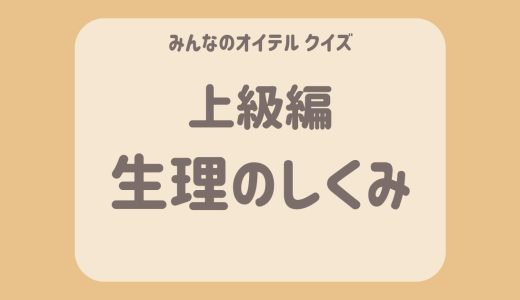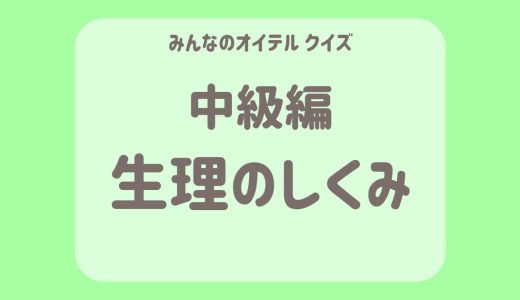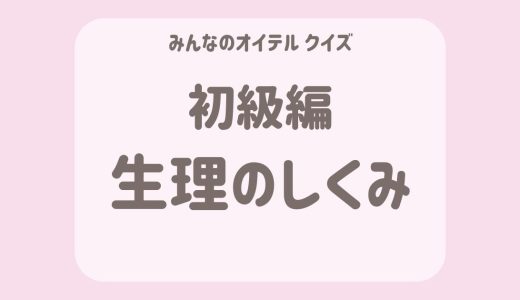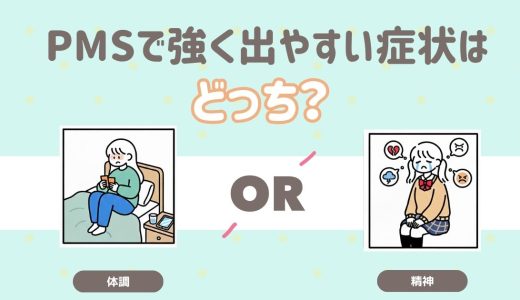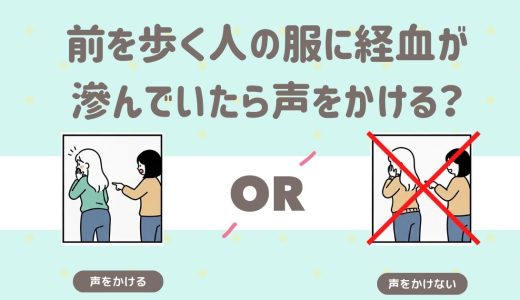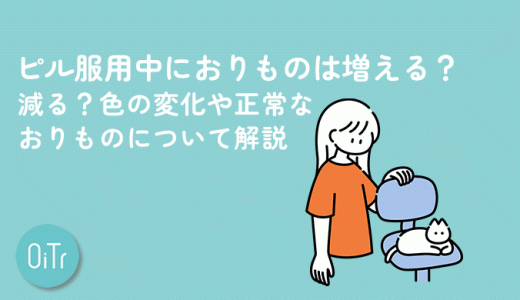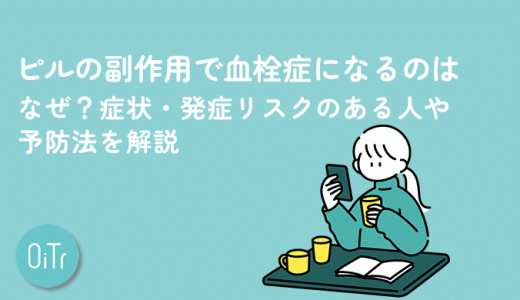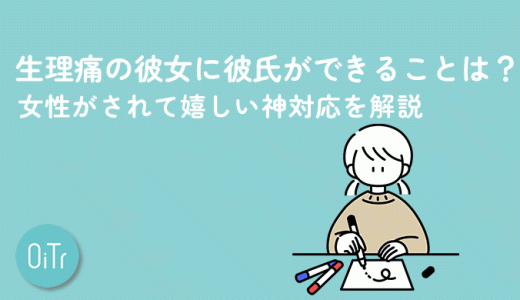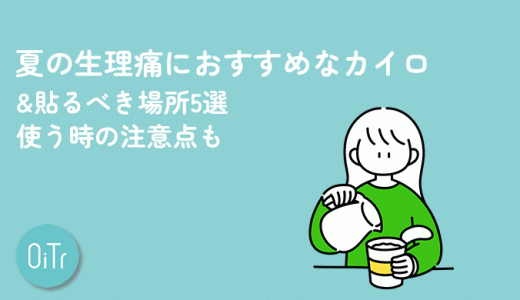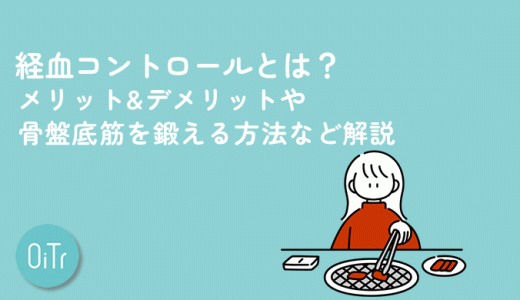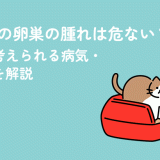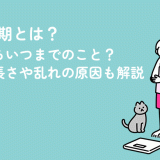生理がいつもより早まったり遅れたりすると「私の生理周期って平均から外れている?」と思うかもしれません。
1ヶ月に1回来ていた生理が、なかなか来なくなると不安になるのも当然です。
特に、10代の頃は生理周期が安定せず、対応が難しいと感じる人もいるでしょう。
一方、30代後半を過ぎて、生理周期が長くなったと思う人もいるかもしれません。
今回は、生理周期の平均を年代別に解説するとともに、正常範囲や受診の目安を紹介します。
\アンケート実施中/
生理周期の平均は、25日~38日です。
次の生理までの日数が、月によって異なったとしても、この範囲内に収まっていれば問題ありません。
月経周期の平均は、10代~20代では長くなり、30代以降から40代にかけて短縮する傾向にあります。
ここからは、年代別の生理周期についてみていきましょう。
生理が始まったばかりの10代の頃は、身体が成熟しきっていないため、ホルモンバランスが不安定で、生理周期が安定しないことが多いです。
その後、20代にかけて生理周期は徐々に長くなり、月経周期も安定し、23歳で平均30. 7日になるという報告があります。
性成熟期にあたる30代前半は、20代と同じような生理周期ですが、30代後半〜40代になるにしたがって、少しずつ生理周期が短くなります。
卵巣機能が徐々に低下し、女性ホルモン分泌量が低下するため、月経に変化がみられるようになるでしょう。
45歳の生理周期の平均は27. 3日で、40代半ばから更年期に入ると、月経不順をくり返すようになって、閉経に向かいます。
生理周期とは、生理が始まった日から、次の月経が始まる前日までの期間をさします。
生理周期は、女性ホルモン分泌の変化によって生まれ、大きく4つの時期に分かれているのです。
ここからは、それぞれの時期についてみていきましょう。
卵胞期は、卵胞刺激ホルモンの影響により、卵巣にある原子卵胞が成長を始め、卵胞から女性ホルモンの1つである「卵胞ホルモン(エストロゲン)」が分泌されるようになります。
この働きによって、子宮内膜が少しずつ厚くなっていくのです。
この時期は、肌や髪にツヤがあり、心身ともに調子がよいでしょう。
卵胞が成熟すると迎えるのが、黄体形成ホルモンが大量分泌される「排卵期」です。
この黄体形成ホルモンの分泌量がピークを迎えた約12時間後に、卵胞から卵子が飛び出す「排卵」が起こります。
大きく成長した卵胞が腹膜を刺激したり、卵巣から卵子が飛び出たりすることで、排卵痛が起こる人もいるでしょう。
排卵後は、黄体形成ホルモンの影響で卵胞が黄体となり、女性ホルモンの1つである「黄体ホルモン(プロゲステロン)」を分泌します。
卵胞ホルモンと黄体ホルモンの影響で、子宮内膜はより厚くやわらかくなり、身体が妊娠を維持するのに適した状態を作り出すのです。
心身ともに不安定になりやすく、なかには月経前3日~10日にPMS(月経前症候群)に悩まされる人もいます。
妊娠が成立しない場合、卵胞ホルモンと黄体ホルモンの血中濃度が下がり、生理が始まります。
月経期は、不要な子宮内膜を剥がして、体外に排出するために「プロスタグランジン」という物質が分泌される時期です。
プロスタグランジンの分泌量が多いと、子宮が強く収縮し生理痛が起こることも。
生理期間の平均は4. 6日で、3日〜7日の範囲内が正常です。
1日〜2日で終わる場合を過短月経、8日以上続く場合を過長月経と呼びます。
生理周期が25日〜39日の間に収まっていれば、前後6日のずれは問題ありません。
しかし、生理周期が極端に長い・短い場合は、何かしらの病気が隠れている可能性があります。
ここからは、生理周期が長い人・短い人の特徴をみていきましょう。
生理周期が39日以上と長い場合を「稀発月経」と呼びます。
卵巣や脳下垂体の機能が下がることで起こり、生理が来る回数が1年に10回以下になるのです。
稀発月経が起こる原因の代表例は、以下のとおりです。
- ホルモンバランスの乱れ
- ストレス
- 急激な体重減少
- 肥満
- 多嚢胞性卵巣症候群
- 甲状腺の病気
- 高プロラクチン血症
3ヶ月以上生理が来ない状態を、無月経と呼びます。
妊娠していないにも関わらず、生理が来ない場合は、婦人科クリニックで相談しましょう。
生理周期が24日以下と短い場合を、頻発月経と呼びます。
月経終了から排卵までが短いケースや、排卵から生理開始までが早まるケース、生理は来るものの、排卵が起こらない無排卵周期症のケースが考えられるでしょう。
頻発月経の原因の代表例は、以下のとおりです。
- ホルモンバランスの異常
- ストレス
- 黄体機能不全
- 加齢による卵巣機能の低下
頻発月経では、正常の生理よりも経血量が増えるため、貧血が起こりやすくなります。
無排卵周期症を放置すると、不妊につながることも。
生理だと思っていたら、実は不正出血だったケースもみられるため、頻発月経があるなら婦人科で原因を特定しましょう。
不正出血と生理の違いについては、以下の記事でくわしく解説しています。
\あわせて読みたい/
 不正出血と生理の違いがわからない!月経以外で出血が起こる原因など解説
不正出血と生理の違いがわからない!月経以外で出血が起こる原因など解説
生理予定日を過ぎても出血がみられない時は、妊娠している可能性があります。
生理周期が安定しており、生理予定日から7日以上過ぎている場合は、妊娠検査薬を使用しましょう。
- 基礎体温の高温期が続く
- おりものが増える
- 微熱が続く
- 強い眠気がある
- 体がだるい
- 胸の張りがある
- 胃がむかむかしたり、吐き気が出たりする
こうした体調の変化が、妊娠に気づくきっかけになることも。
妊娠検査薬で陽性が出たら、すぐに婦人科を受診してくださいね。
生理周期が乱れたり、経血量に大きな変化があったりして、婦人科の受診を検討する人も多いでしょう。
生理トラブルで婦人科を受診する目安は、以下のとおりです。
- 生理周期が24日以内もしくは39日以上が続く
- 生理周期が毎回安定しない
- 妊娠していないのに3ヶ月以上生理がこない(無月経)
- 普通のナプキンでは1時間ももたない(過多月経)
- 経血量がおりもの程度で、ナプキンをほとんど必要としない(過少月経)
- 以前よりも経血量が増えて、生理期間も伸びた
3ヶ月以上生理がこない無月経を放置すると、不妊になる可能性もあります。
できるだけ早めに婦人科を受診し、原因を特定しましょう。
生理周期は、年代によって平均が異なり、23歳と45歳ではおよそ3日のずれが生じます。
性機能が未成熟な10代では生理周期が安定しにくいですが、20代前半に入れば安定するでしょう。
30代後半からは、卵巣機能の低下により、生理周期が今までと異なるケースも出てきます。
どの年代でも、25日〜38日に収まっていれば、前回の生理周期と日数が異なっても問題ありません。
しかし、生理周期が極端に長い・短い場合は、病気が隠れているおそれがあるため、婦人科を受診しましょう。
- 生理周期の平均は25日~38日で、次の生理までの日数が月によって違っても問題ない
- 月経周期は、10代~20代で長くなり、30代~40代では短くなる傾向にある
- 生理周期は、ホルモンバランスの変化によって生まれ、4つの時期に分けられる
- 生理周期が極端に長い・短い人は、稀発月経や頻発月経、妊娠の可能性を考えよう
- 生理周期や経血量の異常がみられたら、婦人科で原因を特定して