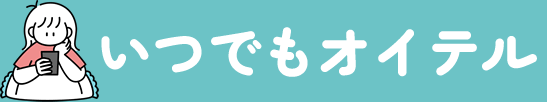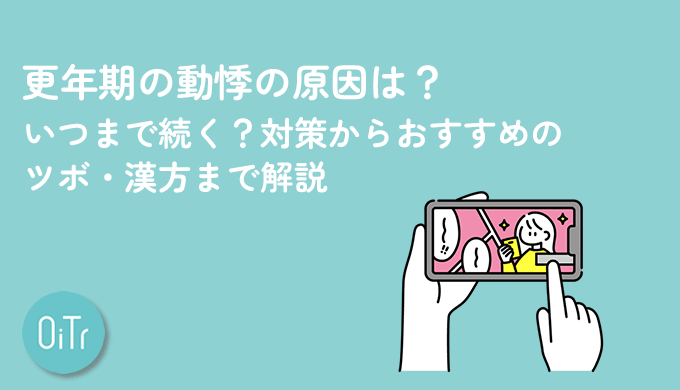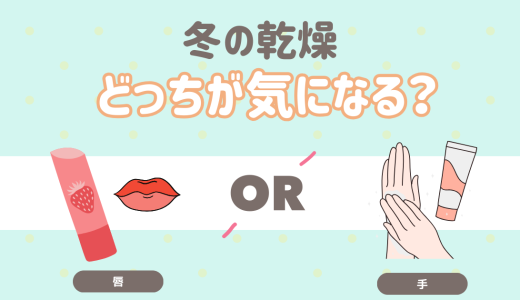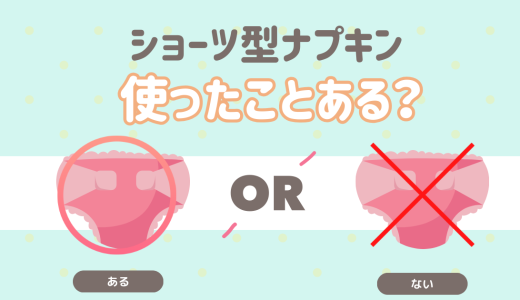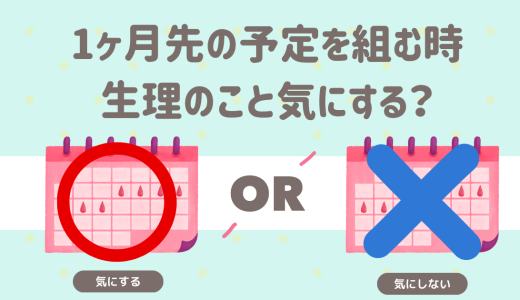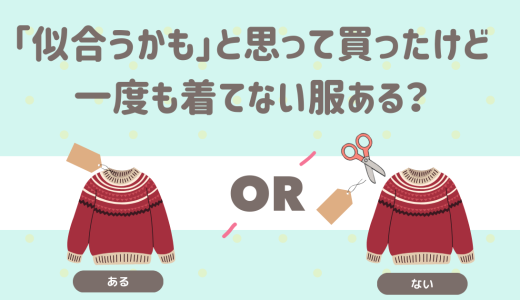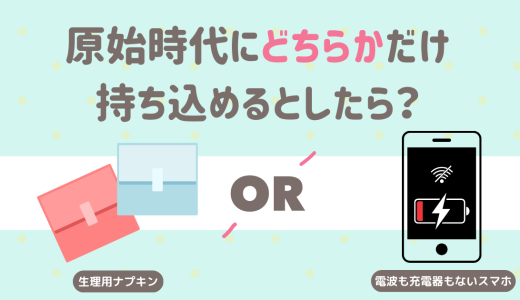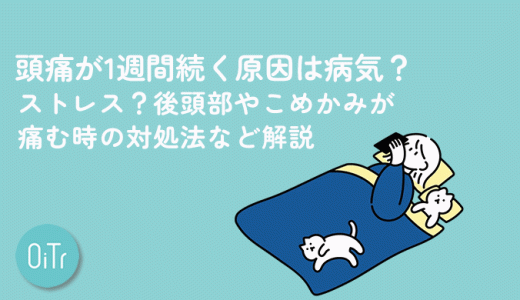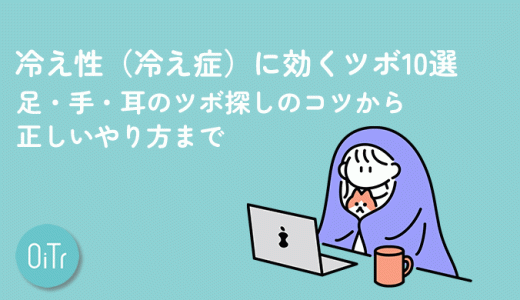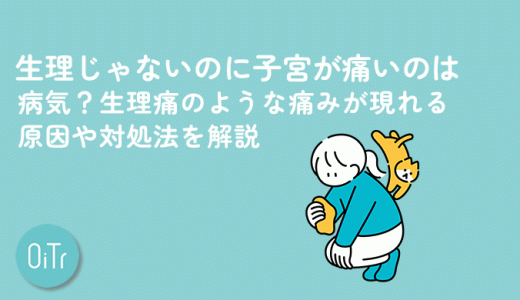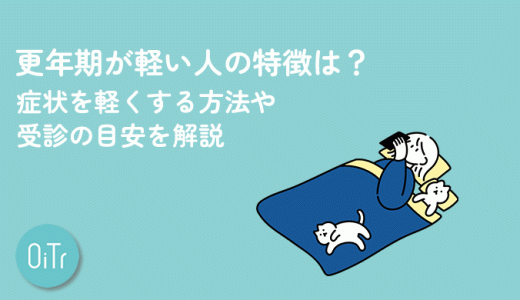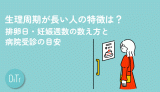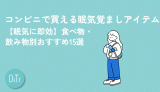「激しく動いたわけでもないのに、急に動悸がしてつらい」「横になるとドキドキと動悸がするせいで寝つけない」と悩んでいる、40代後半〜50代前半の女性は多いもの。
いわゆる更年期は、さまざまな理由で動悸を感じやすい時期です。
どのように対処すればよいのかがわかれば、心も楽になるのではないでしょうか。
今回は、更年期の動悸の原因やいつまで続くかを解説するとともに、おすすめのツボや漢方などの対処法を紹介します。
\アンケート実施中/
更年期に起こる動悸は、さまざまな原因が考えられます。
更年期症状だと思っていたら、ほかの病気が原因のケースもよくみられるため、自己判断せずに受診するべきです。
ここからは、更年期に動悸が起こる原因を解説します。
更年期は、加齢にともなって卵巣機能が低下し、女性ホルモンの分泌量が減少するため、自律神経が乱れやすい時期。
なぜなら、ホルモンバランスをコントロールする脳の視床下部は、自律神経の働きも同時に司っているためです。
体内の女性ホルモンが足りなくなると、ホルモンを分泌するように視床下部が卵巣に指令を出しますが、機能が低下した卵巣からはホルモンが分泌されないため、次第に視床下部が混乱してしまうのです。
自律神経は、心臓の働きや呼吸もコントロールしているため、機能が低下すると動悸や息切れなどが起こりやすくなります。
心身にストレスを感じると、動悸や脈が飛ぶような感覚が現れることがあります。
ストレスが自律神経を乱し、交感神経が過剰に働くため、心拍数が上昇したり脈が速くなったりするのです。
ストレスに長くさらされると、動悸や息切れなどの症状が現れやすくなります。
更年期は、昇進や異動、家庭環境の変化など、さまざまなストレスにさらされる時期のため、注意が必要です。
動悸や息切れ、胸の違和感が定期的にみられる場合は「微小血管狭心症」の可能性があります。
微小血管狭心症とは、酸素や栄養を送る冠動脈から分岐する微小血管が、十分に拡張しなかったり異常収縮したりして、心臓に一時的に血が行き渡らなくなる状態のこと。
エストロゲンには、血管を拡張して血流を保護する作用がありますが、卵巣機能の低下によってエストロゲンが減少する更年期には、微小血管狭心症が起こりやすいです。
動悸やほてりなどは、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)でも起こるため、更年期障害と混同されることも。
更年期機能亢進症では症状が継続するのに対して、更年期障害では症状がみられるのが一時的という見分け方があります。
鉄分が不足し、全身に酸素を運ぶ「ヘモグロビン」が減少すると、全身が酸素不足になるため、動悸がみられることがあります。
動悸以外にも、だるさや立ちくらみ、頭痛などの症状が起こることも。
更年期に入ると、月経周期や経血量が変化し、重度の貧血になるケースがあります。
更年期障害と貧血の症状は共通するものも多いため、血液検査による鑑別が必要です。
更年期にともなう動悸や息切れがみられる期間には、大きな個人差がみられます。
50代後半になると落ち着く人もいれば、50代後半〜60歳ごろまで続くケースも。
動悸をはじめとした血管運動神経障害は、閉経前後2年間に起こりやすいといわれています。
ストレスや環境の変化で、症状が悪化するケースもみられますよ。
更年期の動悸は、時間を問わず急に発生することが多く、就寝前に起こることも。
「動悸が起きるのではないか」と不安になり、眠れなくなる人もいます。
動悸への対処法を知っておくことで、こうした不安や恐怖を緩和できるでしょう。
更年期の動悸を緩和するためには、自律神経を整える工夫が効果的です。
ここからは、更年期の動悸への対処法を解説します。
動悸が現れたら、まずは深い腹式呼吸をおこなうとよいでしょう。
- ゆっくり大きく鼻から息を吸い、お腹に空気を入れるように膨らませる
- 時間をかけて吸った息を吐き出しながらお腹をへこませる
自律神経のバランスが整い、症状が落ち着いていくでしょう。
アロマオイルを含ませたハンカチやティッシュなどを、そばに置いておくのもおすすめです。
エストロゲンの分泌をサポートするイランイランや、交感神経を抑えてリラックスできるマンダリンなどがよいでしょう。
動悸の緩和が期待できるツボを知っておくと、動悸が現れた時にすぐに押せるのでおすすめです。
- 神門(しんもん):手首の内側にあるくぼみにある
- 膻中(だんちゅう):両脇を結んだ線の真ん中にある
- 百会(ひゃくえ):頭の頂点にある
どれも精神安定や自律神経の調整が期待できるツボですので、動悸がしたら呼吸をしつつゆっくり押してみてくださいね。
自律神経を整えるために、生活習慣を見直すのも効果的です。
- 休日も平日と同じ生活リズムを送る
- 朝日を浴びる
- 3食バランスのとれた食事を意識する
- 適度に運動する
- ぬるめのお風呂に浸かる
- 寝る前のスマートフォンなどの使用を控える
日常生活にこれらを取り入れることで、自律神経が安定し、症状の緩和や予防が期待できますよ。
カフェインの過剰摂取や喫煙、飲酒は、動悸や息切れの原因の1つといわれています。
なぜなら、これらは自律神経を刺激し、脈拍を速める作用をもつためです。
動悸や息切れを予防するために、カフェインを控えたり、節酒や禁煙に取り組んだりしましょう。
更年期は、心身にさまざまな症状に悩まされる時期です。
漢方を服用することで、動悸をはじめとした更年期症状の緩和が期待できます。
漢方は複数の生薬を混ぜて作られているため、1つで複数の症状に対処できるのがメリットです。
しかし、体質が合わなければ効果が期待できないばかりか、さらに悪化する可能性があるというデメリットもあることを忘れないでください。
漢方を服用する際は、医師や薬剤師に相談するのがおすすめです。
ここからは、更年期の動悸に使われる漢方を紹介します。
柴胡加竜骨牡蠣湯は、体力が比較的あり、不安や恐怖、不眠が起こっている人に適した漢方です。
動悸や頭痛にも効果が期待できますよ。
柴胡桂枝乾姜湯は、体質が虚弱な傾向にある人の気疲れやだるさの症状を緩和する漢方です。
冷え症や貧血、動悸、息切れ、ホットフラッシュなどの症状にも用いられます。
加味逍遙散は、更年期障害の治療でよく用いられる漢方です。
月経不順や肩こり、冷え症、便秘などのさまざまな症状に対応できます。
\あわせて読みたい/
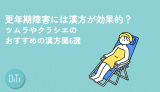 更年期障害には漢方が効果的?ツムラやクラシエのおすすめの漢方薬6選
更年期障害には漢方が効果的?ツムラやクラシエのおすすめの漢方薬6選
更年期に動悸や息切れに加えて、ホットフラッシュなどの更年期症状がみられる場合は、婦人科を受診しましょう。
一方で、動悸や息切れ以外に症状がないなら、循環器内科を受診するのをおすすめします。
ほかの病気が隠れている可能性もあるため「更年期症状だろう」と自己判断して放置せずに、心電図や血液検査、問診による診断を受けるべきです。
動悸が更年期障害の症状だと診断された場合、体外から女性ホルモンを補う「ホルモン補充療法」がおこなわれます。
子宮体がんや乳がんなどの病気の場合は、ホルモン補充療法をおこなえないため、漢方で治療することもあるでしょう。
更年期にみられる動悸は、ホルモンバランスの変化だけでなく、ストレスによる自律神経の乱れやほかの病気が原因かもしれません。
「単なる更年期症状だろう」と片づけず、病院を受診して原因を特定するのがおすすめです。
動悸がしても慌てないで済むように、腹式呼吸やツボ押しなど、すぐにできる対処法を知っておくとよいでしょう。
自律神経を整えるために、食生活や睡眠などの生活習慣を見直し、カフェインやアルコールの摂取を控えるのも大切です。
更年期による動悸は、ほかの更年期症状と併発している場合は婦人科、動悸以外に症状がない場合は循環器内科を受診しましょう。
- 更年期の動悸は、女性ホルモン分泌の減少だけでなく、ストレスやほかの病気が原因かもしれない
- 更年期にともなう動悸や息切れが現れる期間には、大きな個人差がある
- 更年期の動悸を緩和するためには、生活習慣の見直しで自律神経を整えよう
- 体質や症状に合った漢方の服用で、動悸が改善することも
- 併発する症状や度合いに応じて、婦人科や循環器内科を受診しよう