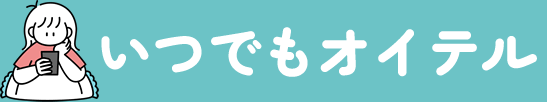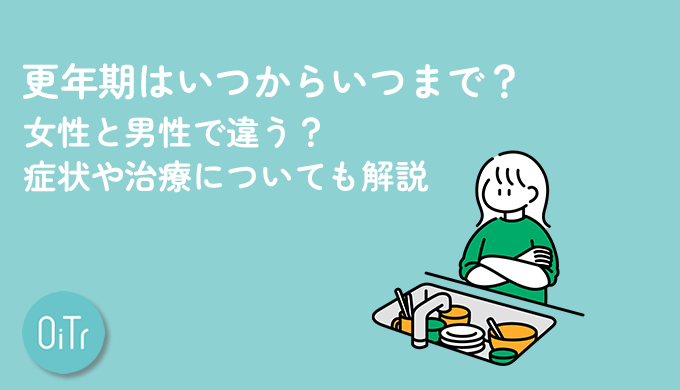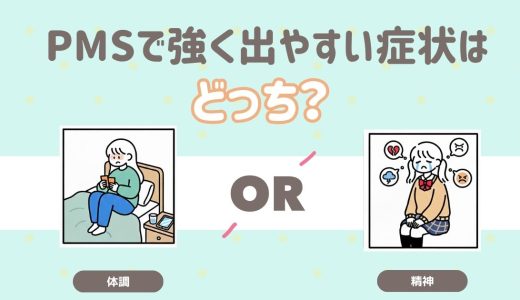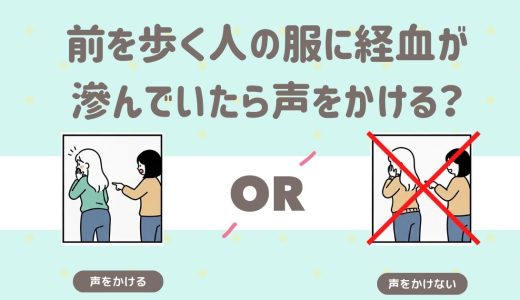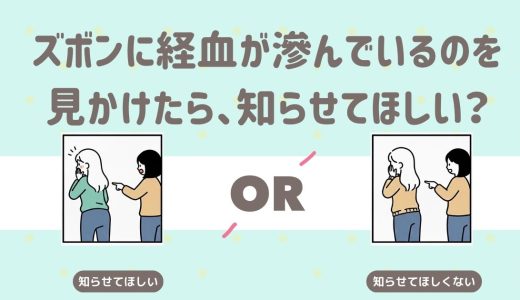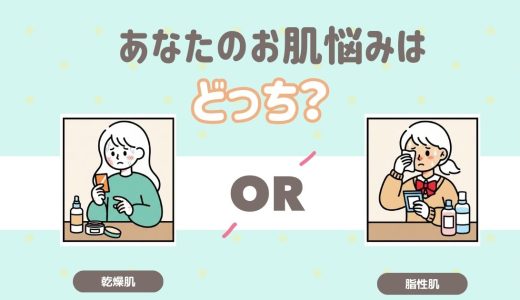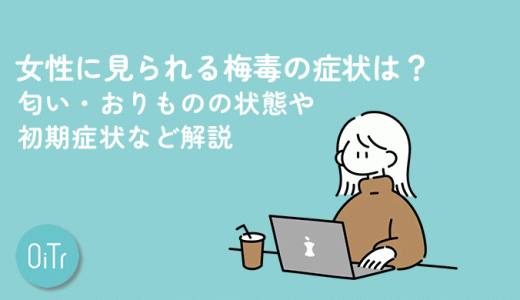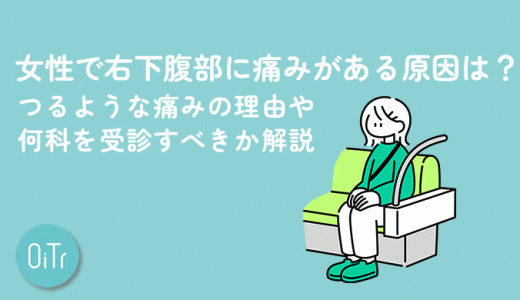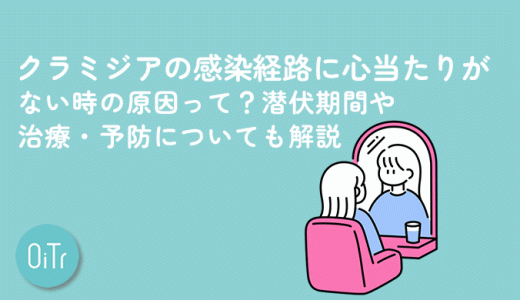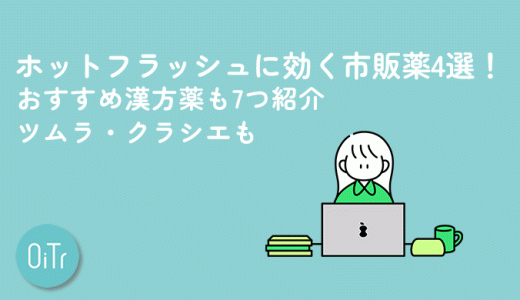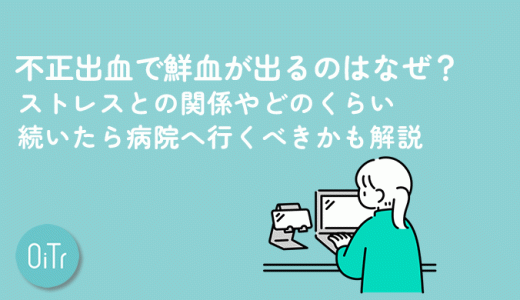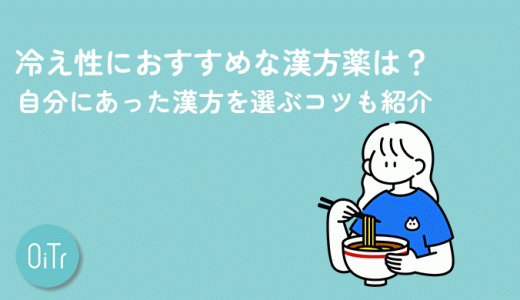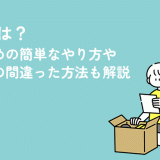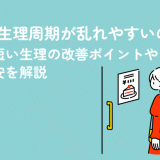更年期にさしかかると、心身ともに不調がみられやすくなります。
女性の更年期について知っている人は増えてきていますが、男性にも更年期があることを知っていますか?
更年期は性別問わず、さまざまな不調が現れやすいため、心身を労る必要がある時期です。
今回は、更年期はいつからいつまでを指すのかや、みられる症状、治療法について解説します。
\アンケート実施中/
更年期とは、閉経前後の5年間を合わせた10年間のことです。
女性の場合、卵巣機能の低下にともない、女性ホルモン分泌量が急激に低下します。
すると自律神経が乱れてしまい、心身の状態に変化が起こりやすいです。
心身の不調以外にも、生理周期にも変化がみられます。
ここからは、更年期はいつからいつまでをさすのかみていきましょう。
更年期が始まる年齢は、45歳ごろが一般的です。
月経が来なくなる「閉経」を50歳すぎに迎え、55歳ごろに更年期が終わる人が多いでしょう。
症状の程度には個人差があり、日常生活に支障が出る人がいる一方で、更年期症状を感じずに終わる人も。
更年期が終わる55歳以降を「アフター更年期」と呼びます。
この時期には、更年期症状が落ち着き始める一方で、生活習慣病や子宮体がん、骨粗鬆症になる可能性が高まるので、注意が必要です。
人によっては、30代後半から更年期にみられる症状に悩まされる人もいます。
なぜなら、女性ホルモンの1つである「エストロゲン」の減少が、30代後半から始まるためです。
35歳ごろ〜45歳ごろまでを「プレ更年期」と呼びます。
無理なダイエットによる体重減少や睡眠障害、栄養不足など、生活習慣が不規則な場合、ホルモンバランスが乱れやすく、更年期のような症状が出やすいです。
更年期症状は、女性だけでなく男性にも訪れます。
男性の更年期障害は、医学的にLOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)と呼ばれる病気です。
一般的には、40代後半から症状がみられる人が多いでしょう。
しかし、男性ホルモン分泌量の低下の程度には個人差があるため、更年期が始まる時期や症状の程度は、人によって異なります。
男性の更年期症状は、男性ホルモンの減少が原因です。
代表的な症状は、次のようなものが挙げられます。
- イライラ
- 疲労感
- 集中力の低下
- ホットフラッシュ
- 動悸
- 筋肉痛
- 筋力低下
- 勃起障害(ED)
- 性欲減退
男性の場合は、女性よりもつらい症状が長期間続くことも。
男性ホルモンの減少は20代から始まり、症状が徐々に進行していくため、加齢による衰えか、更年期障害かの区別が難しいのが現状です。
更年期症状は、年齢に応じて変化がみられることがわかっています。
女性の身体では、年齢を重ねるごとに、卵巣機能とエストロゲンの欠乏が変化していくため、さまざまな症状が現れるようになるのです。
ここからは、女性の更年期症状の経過について解説します。
月経周期の乱れは、更年期に入ったサインの1つです。
卵巣機能が低下するため、周期的に排卵が起こらなくなるために起こります。
更年期にはホルモンバランスが不安定になるため、生理までの間隔や経血量に変化がみられるでしょう。
一般的には、40代後半から月経不順が現れ、経血量も不安定になります。
徐々に生理の回数が減少し、50歳ごろに生理が1年以上ない状態(閉経)を迎えるのです。
エストロゲンの減少が始まると、次のような自律神経失調症状が現れます。
- ホットフラッシュ
- 発汗
- のぼせ
- めまい
エストロゲンが体内で不足すると、脳が卵巣にホルモンを分泌するようにシグナルを出します。
しかし、機能が低下した卵巣はシグナルに応えられないため、エストロゲンが足りない状態が続くのです。
そして、脳が混乱状態に陥るため、同じ脳の視床下部が調整を司る自律神経が乱れてしまいます。
自律神経失調症状が出た後に、次のような精神症状が現れます。
- 倦怠感
- うつ状態
- 不安感
- 不眠
- イライラ
- 新しく体験したことを覚えられない
更年期は、仕事や家庭環境が大きく変化する時期です。
ストレスが積み重なることで、精神症状がみられることも。
閉経後には泌尿生殖器が萎縮するため、以下に示す症状がみられます。
- 萎縮性膣炎
- 外陰部のかゆみ
- 性交障害
- 尿失禁
- 頻尿
更年期は、加齢によって骨盤底筋や尿道括約筋が弱ることや、自律神経が乱れて膀胱を過度に収縮させてしまうことでも、尿漏れ・頻尿に悩まされるでしょう。
「ほかの人は病院に行っていないのだから、つらい症状を我慢すべきだ」と、受診をためらう人も少なくありません。
しかし、更年期症状の現れ方や程度には個人差があるもの。
ほかの人と比較せずに、症状がつらい場合は、受診をおすすめします。
ここからは、更年期症状で病院に行くタイミングや治療法などをみていきましょう。
更年期のつらい症状のせいで日常生活に支障が出ているなら、更年期障害を疑って、女性なら婦人科を受診しましょう。
女性の更年期障害の代表的な治療法は、以下のとおりです。
- ホルモン補充療法:体外から少量のエストロゲンを補充する
- 漢方薬:その人が本来の心身のバランスをとれるようにサポートする
- 抗うつ薬・向精神薬:更年期の精神症状を緩和する
- カウンセリング:自分自身の問題と向き合い、ストレスを軽減する
男性の更年期障害は、主に泌尿器科や内科でおこなわれ、症状に合わせて抗うつ薬や漢方薬、ED治療薬などが選択されます。
血中の男性ホルモン値が著しく低い場合は、男性ホルモン製剤を投与することも。
更年期障害でみられる症状は、甲状腺や心臓の病気でも起こりうるものです。
適切な治療をおこなうためには、できるだけ早めの受診をおすすめします。
病院の治療と並行して、規則正しい生活を送ることも、男女ともに更年期症状を緩和するために大切です。
- ストレスを溜めない
- バランスのとれた食事を意識する
- 適度に運動する
- 質のよい睡眠を確保する
上記の工夫を意識して取り入れましょう。
更年期は、閉経の5年前である40代後半から始まることが多いです。
加齢にともない、女性の身体では卵巣機能が低下し、エストロゲンの分泌が急激に減るため、さまざまな不調が現れます。
男性の身体では、テストステロンの減少にともない、40代後半から更年期症状がみられることも。
つらい症状を緩和・予防するには、更年期がいつから始まるかを知り、生活習慣を整えることが大切です。
更年期症状がつらく、日常生活に支障が出ている場合は、早めに病院を受診しましょう。
- 更年期は、男女ともに40代後半から始まることが多い
- 卵巣機能が低下し始める30代後半(プレ更年期)から不調を感じる人も
- 女性の更年期では、年齢によって症状が変化していく
- 更年期がいつからいつまでなのかを知り、生活習慣を整えておくことで症状の予防や緩和が目指せる
- 日常生活に支障が出ている場合、女性は婦人科、男性は泌尿器科や内科を受診しよう