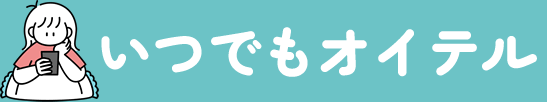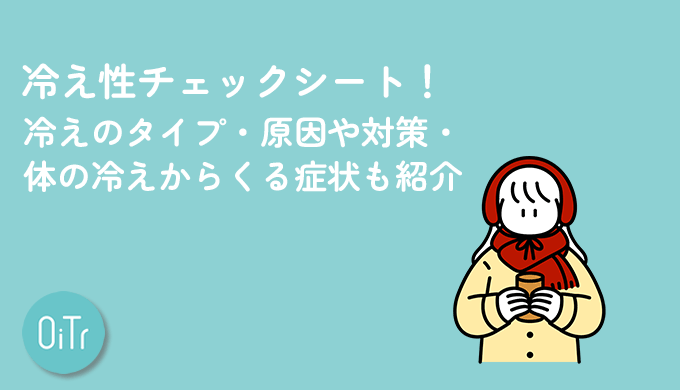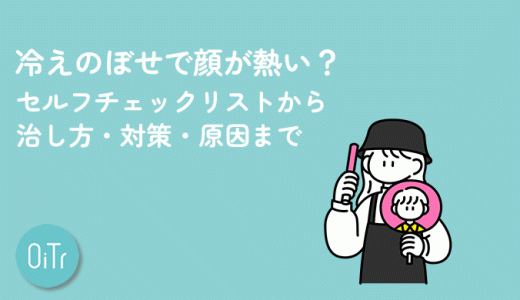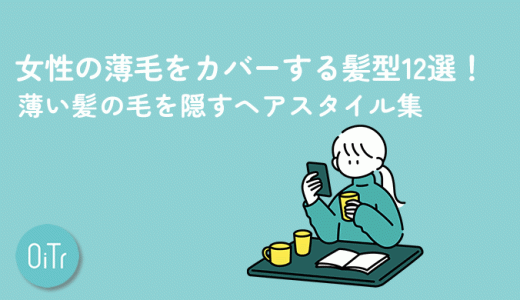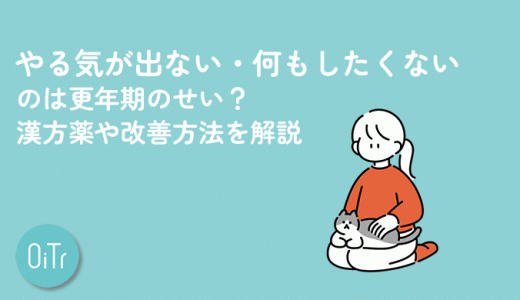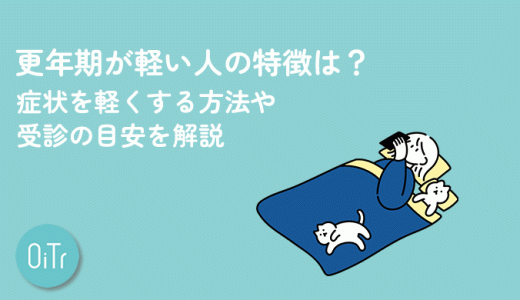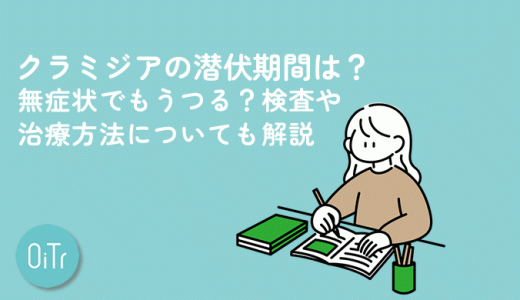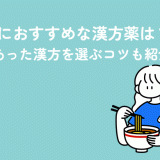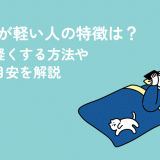手足が冷たい、生理痛がつらいなど、冷えに悩む女性は少なくありません。
冷え性は放置すると慢性化し、さまざまな体調不良を引き起こす恐れがあります。
自分が冷え性かどうか、どのタイプに当てはまるのかを知ることが、適切な改善への第一歩です。
この記事では、冷え性チェックシートとともに、タイプごとの特徴や原因、対策まで詳しく解説します。
体質に合ったケアで、冷えにくい体づくりを目指しましょう。
みんなの本音がわかる!
アンケート実施中
冷え性とひとことで言っても、その症状や感じ方は人によってさまざまです。
まずは、以下の項目に当てはまるものがないか確認してみましょう。
- 風邪をひきやすい
- 朝によくお腹を崩す
- トイレに行くことが多い
- 手足の冷えをよく感じる
- 体が冷えるとだるさ・むくみ・腹痛といった症状が出る
- 通常の体温が低い
- エアコンの効いた場所で過ごすことが多い
- お風呂はシャワーで終わることが多い
- よくイライラする
- あまり運動していない
- 疲れやすい
- 生理痛が激しい
- 生理不順が起こっている
- 原因不明の腰痛を持っている
- 貧血気味なことが多い
これらの症状は、体の冷えが関わっているケースが多いとされています。
特に5項目以上該当する人は、体質として冷え性が疑われるため、日常的な対策を意識することがおすすめです。
冷え性は人によって冷えの表れ方や原因がさまざまです。
そのため、自分に合った対策を選ぶためには、まず冷え性のタイプを知りましょう。
ここでは代表的な4つのタイプと、そのチェック方法について紹介します。
手足の先が特に冷たく感じる人に多いのが「四肢末端型冷え症」です。
血管の収縮や血流の滞りによって、体の中心から遠い部分に十分な熱が届かず、末端が冷えてしまいます。
特に、冬場やエアコンの効いた場所で症状が出やすいのが特徴です。
- 手足の冷えをよく感じる
- あまり汗をかかない
- 食事量は少ない
- 爪が折れやすい
- あまり運動をしていない
この末端冷えタイプは、血流不足や筋肉量の少なさが原因とされます。
対策としては、ウォーキングやストレッチなどで全身の血流を改善し、筋肉量を増やすことが効果的です。
手足を温めるだけでなく、体の中心部から熱を生み出せる習慣を意識しましょう。
「下半身型冷え症」は、足元が冷えるのに対して上半身は比較的温かい人に多くみられます。
下半身の血流が滞り、冷たい空気に触れることで足腰が冷えやすいのが特徴です。
特に長時間座っている人や、デスクワークが中心の人に起こりやすいタイプといえます。
- 足は冷えるが上半身は冷えていない
- 上半身は汗をかきやすい
- 食事量は普通
- 寒い場所では下半身がが冷えやすい
- 1日の大半を座って過ごす
原因としては、下半身の筋肉不足や血行不良があげられます。
そのため、定期的に下半身を動かす習慣をつけたり、骨盤まわりを温めるようにしたりすることが大切です。
デスクワーク中もこまめに立ち上がるなど意識して対策しましょう。
「全身型冷え症」は、季節や気温にかかわらず体全体が冷えている感覚がある人に多いタイプです。
慢性的な低体温により、体のあらゆる部分が冷えやすく、基礎代謝の低下や体力の衰えも伴いやすいのが特徴といえます。
- 季節に関係なく冷える
- 風邪をひきやすい
- 食事量が少なくなってきた
- 通常の体温が低い
- 体力の衰えを感じている
全身冷えタイプの場合、食事量の減少や体力の低下からエネルギー不足を引き起こしやすいため、バランスの良い食事で栄養を補い、基礎代謝を高める運動を継続することが大切です。
無理のない範囲で筋力を維持しながら、体の内側から温めていきましょう。
「内臓型冷え症」は、手足や体表面は比較的温かいのに、お腹や腰回りなど内臓が冷えてしまうタイプです。
内臓の血流が不足し、消化機能の低下やガスのたまりやすさなどを引き起こすことがあります。
- 身体や手足は暖かい
- 良く汗をかいて冷えやすい
- 食事量は多い
- 寒い場所ではお腹が冷えやすい
- 腹にガスが溜まりやすい
この内臓冷えタイプは、冷たい飲食物の摂りすぎやストレスによる自律神経の乱れが原因になりやすいです。
お腹を中心に温める腹巻やカイロを活用し、食事も温かいものを意識してとるようにしましょう。
他にもある冷え性のひとつが「局所型冷え症」で、体の一部だけに強く冷えを感じるのが特徴です。
手足の一部や背中などに限定して冷えが現れるケースが多く、神経障害や椎間板ヘルニアといった持病に関連する場合もあります。
- 手足、背中などの一部に局所的に冷えが現れ、神経系の障害やヘルニアなどの症状を抱えている人に多い
- 冷え症の治療より原因疾患の治療が必要とされる
このタイプは、冷えそのものよりも原因疾患の治療が優先されます。
まずは医療機関で根本の病気について相談し、必要に応じて冷え対策も行うとよいでしょう。
また「混合型冷え症」という、複数の冷え性タイプが組み合わさって起こるケースもあります。
特に下半身型と他の冷えが合わさることが多く、年齢を重ねることで体質の変化とともに現れるのが特徴です。
- 冷え性のタイプが混合しており、特に下半身型と他のタイプが混ざることが多い
- 年を重ねることで、若い時と異なるタイプの冷え症が合併することが原因
- 冷え症外来では全体の約25%
混合型は冷えのパターンが複雑なため、幅広い視点でケアを考える必要があります。
温活や生活習慣の見直しに加え、必要に応じて専門外来の相談も検討してみてください。
冷え性を改善するためには、体質だけでなく生活習慣や環境などの原因を知って対策を立てることが大切です。
ここでは、冷え性を引き起こす主な原因について詳しく見ていきましょう。
現代人に多い運動不足は、冷え性を招く大きな原因です。
筋肉は体の熱を生み出す重要な器官であり、特に下半身の筋肉は血液を全身へ送り出すポンプの役割も担っています。
しかし、運動習慣が少なく筋肉量が不足すると血流が停滞しやすく、手足など末端まで十分な熱が届かなくなってしまうのです。
さらに、筋肉量が少ないと基礎代謝も下がりやすく、結果として体温が維持できない状態に陥り、冷えを感じやすくなるといわれています。
基礎代謝とは、生命を維持するために最低限必要なエネルギーのことです。
加齢や生活習慣の乱れによって基礎代謝が低下すると、体内で作り出される熱の量も減り、体温が下がりやすくなります。
特に女性は筋肉量が少ないため、基礎代謝の低下が冷え性に直結しやすいのです。
代謝が落ちることで血流も悪くなり、体の末端まで温かさが届きにくくなることが、冷えを感じる原因の1つとされています。
自律神経は、体温調節や血流のコントロールを担う大切な役割を持っています。
しかし、ストレスや不規則な生活、睡眠不足などが続くと自律神経の働きが乱れ、血管の収縮や拡張がうまくいかなくなってしまうのです。
その結果、手足の末端まで十分に血液が行き渡らず、冷えを感じやすくなります。
自律神経の乱れによる体温調節機能の低下は、本人の意識では気づきにくいことも多く、慢性的な冷えにつながりやすいといえるでしょう。
女性に多い冷え性の原因として、ホルモンバランスの乱れも挙げられます。
女性ホルモンは血流や自律神経の働きにも深く関わっており、月経周期やストレス、更年期などによってバランスが崩れると体温調節がうまくいかなくなるのです。
特に、エストロゲンの分泌が低下すると血行が悪くなり、末端の冷えや内臓の冷えを引き起こしやすくなります。
ホルモンバランスの変化は自覚しにくいため、注意が必要です。
血液の流れが滞ると、体のすみずみまで熱が届けられず、冷えを引き起こしやすくなります。
血行不良は、長時間の同じ姿勢や運動不足、締め付けの強い衣服などによって起こりがちです。
さらに、血液の粘度が高い状態や自律神経の乱れも血流を悪化させる原因となります。
体の中心部では温かさを感じていても、血液が十分に巡らないことで手足などの末端が冷えやすくなるのが特徴です。
栄養バランスの偏った食生活は、冷え性の大きな原因になります。
極端なダイエットや朝食を抜く習慣、冷たい飲食物の摂りすぎなどは体を温めるエネルギーが不足し、基礎代謝が低下しやすくなるのです。
さらに、糖質や脂質に偏った食事は血液の質を悪化させ、血流を滞らせる原因にもつながります。
体を内側から温めるためには、まず食生活の乱れを整えることが大切です。
冷え性の背景には、病気が隠れている場合もあります。
貧血や甲状腺機能低下症、糖尿病などは血流や代謝に影響を及ぼし、結果として体温の低下を招くケースがあるのです。
また、自律神経に関わる病気や循環器系の不調も、体の冷えを引き起こす一因になります。
こうした疾患が原因の場合、冷え性の改善には生活習慣だけでなく医療的な治療が必要です。
お腹の冷えからくる腹痛には、腹部や腰回りをしっかり温めることが大切です。
部屋を暖かくしたり、お尻まで覆える服を選んだりして、お腹を冷やさない工夫をしましょう。
秋冬は腹巻きやカイロを使うのも効果的です。
貼る場所によって得られる温めの効果が変わるため、目的に合わせて貼る部位を選び、低温やけどに注意しながら活用してください。
また、きつい下着は血流を妨げる原因になるため、サイズの合うものを選ぶことも冷え対策として大切です。
体温が低い状態が続くと、血流や代謝が落ちて以下のような症状が出やすくなります。
- 肌荒れ
- むくみ
- 耳鳴り
- 肥満
- 胃痛・胸やけ
- 便秘・下痢
- 肩こり・腰痛
- 生理痛・生理不順(女性の場合)
さらに、汗腺や排泄器官の働きが鈍くなると老廃物の排出が滞り、血中の糖分や脂肪分が燃焼されにくくなることで、高血糖や脂質異常症を招く可能性もあります。
免疫力の低下にもつながるため、冷えは早めにケアしていくことが大切です。
女性に冷え性が多いのは、もともと男性より筋肉量が少なく、熱をつくりにくい体質だからです。
さらに女性は脂肪が多い傾向があり、この脂肪は一度冷えると温まりにくい性質を持っているため、体の深部まで温かさが届きにくくなります。
加えて、無理なダイエットや運動不足で筋肉量がさらに減ると、熱を生み出せず冷えが進行しやすくなってしまうのです。
他にもタイトな服装やガードルによる締め付け、貧血、ストレスなども血流を悪化させる要因といえるでしょう。
現代では冷暖房による寒暖差で自律神経が乱れ、体温調節がうまくいかない女性も増えています。
冷え性は体質だから仕方ないと思われがちですが、日々の習慣を少し見直すだけでも改善は十分に可能です。
ここでは、生活に取り入れやすい冷え性対策のポイントを紹介します。
冷え性対策としてまず意識したいのが服装です。
体を締め付けるようなタイトな服は血流を悪くしてしまうため、できるだけゆったりとした服を選びましょう。
また、首・手首・足首の「三首」と呼ばれる部位は血管が集まっており、ここを冷やさない工夫が大切です。
重ね着で空気の層を作りつつ、発熱インナーや温かい靴下を活用すると、効率よく体を温められます。
季節に合わせた調整も心がけましょう。
筋肉は熱を生み出す大切な器官で、冷え性の改善に直結します。
特に下半身には大きな筋肉が多く集まっているため、ウォーキングや軽いスクワットなどを習慣にして、筋肉量を増やしましょう。
筋肉がしっかりついていると血液の巡りも良くなり、体の隅々まで温かさが届きやすくなります。
いきなり激しい運動をする必要はないので、日々の生活の中で体を動かす意識を持つことから始めてみましょう。
食生活の乱れは冷え性を悪化させる大きな要因です。
冷たい飲み物や、冷たい料理を中心にした食事は体を冷やしやすくなるため、温かいスープや加熱した野菜、根菜類、生姜など体を温める食材を意識して取り入れましょう。
バランスの良い食事は基礎代謝を維持し、血流の改善にも役立ちます。
無理なダイエットはエネルギー不足を招き、冷えを助長する恐れがあるので避けましょう。
お風呂にゆっくり浸かることは、冷え性の改善にとても効果的です。
シャワーだけでは体の表面しか温まらず、深部まで熱が届きにくいので注意しましょう。
38〜40度程度のぬるめのお湯に10分以上浸かることで血流が促進され、全身の温まりが持続しやすくなります。
お風呂上がりに体が冷えないよう、入浴後は早めに衣類を着て保温し、湯冷めを防ぐことも意識しましょう。
冷え性の改善には、体質に合わせた漢方薬を取り入れる方法もおすすめです。
漢方は体のバランスを整え、血流や代謝を改善して根本から冷えを和らげる効果が期待できます。
特に、冷えを伴う生理痛やむくみなどの不調を抱えている人には相性が良いケースも少なくありません。
ただし、自己判断での使用は避け、薬剤師や専門家に相談しながら選ぶことが大切です。
冷え性は放っておくと慢性化しやすく、さまざまな体調不良の原因にもつながります。
まずはチェックシートで自分の症状や傾向を知り、冷え性のタイプを把握しましょう。
原因やタイプがわかれば、適切な対策も立てやすくなります。
日々の生活に少しずつ工夫を取り入れて、冷えにくい健康的な体を目指してください。
自分の体調に合った冷え対策を意識的に続けることで、無理なく改善を図っていきましょう。
- 冷え性には末端型・下半身型・全身型・内臓型などのさまざまなタイプがある
- 適切なチェックで自分の冷え性タイプを把握することが改善への一歩になる
- 冷えは生活習慣や体質によって起こりやすいので、食事や運動などの見直しが大切