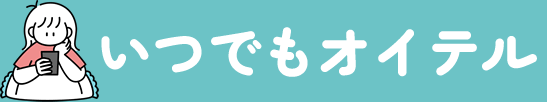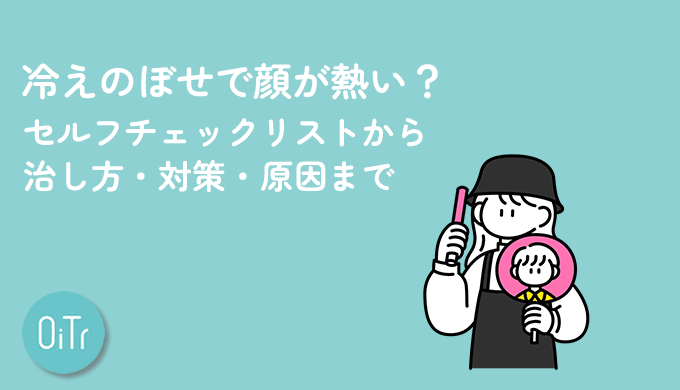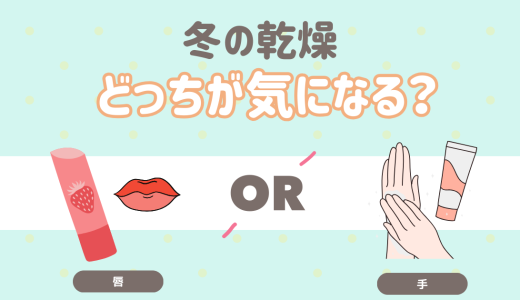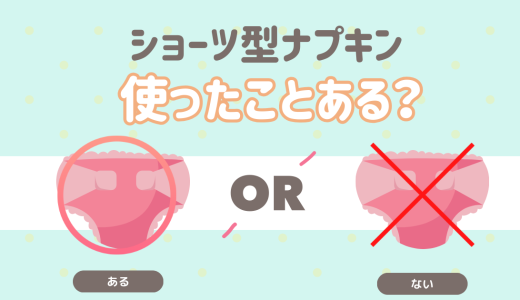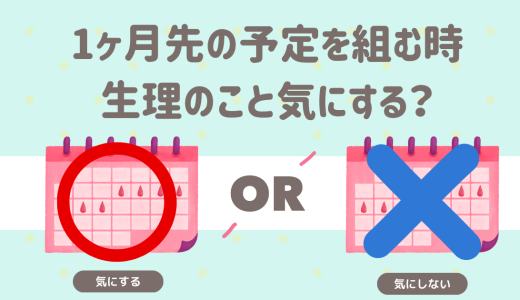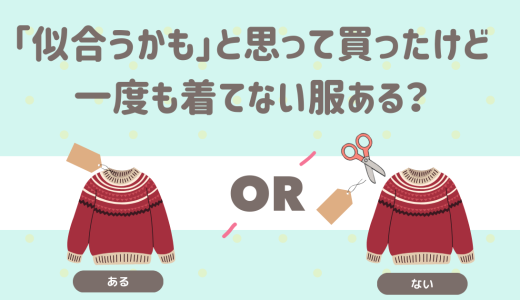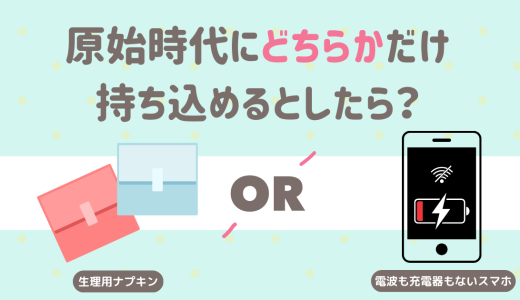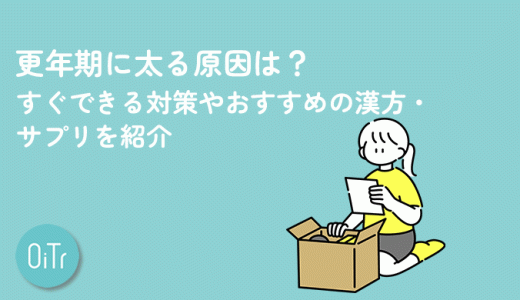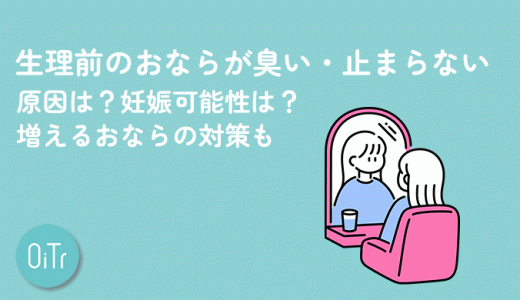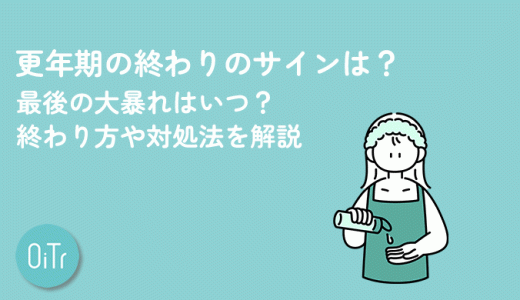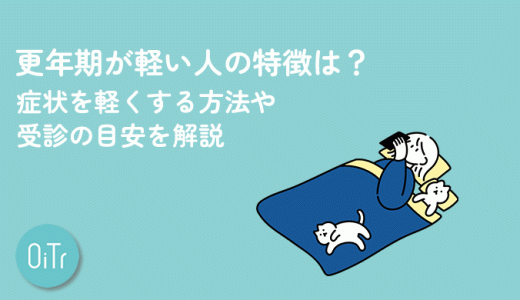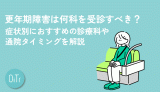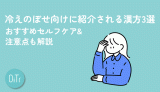手足などの末端は冷えているのに、熱っぽく感じたり頭がぼーっとすると感じたりする経験はありませんか。
暑いのに寒さを感じるのは「冷えのぼせ」と呼ばれる状態に陥っている可能性があります。
この記事では、冷えのぼせかどうか確かめるセルフチェック方法を紹介します。
対策・原因についても解説しているので、自身の生活を見直すきっかけにしてくださいね。
\アンケート実施中/
冷えのぼせは、上半身のほてりと手足の冷えが同時に現れる、一般的な冷え性よりも症状が重い状態です。
気温が高い場所で、胸から上部分のみ汗をかくのも典型的な症状の1つ。
では、なぜこのような「冷えのぼせ」が起こるのでしょうか?
まずは、そのメカニズムについて理解しましょう。
私たちの体は、体内で熱を生み出したり放出したりすることで、常に一定の体温を保とうと調整しています。
しかし、この体温調節機能がうまく働かない状態が続くと、リンパや血流の流れが滞り、結果として上半身に熱がこもってしまうことがあります。
生まれた時からエアコンを使う環境が当たり前の現代では、体温調節機能が未発達である人も増えているそうです。
そのため、20〜30代でも冷えのぼせの症状に悩まされる人も珍しくありません。
水分代謝がうまくいかなくなることも、冷えのぼせを引き起こす要因の1つ。
水分代謝とは、汗や尿として不必要な水分を体外へ排出することをいい、機能がうまく働かないと、水分が排出されず体内に溜まっていきます。
これにより、頭痛やめまい・むくみなどの症状を引き起こすほか、血行不良となるので冷え性を加速させます。
血行不良・むくみなどで身体が冷えた状態が続くと、脳だけは温度を保とうと頭を優先して血液が送られます。
その結果、血液を優先的に送られた頭は熱く、手足などの末端は冷えるという冷えのぼせを引き起こすのです。
また、頭と末端の温度差が激しい状態は、交感神経と副交感神経が頻繁に働くため、自律神経の負担も大きくなります。
冷えのぼせが続くと自律神経のバランスが乱れ生理痛が悪化したり、むくみやめまい・頭痛などの更なる症状を引き起こしたりする可能性もあるのです。
冷えのぼせは、ホルモンバランスが乱れやすい女性に特に多く見られるとされている症状です。
女性の身体は、生理周期、妊娠・出産、そして更年期など、女性ホルモンの分泌量が大きく変動します。
このホルモンバランスの変動は、体温調節機能を司る自律神経に影響を与えやすく、ホルモンバランスが乱れると自律神経のバランスも乱れやすくなります。
冷えのぼせによく似た更年期の症状である「ホットフラッシュ」も、女性ホルモン減少による自律神経の乱れが影響していると考えられているのです。
更年期の症状として知られるホットフラッシュと異なり、冷えのぼせは20代〜30代の若い人にもみられるとされています。
「冷えのぼせかどうか知りたい」という人は、下記の項目にいくつ該当するかセルフチェックしてみましょう。
1つでも当てはまれば冷えのぼせの可能性があり、数が多いほどその可能性は高まります。
「自分は冷えのぼせかも」と感じた人は、生活習慣の見直しや医療機関への相談を検討してみてくださいね。
- 手足は冷えているのに、顔だけが熱くぼーっとする
- 上半身の冷えは感じないのに、下半身・手足の冷えが気になる
- 暑くなると、胸から上が急激に熱くなり、大量に汗が出る
- 手のひら・足の裏が、じっとりとした汗でベタつく
- 冷えた食べ物・飲み物をとると、トイレが近くなる
冷えのぼせには、自律神経の乱れが関わっていると考えられています。
そのため、自律神経を乱している生活習慣を探ることがセルフケアの第一歩です。
こちらでは、冷えのぼせの原因となる生活習慣を紹介するので、自身の生活習慣を振り返ってみましょう。
十分に睡眠がとれていなかったり、睡眠の質が悪かったりすると自律神経のバランスに影響を与える可能性があり、体温調節機能の働きが鈍りやすくなってしまいます。
さらに、睡眠不足が慢性化すると集中力や意欲が低下したり、頭痛やめまいなどの症状を引き起こしたりする可能性も。
夜更かしが続いていたり、しっかりと睡眠しているのに疲れが取れなかったりする人は、睡眠環境を見直してみましょう。
冷え性と筋肉量は密接に関わっており、筋肉量の低下により、冷え性を招く可能性があります。
筋肉は体内で熱をつくる大切な役割をもっており、筋肉量が低下すると基礎代謝が低下してしまいます。
特に下半身の筋肉は、加齢により衰えやすい部位。
運動不足や筋肉の衰えを感じている人は、下半身を中心とした筋トレや有酸素運動を習慣にして、筋肉量アップを目指しましょう。
冷え性で悩んでいる人は、食事量にも注目しましょう。
ダイエットなどで無理な食事制限をしていると、食事誘発性熱産生が低下し、体内で生成される熱量に影響が出ることがあります。
また、食事誘発性熱産生は摂取する栄養素によって産生する熱量が異なり、タンパク質を摂取した時が最も大きな熱産生が起こります。
3食欠かさず食事を摂るのはもちろん、バランスの良い食事が摂れているかどうかもチェックしましょう。
冷えた環境での長時間滞在も、冷えを加速させます。
特に、オフィスなど自由に温度調節ができない環境で働いている人は要注意です。
クーラーでガンガンに冷えた環境に長時間いると、血管が収縮した状態が続き、血行不良を招きます。
また、体温調節機能を乱す要因にもなるので、冷えた環境に長時間いると冷えのぼせを引き起こしやすくなります。
冷たい飲み物や食べ物ばかり食べていると内臓が冷えてしまい、冷え性の悪化を招きます。
特に夏期は冷たいドリンクや食べ物を摂取したくなるので、夏の冷え性に悩まされる人も少なくありません。
また、内臓が冷えると血行不良や消化機能の低下を招き、冷え性以外にも様々な不調につながる可能性もあるのです。
日常的に冷たい飲み物を好んで摂取している人は、要注意です。
冷えのぼせは、日頃の生活習慣も影響しているため、冷えを感じた際のケアだけでなく根本的な原因を解消することが重要です。
こちらでは、冷え性解消のために取り入れてほしいポイントを紹介します。
まずはできることから始めて習慣化できるよう頑張ってみましょう。
お風呂は血行促進に効果的なので、できるだけ毎日ゆっくりと入浴するようにしましょう。
体を芯から温めるためには、38〜40度のぬるめのお湯に20〜30分程度ゆっくり浸かるようにしてください。
ただし、長時間入りすぎはめまいを引き起こす可能性があります。
うっすらと汗をかいてきたらお風呂から上がるようにしましょう。
自律神経を整えるために、しっかりと睡眠をとることが大切です。
交感神経が活発にならないよう、就寝1時間前までに入浴しておく、リラックスできるアロマや音楽を取り入れるのもおすすめ。
寝つきが悪い人は枕や寝姿勢などを見直して、自分が心地よく眠れるような環境を整えましょう。
東洋医学では「冷え」は病気の1つとされ、体質に合わせた漢方処方が行われることがあります。
冷え性に効果があるとされている漢方は体質や冷えタイプに応じて異なり、冷えのぼせには「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」が多く用いられます。
ただし、自分の体質に合っていない漢方は返って悪化を招く可能性もあるので、漢方を取り入れる際は専門家に相談するようにしましょう。
毎回の食事は身体を温めるための大切なエネルギー源です。
バランスよく栄養素を摂取するのはもちろん、筋肉をつくるタンパク質はしっかりと摂取するよう意識しましょう。
また、生姜や長ねぎ・カボチャ・玉ねぎなどの野菜やクルミ・栗などのナッツ類は体を温めてくれる食材だといわれているので、工夫して料理に取り入れてくださいね。
他にも、大豆製品や赤ワイン・お茶などに含まれるポリフェノールには血行を改善する作用があるので、冷え性の改善に役立つといわれています。
冷えのぼせの症状が辛い時は、一時的に楽になると感じられるケアもあります。
「冷え」と「ほてり」という異なる症状が混在しているため、冷えやほてりを感じる部位に応じて適切な対処をすることが大切です。
自宅はもちろんオフィスでも手軽にできる対策ばかりなので、ぜひ試してみてくださいね。
冷えのぼせは冷え性の一種なので、体全体を冷やしてしまうのはNG。
熱っぽさを感じる顔や脇の下など部分的に冷やすことで、ほてりを和らげることができます。
水で絞った冷たいタオルを当てたり、冷たい風を一時的に当てたりして熱を逃がすのがおすすめです。
首には大きな血管や筋肉があるので、首や肩を温めることで全身に温まった血液を巡らせられます。
頭が熱っぽいのでつい冷やしてしまいがちですが、首や肩は冷やしすぎないよう注意しましょう。
また、首の後ろを温めると副交感神経が優位になり、リラックスしやすいといわれています。
ストールやネックウォーマー、タートルネックなどを上手く活用して、首や肩を冷やしすぎないよう調節しましょう。
冷えを強く感じやすい足元は、しっかり温めてあげることが大切。
靴下やレッグウォーマー、スパッツなどで足元が冷えすぎないようにしましょう。
ただし、ガードルなどの締め付けの強いアイテムは、血の巡りを滞らせる可能性があるので避けたほうがいいです。
オフィスなどの温度調節の難しい環境に長時間滞在する人は、ひざ掛けなども準備しておくと安心ですよ。
十分に足元を温めているけど冷える時には、下半身を動かして血流の巡りを改善しましょう。
下半身の冷えにおすすめなのが、太い血管が通っているふくらはぎをしっかりと伸ばせるかかと上げ運動。
椅子に浅く腰かけた状態で、両足のかかとをゆっくりと上げ下げしましょう。
座ったままでできるので、職場や自宅でも冷えを感じた際にぜひ試してみてくださいね。
体を温めたい時におすすめなのが「三陰交」と呼ばれるツボ。
内くるぶしの頂点から指4本分上の場所にあるツボで、筋肉の境目にあります。
伝統的に、三陰交は下半身の冷えや不調時に使われることがあるツボとして知られています。
下半身の冷えを感じた際に、息をゆっくりと吐きながら押す、吸いながら離すを繰り返してあげましょう。
冷えのぼせは、自律神経の乱れによって引き起こされる症状で、更年期の女性だけでなく若い世代の人もなる可能性があります。
日々のストレスや不規則な生活習慣などを続けていると、自律神経のバランスが乱れて冷え性が悪化し、冷えのぼせを引き起こすかもしれません。
この記事で紹介したセルフチェックを通して「もしかして、冷えのぼせかも…」と感じたら、まずは自身の生活習慣を見直して冷えにくい体作りを目指しましょう。
日々の少しずつの心がけが体調管理に役立つので、無理のない範囲で習慣にしてくださいね。
- 冷えのぼせは「自律神経失調型」の冷え症状
- 手足などの末端が冷えているのに頭が熱っぽいのは「冷えのぼせ」の可能性あり
- 冷えのぼせの原因は睡眠不足・食生活などの生活習慣が大きく影響している
- 毎日の入浴やバランスの良い食生活が冷えのぼせの改善に役立つ
- 頭や脇の下は冷やして、他の部位は保温して冷やしすぎないようにしよう