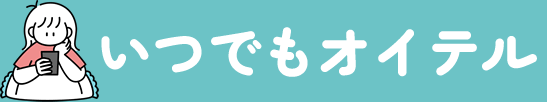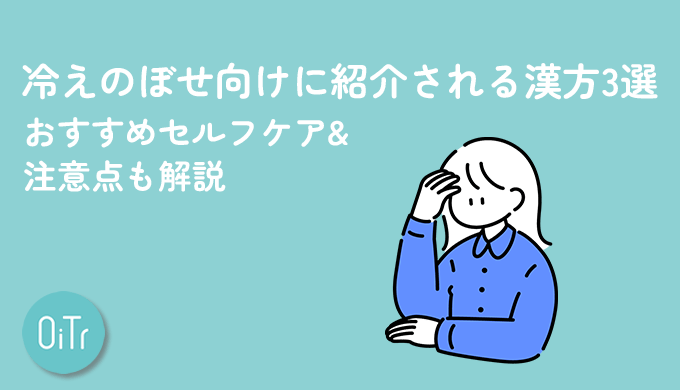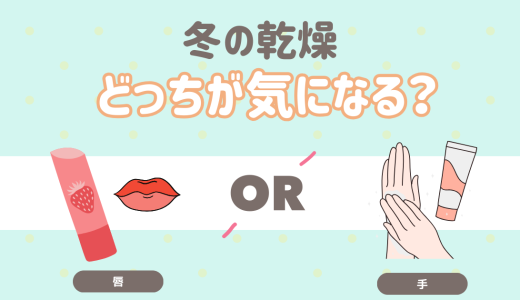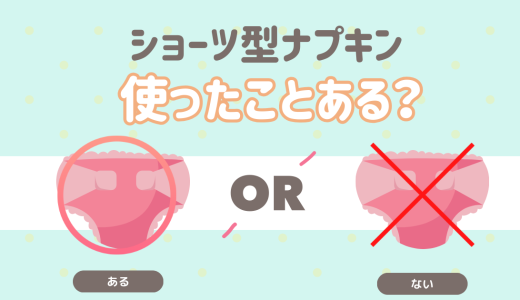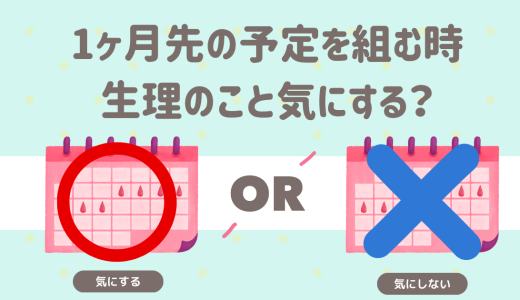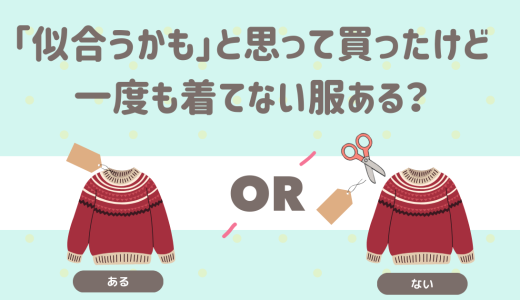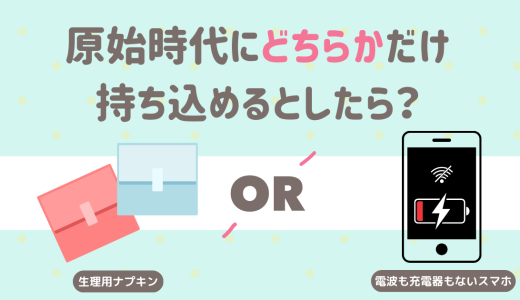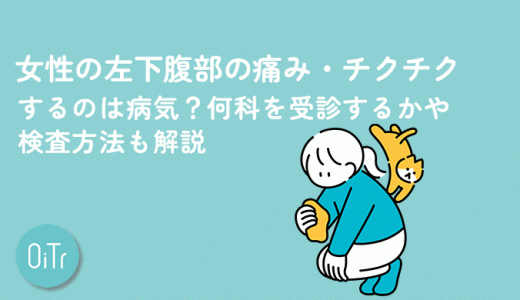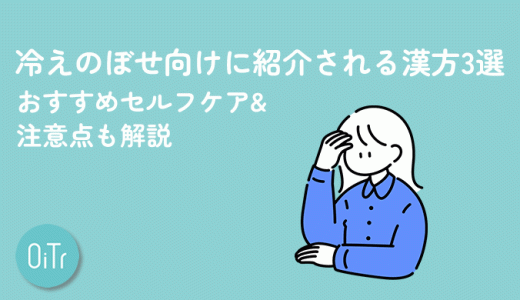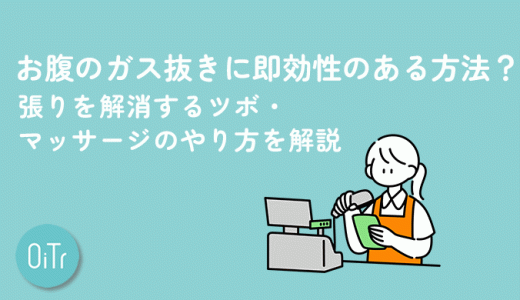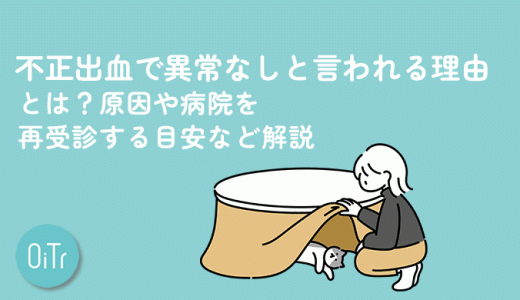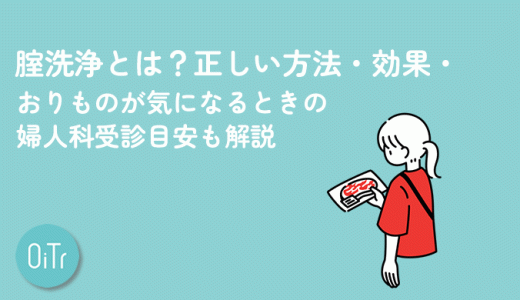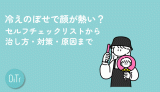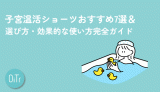PR/この記事は一部プロモーションを含みます
「足元は冷えているのに、顔は熱い…」という冷えのぼせに悩む女性は少なくありません。
ホルモンバランスや自律神経の乱れが関係することも多く、体質に合ったケアが大切です。
なかには、冷えのぼせに対して、漢方で対応したいと考える人もいるでしょう。
この記事では、冷えのぼせがある人に使われる漢方や、冷えのぼせの考えられる原因、セルフケアのポイントなどをわかりやすく解説します。
\アンケート実施中/
「冷えのぼせに対して選ばれる漢方薬を知りたい」と思う人は多いでしょう。
しかし、漢方は冷え対策に使われるものだけでも多くの種類があり、自分では選べないこともあるかもしれません。
ここでは、冷えのぼせに使われる漢方の代表例を紹介します。
ただし、体質によっては他の漢方が選ばれる可能性があることを押さえておきましょう。
また、これらの漢方を使用する際は、医師や薬剤師に相談の上でお使いください。
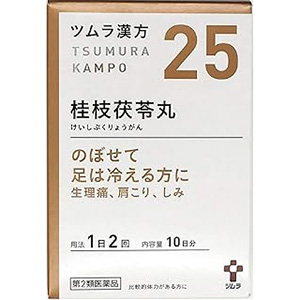
桂枝茯苓丸 けいしぶくりょうがん ツムラ
ツムラ
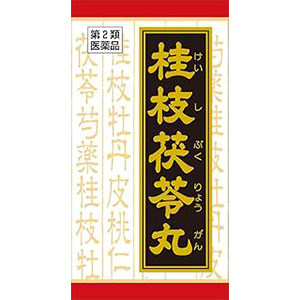
桂枝茯苓丸 けいしぶくりょうがん クラシエ
クラシエ
漢方医学において、桂枝茯苓丸は下半身の冷えが特に強い人、月経不順や生理痛に悩んでいる人に対して処方されることが多い漢方です。
漢方理論では身体の巡りがうまくいかないと、温かいものは上にのぼり、冷たければ下に降りる性質をもつため、顔は熱いのに手足は冷える状態になります。
比較的体力がある人向けの漢方で、冷えのぼせだけでなく、肩こりやめまいなどがみられる人にも処方される漢方です。
ツムラやクラシエでは、第二類医薬品としてドラッグストアや薬局で購入できます。
医療用では、ツムラ25番に該当する漢方です。
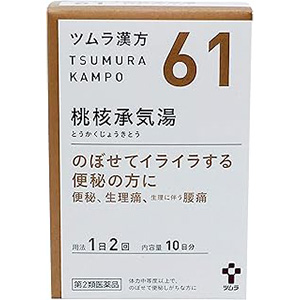
桃核承気湯 とうかくじょうきとう ツムラ
ツムラ
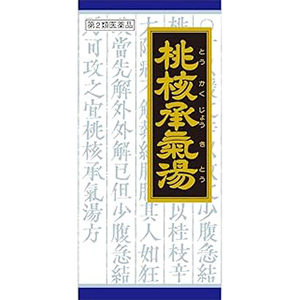
桃核承気湯 とうかくじょうきとう クラシエ
クラシエ
桃核承気湯は、生理前の痛みや生理痛、のぼせなどの症状がある人に古くから用例のある漢方です。
体力がある人に使われる漢方なので、体質を判断したうえでの検討が必要になります。
体力が中等度以上で、のぼせて便秘しがちな人の生理不順や、腰痛などに処方されることがあるとされる漢方です。
ツムラやクラシエでは、第二類医薬品としてドラッグストアや薬局で購入できます。
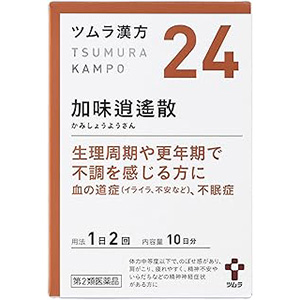
加味逍遙散 かみしょうようさん ツムラ
ツムラ
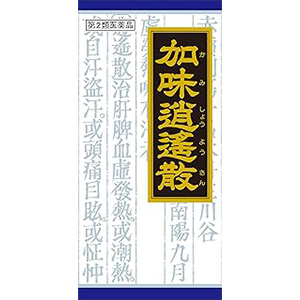
加味逍遙散 かみしょうようさん クラシエ
クラシエ
加味逍遙散は、漢方分野でいらだちや、のぼせを訴える人に処方されることがある処方です。
自律神経のバランスや血の巡りに対して用いられることがあるとされ、冷えのぼせがある女性に選ばれることもあります。
体力が中等度以下で、肩こりや疲れやすさ、冷えを感じやすい人に使われることもある漢方です。
同じ冷え症でも、全身が冷える「全身型」、手足が冷える「四肢末端型」、上半身は熱く下半身が冷たい「上熱下寒(じょうねつげかん)型」の3タイプに分けられます。
冷えのぼせは「上熱下寒型」です。
ここからは、冷えのぼせが起こる原因を解説します。
自律神経が乱れると、体温調節機能が正常に働かず、冷えのぼせが起こることがあります。
主な原因は、不規則な生活習慣やストレスなどです。
同じく脳の視床下部がコントロールしている女性ホルモンの分泌が乱れると、自律神経にも影響が出ます。
血行不良も冷えのぼせの原因の1つです。
たとえば、外気と室内の気温差が大きく体温調節がうまくいかなかったり、長時間の冷房や冷たい飲み物などで身体を冷やしたりすると、血行不良が起こりやすくなります。
すると血管が収縮し、末端まで血液がいかなくなることで、むくみが生じて冷えを感じやすくなるのです。
脳だけは温度が低下しないようにと、頭部への血流が優先され血流配分が変化し、顔のほてりや、手足は冷えとして感じられることがあります。
冷えのぼせは、更年期障害による血管運動症状の可能性もあるかもしれません。
更年期は、閉経前の5年間と閉経後の5年間をあわせた10年間のことで、この時期は卵巣機能が低下し、女性ホルモンの分泌が急激に少なくなります。
するとホルモンバランスが崩れ、自律神経の乱れを引き起こす一因となることがあります。
そのため更年期に入ってから、冷えのぼせがひどくなったと感じる人も多いでしょう。
漢方医学では、冷えやのぼせをはじめとした心身の症状は「気(き)・血(けつ)・水(すい)」の異常が関係していると考えられています。
気血水の特徴は、以下のとおりです。
- 気:エネルギーや生命力を巡らせる力
- 血:栄養を含む血液の流れ
- 水:体内の潤いや代謝に関わる水分
冷えとのぼせが同時に起こるのは、気と血の流れが滞ることが一因とされることがあります。
血流が滞ると、全身に熱がまんべんなく行き渡らず、体内で熱の分布が偏るのです。
こもった熱は上にのぼる性質があるため、冷えのぼせが起こります。
冷えのぼせでは、気や血の巡りに着目した漢方が検討されることがあります。
冷えのぼせを感じる時は、漢方以外にも今日からできるセルフケアを取り入れるとよいでしょう。
ここからは、簡単にできるセルフケアについて紹介します。
日常生活に1つでもよいので、取り入れてみてくださいね。
足湯や半身浴で下半身を中心に温めるのも、一つの方法です。
冷えのぼせがある人は、長時間湯船に浸かると身体が温まる前にのぼせる可能性があります。
シャワーを浴びただけでは手足が冷えたままのため、入浴方法を見直してみるのもいいでしょう。
冷えのぼせを和らげるためには、自律神経を整えるために生活習慣を整えることが大切だとされています。
- 睡眠をしっかりとる
- 身体を温める食材や巡りを意識した食材を取り入れる
- 冷たい飲食物を避け、温かく消化のよいものを取り入れる
- タイトな下着や衣類の着用を避ける
- 冷房の温度を調節する
できる範囲で取り入れることで、体調の変化を感じる人もいるようです。
下半身を中心に筋肉を動かすことで、血液の巡りがよくなり、冷えを感じにくくなる場合も。
女性は男性よりも筋肉が少ないため、冷え症になりやすいとされているのです。
ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、血液を心臓に戻すポンプの役割をもちます。
スクワットやつま先立ちのような簡単な運動を毎日取り入れることで、体の冷えやむくみへの対策の一つとなるでしょう。
冷えのぼせが気になる人のセルフケアとして、ツボ押しがよく取り上げられます。
一般的に知られているツボの例を以下にまとめました。
- 三陰交(さんいんこう):くるぶしの骨の1番上から指4本分上にある
- 労宮(ろうきゅう):手のひらの真ん中のくぼみ部分にある
- 合谷(ごうこく):手の甲側で親指と人差し指のつけ根にある
無理に強く押すのではなく、心地よいと感じる程度の刺激でとどめるといいでしょう。
漢方はドラッグストアや薬局で手軽に購入できるため、試してみたい人は多いでしょう。
副作用が少ないと感じる人もいますが、すべての人に当てはまるわけではなく、服用開始前や服用中の注意点があります。
ここからは、冷え・のぼせを和らげたい人が、漢方を取り入れるときに注意すべきポイントをみていきましょう。
自己判断で漢方を服用するのではなく、医師や薬剤師に相談しましょう。
体質に合っていない漢方を服用すると、効果が感じにくかったり、体調の不良を感じたりすることがあるためです。
漢方は自分に合っているかが重要なため、同じ冷えのぼせでも選ぶべき処方は人によって異なります。
飲み始めて冷えのぼせが悪化したり、別の不調を感じたりした場合は、すぐに服用を中止して専門家に相談してください。
漢方を飲み始めてから変化を実感するまでは、数週間~数ヶ月かかるとも言われています。
漢方は、身体の内側から気血水のバランスを重視した考えに基づいているため、徐々に変化があらわれることも多いのです。
ただし、1ヶ月程度服用しても思うような変化が感じられない場合は、自己判断せず医師や薬剤師に相談しましょう。
冷えのぼせは、身体の熱の巡りが乱れることで起こる不快な症状のひとつです。
冷えとほてりが同時に現れるため、対処が難しく感じることもあるでしょう。
漢方では体質や体調に応じてさまざまな処方が用いられています。
自分の体質や症状に合わせた漢方を取り入れることで、体調の変化を感じる人も。
漢方だけでなく、生活習慣やセルフケアにも目を向けて、できることから少しずつ整えていきましょう。
また、漢方は誰にでも同じように効くものではないため、自己判断せず医師や薬剤師に相談しながら取り入れることが大切です。
- 冷えのぼせは「上半身ののぼせ+下半身の冷え」が同時に起こる状態
- 自律神経やホルモンバランスの乱れ、血行不良などが原因になる
- セルフケアでは、足湯・半身浴・運動・ツボ押しなどが取り入れられる
- 漢方の服用は自己判断せず、必ず医師や薬剤師に相談を