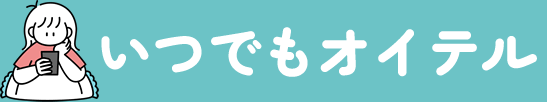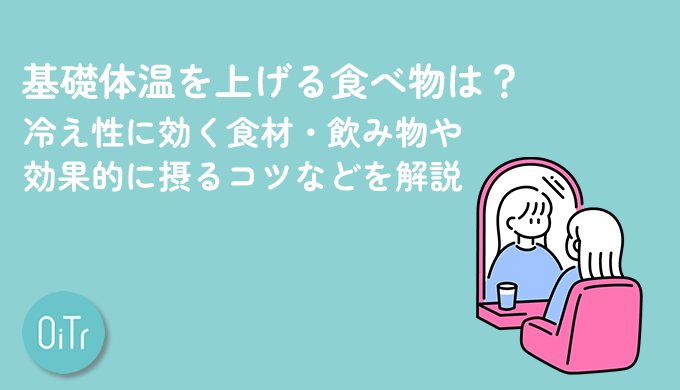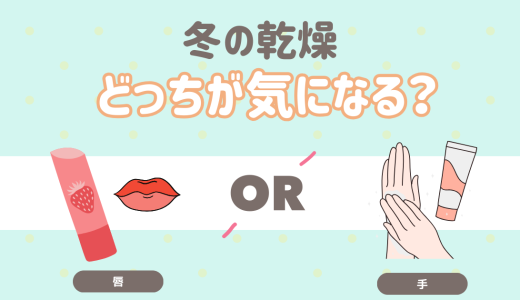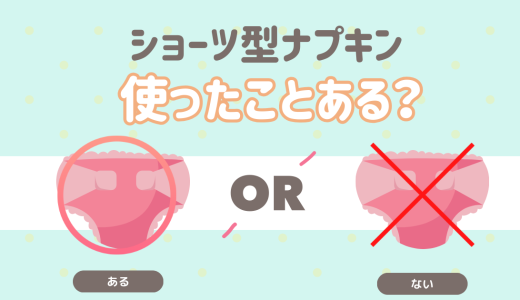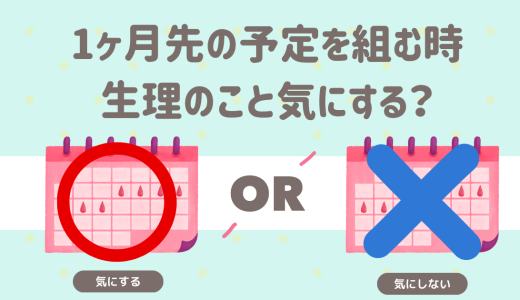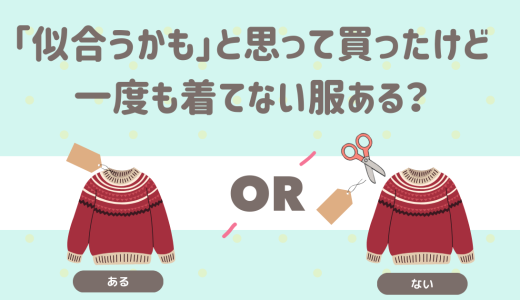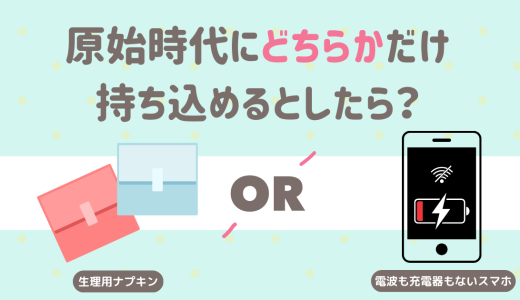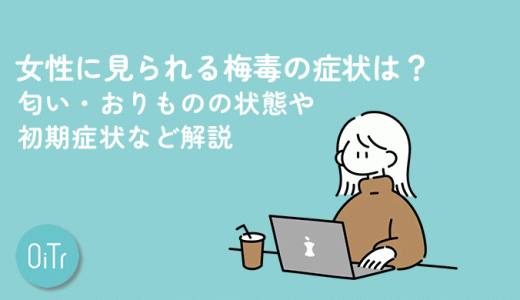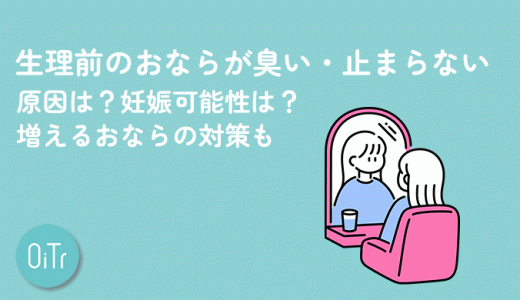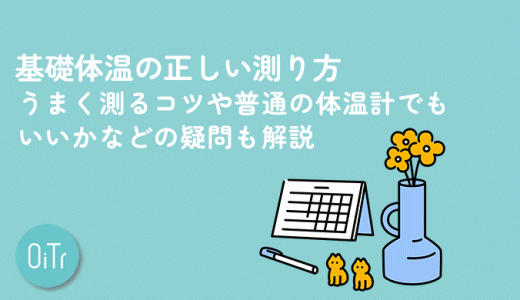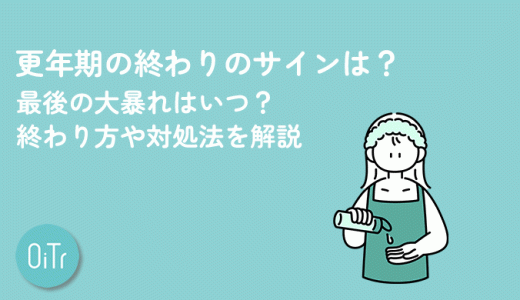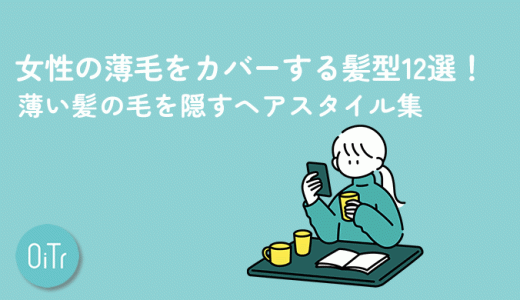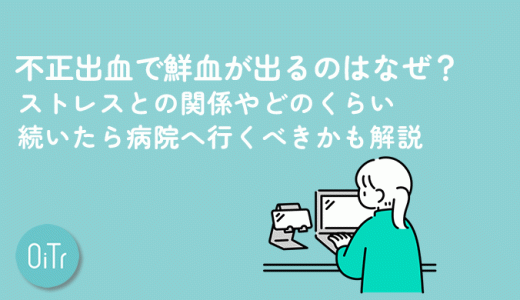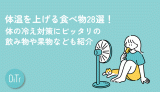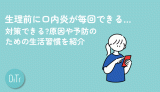冷え性に悩んでいる方の中には、手足の冷えだけでなく、朝の体温の低さや代謝の悪さに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、日々の食事や生活習慣を見直して「基礎体温」を上げることが大切です。
この記事では、体を内側から温める食材や飲み物、効果的な摂り方、生活習慣の工夫までをわかりやすく解説します。
無理のない温活で、冷えにくい身体を目指しましょう。
\アンケート実施中/
基礎体温が低いと感じている方は、体を温めやすい特徴を持つ食べ物を意識して取り入れることが大切です。
ここでは、冷えに悩む方におすすめしたい食材の特徴を4つに分けて紹介します。
基礎体温を上げるには、筋肉を増やして代謝を高めることがポイントです。
そのためには、筋肉の材料となる次のような食材を、毎日の食事でしっかり摂りましょう。
- 赤身肉(牛もも、豚ヒレなど)
- 鶏むね肉やささみ
- 卵
- 納豆・豆腐・大豆製品
- まぐろ・さば・たらなどの魚
- ヨーグルト・チーズなどの乳製品
これらの食材は、1食あたり20〜30gを目安に、毎日の食事に取り入れるのがおすすめです。
代謝を助けるビタミンB群を摂れる食材を組み合わせれば、筋肉量の維持や基礎代謝の向上、さらには免疫力を強めることにもつながります。
東洋医学やマクロバイオティックの世界では、根菜類を中心とした「地面の下で育つ食材」には、体を内側から温める働きがあるとされています。
とくに以下のような野菜は熱をため込む性質を持っているため、冷え性に悩む方は、毎日の食事に意識して取り入れましょう。
- にんじん
- ごぼう
- れんこん
- さつまいも
- 玉ねぎ
- 生姜
- 山芋
見分け方の目安としては、「地中で育つ」「色が濃い」「冬が旬」という3点を意識すると選びやすくなります。
伝統的な食養生では、寒冷地で育つ野菜や果物は厳しい環境でも育つよう冬に旬を迎えるものが多く、体を温める性質を持つと考えられています。
とくに以下のような食材を取り入れることで、体内に熱を蓄えやすくなり、基礎体温の向上につながります。
- ごぼう
- れんこん
- にんじん
- 玉ねぎ
- かぼちゃ
- じゃがいも
- りんご
これらを旬の時期に合わせて取り入れることで、自然と栄養価も高まり、効率よく体質改善を目指せます
血流促進につながる栄養素(鉄分・カロテン・ポリフェノール等)を含みやすい、赤・オレンジ・黄色・黒などの濃くて温かみのある色をした食材は、体を温める傾向があるとされています。
血流を促したり、代謝を高めたりするためにも以下の食材を取り入れてみましょう。
- にんじん
- かぼちゃ
- ごぼう
- さつまいも
- 赤身の肉や魚(牛肉・まぐろ・鮭など)
- 黒ごま・黒豆
ただし、トマトや赤ピーマンなど、色は濃くても体を冷やす性質を持つものもあるため、産地や旬の時期、調理法とあわせて見極めることが大切です。
食材と同じように、体を内側から温めるためには飲み物の選び方も大切です。
ここでは、基礎体温の上昇をサポートする飲み物と、その働きについて紹介します。
白湯は、もっとも手軽に取り入れやすい温活ドリンクです。
体温が低くなる朝や寝る前に飲むと、内臓がゆっくり温まり、基礎代謝のサポートにもつながります。
水道水をやかんで10〜15分沸騰させたものを冷まして飲むのが基本ですが、電子レンジで加熱したミネラルウォーターでもOKです。
冷たい飲み物を控え白湯を習慣にすることで、体のめぐりを整え、冷えにくい状態を目指せます。
ルイボスティーは、体を温める作用があり、冷え性対策に役立ちます。
南アフリカ原産のルイボスという植物から作られ、赤みがかった色とやさしい味わいが特徴です。
活性酸素を抑える抗酸化酵素「SOD(スーパーオキシドジスムターゼ)」などを含んでおり、代謝のサポートが期待できます。
ノンカフェインなので、寝る前に飲んでも睡眠の妨げになりません。
妊娠中や授乳中の方にもおすすめできる飲み物です。
シナモンティーには、血行を促進する成分「シンナムアルデヒド」が含まれており、毛細血管の働きを助け、血流を整えることで冷え性改善に役立つとされています。
市販の紅茶にシナモンスティックを入れるだけで簡単に作ることができ、シナモンパウダーで代用しても十分効果が期待できるでしょう。
スパイスの香りが気分をほぐしてくれる点も、日常に取り入れやすい魅力のひとつです。
ココアに含まれるカカオポリフェノールやテオブロミンには、血管を拡張して血流を促す働きがあるといわれています。
そのため、体の内側から温まりやすく、冷え性の方にも適した飲み物です。
また、鉄分も含まれているため、貧血気味の方にもおすすめできます。
甘くして飲む場合は、砂糖を加えすぎないよう注意しましょう。
スパイスが平気な方は、シナモンを少量加えると温め効果がより高まります。
せっかく体を温める食材を選んでも、食べ方によっては十分な効果が得られないこともあります。
ここでは、基礎体温をしっかり上げるために意識したい、日々の食事での工夫を見ていきましょう。
体を温める食材でも、冷たいまま食べると効果が十分に発揮されません。
とくに冷え性が気になる方は、スープや煮物、蒸し料理など、加熱調理した温かい料理で取り入れることが大切です。
温かい食事は内臓の働きを助け、消化吸収をスムーズにしてくれるメリットもあります。
朝はとくに体温が低いため、具だくさんのみそ汁や温野菜などを取り入れて、体の内側からじんわり温めましょう。
朝食は、1日の体温リズムを整える大切なスイッチです。
寝ている間に下がった体温を上げるには、朝にしっかりとエネルギーを補給する必要があります。
温かい汁物やたんぱく質を含むメニューを取り入れて、内臓が目覚めさせてあげましょう。
朝食を抜いてしまうと体が省エネモードになり、血流も悪くなりがちです。
ごはんなどの糖質も適度に摂り、体温の維持に努めましょう。
食事中によく噛むことで、唾液や胃液の分泌が促され、消化吸収がスムーズになります。
これにより内臓の働きが活発になり、体の内側から自然と熱が生まれやすくなるのです。
また、咀嚼には自律神経を整える作用もあり、血流の促進や体温の安定にもつながります。冷え性の方は、早食いを避けて1口につき30回ほど噛むことを意識してみてください。
丁寧に食べることが、体を温める第一歩になります。
基礎体温を上げるには、食事だけでなく日々の生活習慣にも目を向けることが大切です。
ここでは、体を内側から温める食べ物と相乗効果が期待できる、身近な習慣を紹介します。
食べ物で体を温めても、血流が悪いままだと全身に熱が巡りにくくなります。
そんなときに取り入れたいのが、湯船に浸かる習慣です。
ぬるめのお湯に10〜15分浸かるだけでも、血行が促されて、食事で得たエネルギーや栄養がしっかり全身に届けられます。
とくに夜の入浴は、寝つきやすくなるだけでなく、体温の底上げにもつながるのです。
シャワー派の方も、週に数回は湯船で温まるようにしましょう。
食べ物で栄養をしっかり摂っても、それを熱に変えるには筋肉の力が必要です。
筋肉には体温を維持する働きがあるため、筋トレは基礎体温アップに欠かせない習慣といえます。
とくに女性は筋肉量が少ない傾向があるため、軽めのスクワットやつま先立ち運動など、無理なく続けられるメニューを取り入れてみてください。
食事と筋トレをセットにすることで、代謝が上がり、冷えにくい体へと近づいていきます。
朝は体温がもっとも低くなる時間帯です。
そこに白湯を取り入れることで、内臓がゆっくり温まり、代謝が動き出します。
食べ物で体を温めたい方にとって、白湯はその効果を引き出す「はじまりの一杯」ともいえる存在です。
カフェインが気になる方でも安心して取り入れられるので、温活の第一歩として習慣にしてみてください。
おやつの時間も、体を温めるチャンスに変えることができます。
とくにナッツ類には、ビタミンEや食物繊維、良質な脂質が豊富に含まれており、血流を促す働きが期待できるのでおすすめです。
食事だけでは補いきれない栄養をプラスできるため、温活中の間食に取り入れてみましょう。
アーモンドやくるみ、カシューナッツなどを素焼きで取り入れるのがポイントです。
甘いお菓子の代わりにナッツを選ぶことで、基礎体温の維持にもつながります。
基礎体温を上げるには、特別なことをするよりも、毎日の食事や習慣を少し見直すことが近道です。
また、栄養バランスを整えることも、温活には欠かせません。
さらに、身体を温める食材を選び、飲み物や生活習慣にもひと工夫を加えることで、冷えにくい体を少しずつつくることができます。
できることから少しずつ取り入れて、無理なく温活を続けてみましょう。
体の内側から整える意識が、体質改善へつながります。
- 基礎体温を上げるにはタンパク質や根菜など、体を温める食材を積極的に選ぶ
- 飲み物は白湯やルイボスティーなど体を温めるものを意識する
- 食材は冷たいままでなく、温かい料理で食べるようにする
- 朝食・入浴・運動・ナッツの間食など生活習慣からも温活を意識する