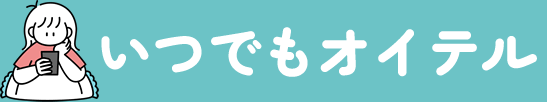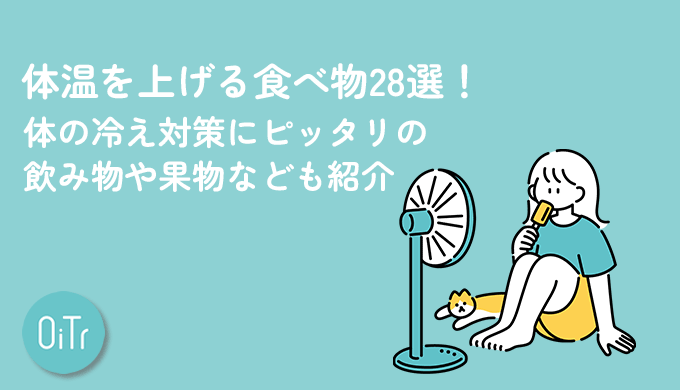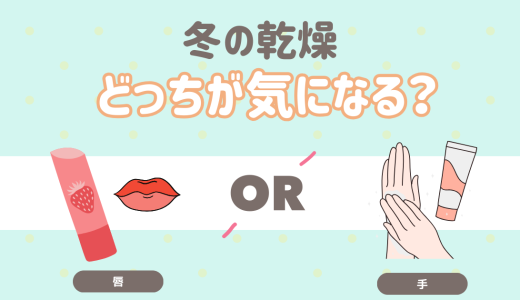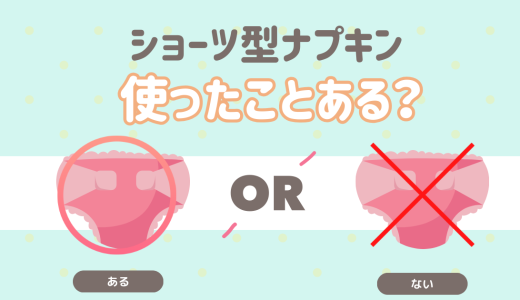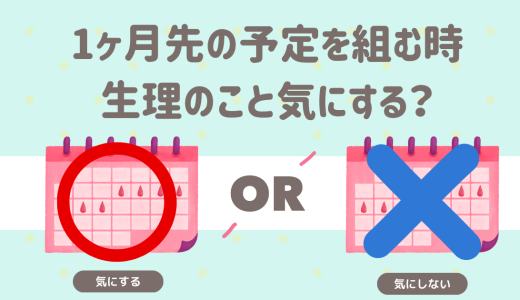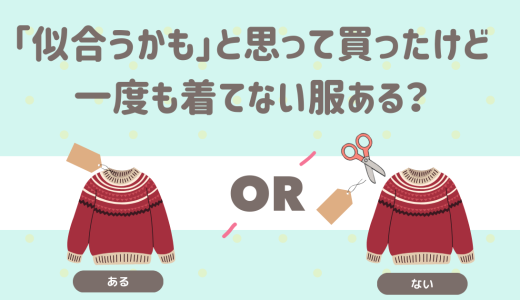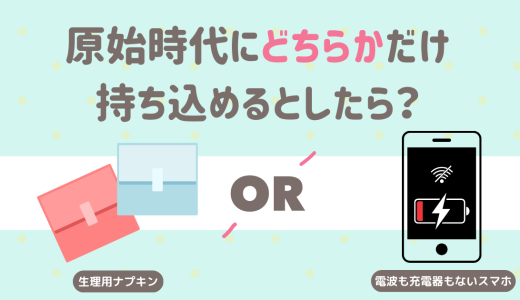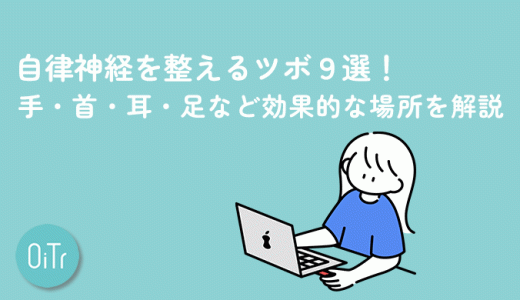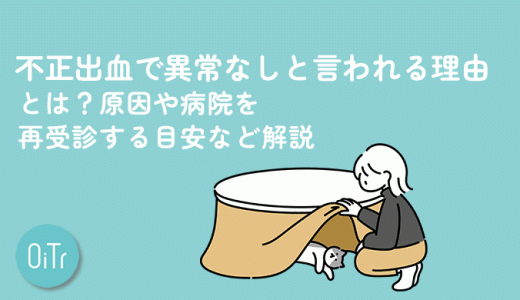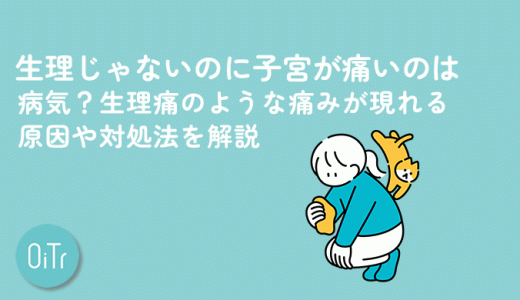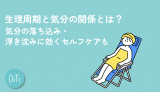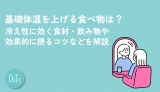冬の寒さや手足の冷えに悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
体温が低いと血行が悪くなり、代謝や免疫力の低下にもつながりやすいのです。
そこでこの記事では、今すぐ取り入れやすい「体温を上げる食べ物」を野菜・肉・スパイス・果物・飲み物に分けてご紹介します。
毎日の食事から温活を始めて、冷えにくい体づくりを目指しましょう。
\アンケート実施中/
野菜のなかには、体を内側から温めてくれるものがあり、冷えを感じるときこそ意識して取り入れましょう。
ここでは、体温アップに効果的な野菜を5つご紹介します。
生姜は、体温を上げる食べ物として定番の食材です。
生の状態には「ジンゲロール」という成分が多く含まれ、血行を促進する働きがあります。
加熱や乾燥を加えることで「ショウガオール」に変化し、体の深部からじんわり温めてくれるのが特徴です。
冷え症の改善には、加熱調理した生姜のほうが効果的とされています。
みそ汁やスープにすりおろして入れたり、ご飯を炊くときに千切りを加えたりと、さまざまな料理に使える万能さも魅力です。
ねぎには、血行を促進する「硫化アリル」が含まれており、体の冷えを和らげる働きがあります。
香り成分として知られる硫化アリルには、免疫力を高める作用もあるため、風邪の予防にも効果が期待できるのが特徴です。
とくに白い部分に多く含まれているため、煮込み料理や汁物に加えることで温かさを引き出せます。
薬味や炒め物にも活用しやすく、毎日の食事に取り入れやすいのも魅力なので、冷えが気になる季節には積極的に取り入れましょう。
とうがらしに含まれる「カプサイシン」は、血行を促進する働きを持った、体温を一時的に高めてくれる成分です。
カプサイシンは発汗をうながす作用もあるため、寒い季節に取り入れることで体の内側から温まりやすくなります。
炒め物やスープに少量加えるだけで、辛味と温熱効果が得られるのも魅力です。
ただし、とりすぎると汗の蒸発によって逆に体を冷やしてしまうおそれがあるため、適量を意識しましょう。
かぼちゃには、体を温める働きをもつ「ビタミンE」が豊富に含まれています。
ビタミンEには血管を広げて血流を良くする作用があり、冷えの緩和に役立つ栄養素です。
また、抗酸化作用によって血管の老化を防ぎ、血行を保ちやすくする点もメリットといえるでしょう。
かぼちゃは、煮物やスープなどに使いやすく、食卓に自然に取り入れやすい点も魅力です。
甘味を活かして間食に取り入れるなど、日常のなかで積極的に活用することで、温活効果を高めることもできるでしょう。
にんにくには「アリシン」という成分が含まれており、血行を促進して体を芯から温める働きがあります。
アリシンは、強い香りのもとにもなっている成分で、ねぎや玉ねぎなどにも含まれる硫化アリルの一種です。
冷え性の対策だけでなく、免疫力を高める効果も期待されており、寒さが厳しい季節に積極的に取り入れたい食材とされています。
炒め物やスープに加えるだけで風味も増し、料理の満足感もアップするので、日々の食事のなかに、無理なく取り入れていきましょう。
肉や魚には、基礎体温の維持に欠かせないたんぱく質や鉄分が多く含まれており、冷えやすい方にとっては、代謝を高めるうえでも大切な食材です。
ここでは、体を内側から温める働きがある肉類・魚介類をご紹介します。
肉類は、たんぱく質が豊富なうえ、体内でエネルギーに変わる際に熱を生み出すため、体を温めるのに役立ちます。
とくに冷えの緩和に適しているのは、以下の3つです。
- 牛肉
- 鶏肉
- 羊肉
なかでも羊肉は、寒冷地での食文化に根付いており、食事誘発性熱産生が比較的高いとされ、体を温める食材として注目されています。
牛肉や鶏肉にも代謝を助ける成分が含まれており、スープや煮込み料理などに取り入れやすい点も魅力です。
食事にこれらの肉類をうまく取り入れることで、冷えにくい体づくりをサポートできます。
魚介類のなかにも体を温める働きをもつ種類があり、とくに食べておきたいのは、以下のような魚です。
- 青魚
- 赤身魚
青魚にはDHAやEPAといった良質な脂質が含まれており、血流を促進して結果的に冷えをやわらげる効果が期待できます。
赤身魚はたんぱく質や鉄分が豊富で、代謝をサポートし、健康的な体温維持に役立つ栄養素を含んでいます。
サバやサンマ、アジ、マグロ、カツオなど、日常の食卓に取り入れやすい魚も多いため、バランスよく摂取していきましょう。
スパイスには、香りや辛味によって血流を促し、体を温める働きのあるものが多くあります。
ここでは、温活に役立つ代表的なスパイスを見ていきましょう。
シナモンは、血行を促進して体を内側から温めてくれるスパイスです。
香り成分の「桂皮アルデヒド」には、血管をやわらかく保つ働きがあり、冷え性の改善にも役立ちます。
むくみの緩和やリラックス効果もあるため、寒さによる不調が気になるときにぴったりです。
ミルクティーやチャイに加えるだけでなく、煮込み料理やお菓子にも使いやすいので、温活習慣に積極的に取り入れてみましょう。
ジンジャー(生姜)は、体を温める代表的なスパイスです。
辛味成分であるジンゲロールは加熱によってショウガオールに変化し、血流を促して体の深部をじんわり温める働きがあります。
食欲を促す作用や胃腸を整える効果も期待でき、冷えによる不調をトータルでサポートしてくれるでしょう。
料理にすりおろして加えるだけでなく、紅茶やスープにひとさじ入れるだけでも温活効果が高まります。
フェンネルは、独特の甘い香りをもつスパイスで、血流を促し体を温める効果があるとされています。
胃腸の調子を整え、消化を助ける作用もあるため、冷えによるお腹の不調が気になるときにもおすすめです。
食物繊維も豊富で便通を促す働きもあることから、腸内環境の改善をサポートするスパイスとしても注目されています。
魚や鶏肉の香りづけとして使いやすく、温かい飲み物やスープに少量加えれば、ほのかな甘い香りとともに巡りを促す一杯になるでしょう。
塩は単なる味つけのためだけでなく、体温の維持にも深く関わる存在です。
カルシウムやカリウムなどのミネラルには血管や筋肉をゆるめて血流を促す働きがあり、マグネシウムやナトリウムは逆に引き締める作用があります。
これらのバランスがとれている質の良い塩を適度に摂取することで、体調を安定させやすくなるのです。
血液の循環が整うと、体温も自然と保ちやすくなるため、煮物や味噌汁など、温かい料理で塩分をバランスよくとることを意識しましょう。
ただし、摂りすぎると血圧上昇などの健康リスクもあるため注意が必要です。
胡椒は、血行を促進して体を温めるスパイスの代表格です。
辛味成分の「ピペリン」には、消化を助ける作用や冷えによる胃腸の不調をやわらげる働きがあり、寒い季節にとり入れたい常備調味料とされています。
どんな料理にも合わせやすく、スープや炒め物、煮込み料理にひと振り加えるだけで、温活効果を高めてくれるのも魅力です。
日頃から使う調味料だからこそ、意識して選び、こまめに取り入れていくことが体温維持につながります。
花椒は中国原産のスパイスで、日本の山椒に似たしびれるような辛さが特徴です。
香り成分には血行を促進する作用があり、冷えを感じやすい方にとっては温活を支える心強いスパイスとなります。
麻婆豆腐や火鍋などに使われることが多いですが、五香粉やスパイスミックスとしても手軽に取り入れられるのも魅力です。
少量でもしっかりと風味が立ち、体がぽかぽかと温まりやすくなるため、辛味だけでなく香りでも巡りを助ける存在としても活用してみてください。
果物の多くは体を冷やすイメージがありますが、なかには血流を促したり、代謝を高めたりして体を温める働きがあるものもあります。
とくに以下の果物はビタミンやポリフェノール、食物繊維などの栄養素が血流のサポートや代謝の促進に効果を発揮し、冷え対策にも活用しやすいです。
- りんご
- ぶどう
- もも
- サクランボ
それぞれの果物がもつ詳しい温活効果や、おすすめの食べ方については、下記の関連記事をご覧ください。
冷えを感じたときは、飲み物から温かさを得るのも効果的です。
ここでは、冷え対策にも効果が期待できる、おすすめの飲み物を紹介します。
ココアは、血行を促進する「カカオポリフェノール」や「テオブロミン」が含まれており、体を芯から温める働きが期待できる飲み物です。
カフェインは少量含まれていますが、紅茶やコーヒーに比べて控えめなので、リラックスタイムにも適しています。
また、牛乳や豆乳で割って飲むことで、たんぱく質やカルシウムも同時に摂取できます。
甘さが欲しいときは砂糖を入れすぎず、メープルシロップなど自然な甘味料を活用しましょう。
ルイボスティーは、南アフリカ原産のハーブティーで、抗酸化作用のあるポリフェノール類が豊富に含まれています。
体を内側から温めるだけでなく、抗酸化作用によって冷えの原因となる血流の滞りにもアプローチ可能です。
ノンカフェインでクセも少なく、就寝前や妊娠中でも安心して飲めます。
ホットで飲むと体がじんわり温まり、日常的な温活習慣として取り入れやすい飲み物です。
生姜紅茶は、紅茶にすりおろした生姜を加えた温活にぴったりの飲み物です。
紅茶は発酵過程で体を温める性質を持ち、生姜に含まれるショウガオールは血流を促して、冷えた体を芯から温めてくれます。
作り方は簡単で、紅茶にすりおろした生姜を加えるだけです。
好みに応じてハチミツやレモンをプラスすれば、風味も楽しめる温活レシピになるでしょう。
朝の目覚めや、寒い日のティータイムに取り入れるのもおすすめです。
甘酒は「飲む点滴」とも呼ばれるほど栄養価の高い発酵飲料で、温活に役立つ飲み物として注目されています。
ビタミンB群やアミノ酸、オリゴ糖などが豊富に含まれており、血行を促進して体温を維持しやすくするのが特徴です。
とくに米麹由来のノンアルコール甘酒は、小さなお子様や妊娠中の方でも安心して飲めるのも魅力といえます。
腸内環境を整える作用もあるため、冷えと腸の不調が気になる方には日常的に取り入れたい一杯です。
白湯は、水を一度沸騰させて冷ましただけのシンプルな飲み物ですが、体を内側からじんわり温める効果があります。
朝にゆっくり飲むことで内臓の温度が上がり、血流や代謝が促進されやすくなります。
胃腸の働きも整いやすくなるため、便通の改善にも効果的です。
カフェインや糖分を含まないため、就寝前や空腹時の水分補給にも向いています。
体への負担が少ないので、毎日の温活習慣として取り入れてみましょう。
プーアール茶は、発酵度の高い「後発酵茶」で、体を内側から温める作用があるお茶です。
発酵の過程で生まれる酵素やポリフェノールには、血行促進や代謝アップの効果が期待できます。
カフェインが少なめで、まろやかな味わいのため、就寝前やリラックスタイムにも取り入れやすいのが魅力です。
食事にも合わせやすく、体を冷やしたくない方や冷え性が気になる方にとって、日常的に飲みやすい温活ドリンクといえます。
体温を上げるには食べ物だけでなく、日々の生活習慣を見直すことも大切です。
ここでは、食事以外で体温を高める温活方法で意識したいポイントをご紹介します。
体温を上げるには、筋肉量を増やして基礎代謝を高めることが欠かせません。
とくに下半身の筋肉は全身の中でも大きな割合を占めており、ふくらはぎや太ももを動かすことで血流が改善しやすくなります。
ウォーキングやストレッチ、椅子に座ったままできるスクワットなど、無理なく続けられる運動を日常に取り入れることがポイントです。
運動不足の方は、まず週に数回でも身体を動かす習慣を意識してみましょう。
体を温めたいときは、シャワーだけで済ませず湯船につかる習慣を持つことが大切です。
全身をお湯で包み込むことで血行が促進され、深部体温が上がりやすくなります。
とくに就寝の1〜2時間前に入浴することで、体温がゆるやかに下がり、質の良い睡眠にもつながるのです。
お湯の温度は38〜40度程度のぬるめに設定しましょう。
入浴剤を活用すれば保温効果も高まり、毎日の温活習慣として続けやすくなります。
自律神経は体温の調節にも関わっており、バランスが乱れると血流が悪くなり、冷えを感じやすくなります。
体のリズムを保つためには交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズに行われることが大切です。
そのためには、睡眠や食事、呼吸、心の落ち着きといった日常の過ごし方を意識しましょう。
夜はスマートフォンの使用を控え、アロマを取り入れたり、ぬるめのお風呂でリラックスしたりすることで、副交感神経が優位になりやすくなります。
こうした習慣が、冷えにくい体を育てる土台になっていくのです。
体温が低い状態が続くと、冷えだけでなく、代謝の低下や免疫力の低下にもつながりやすくなります。
そんなときこそ、毎日の食事で体を内側から温めることが大切です。
食べ物には、血流を促したり、腸内環境を整えたりといった働きをもつものがあり、冷え対策にも効果的とされています。
とくに香りや辛味のあるスパイス、発酵食品、温かい飲み物などは、手軽に取り入れやすく、続けやすいのが魅力です。
まずは食生活を見直し、できることから温活を始めてみましょう。
- 血流を促す食べ物や飲み物は体温を内側から上げられる
- スパイスや発酵食品は温活の強い味方になってくれる
- 運動や入浴など生活習慣もあわせて見直すとさらに効果的