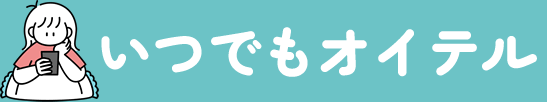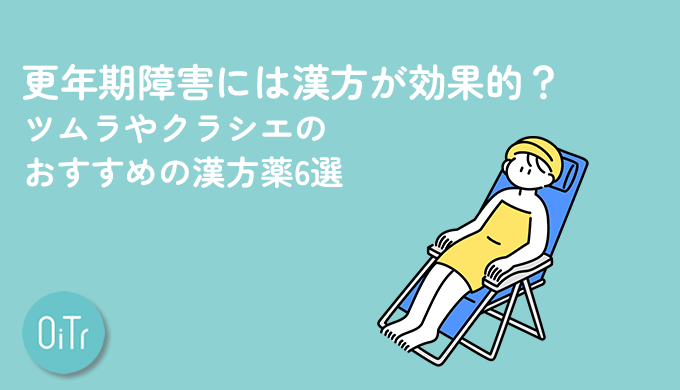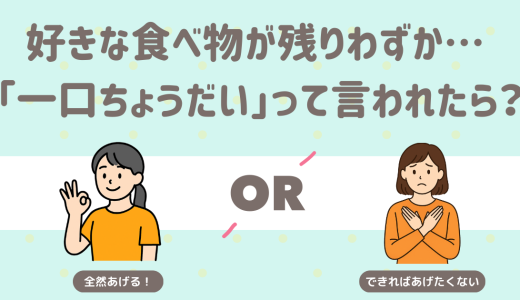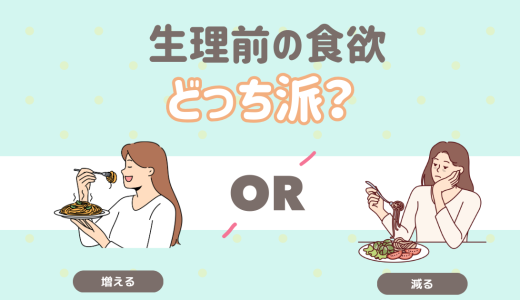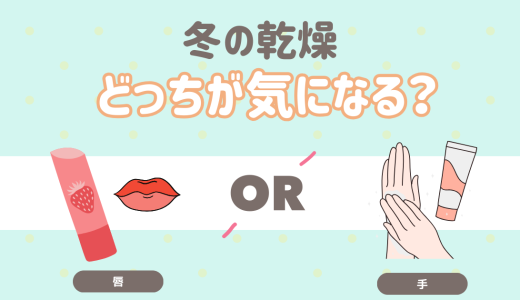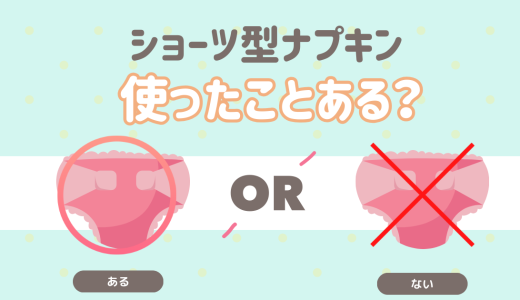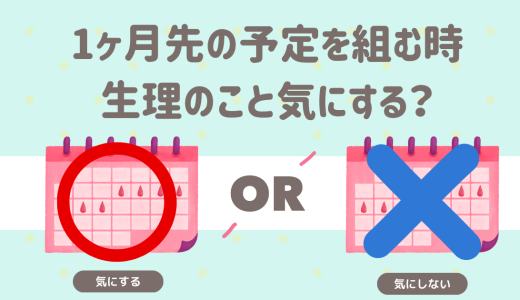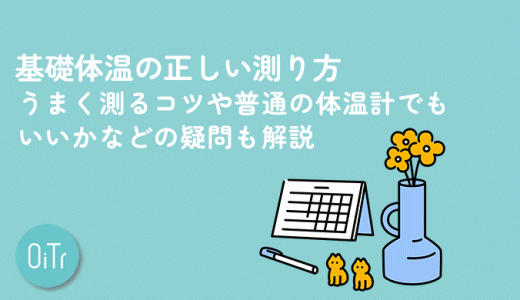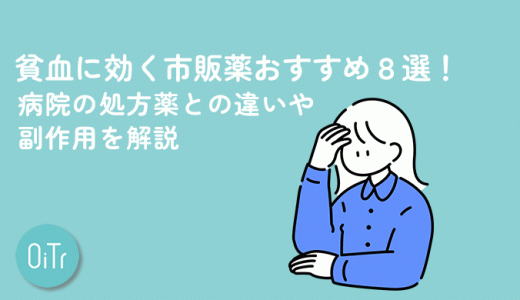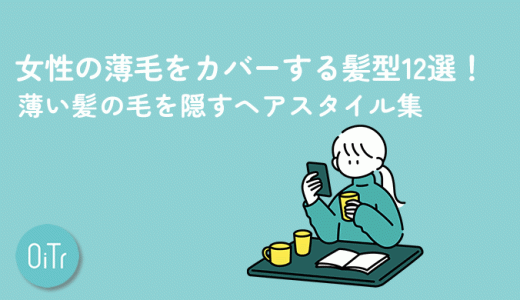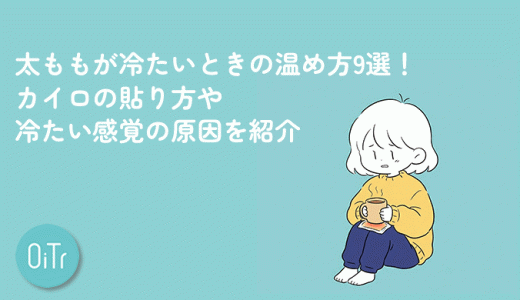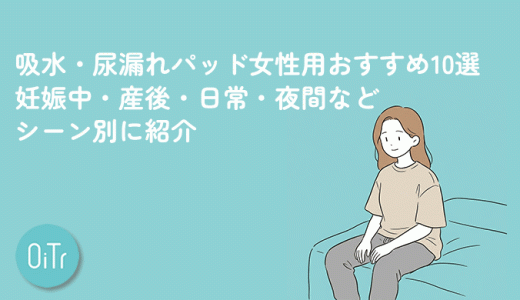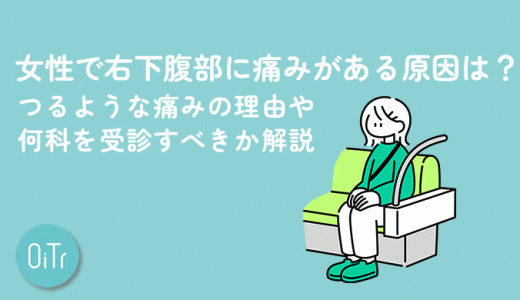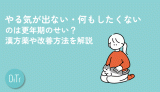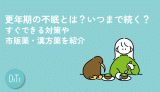更年期に入ってから体調が悪く、日常生活でつらい思いをしている人も多いです。
症状には個人差があるため、周りの人に相談しにくかったり、病院に受診するのをためらったりすることも。
更年期障害の症状を和らげるには、漢方が効果的なケースも多いです。
この記事では、更年期障害に漢方が効く理由や、おすすめの漢方薬を紹介します。
「病院を受診せずに市販のもので対処するのはよいのか?」という疑問や、服用を継続するべき期間についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
\アンケート実施中/
更年期障害とは、更年期のホルモンバランスの乱れが原因で起こる症状のこと。
更年期障害に漢方薬が効果を発揮するのは、漢方医学における「気(き)・血(けつ)・水(すい)」のバランスを整えるからです。
身体の構成要素である気血水のバランスが崩れると、さまざまな不調が現れます。
更年期は、女性の一生のなかで、気血水のバランスが最も崩れやすい時期です。
更年期障害の症状は、年齢を重ねるとともに変化するといわれていますが、これは気、血、水の順番でバランスが崩れるためと考えられています。
ここからは、気血水の特徴や役割、バランスが崩れた時に起こる症状をみていきましょう。
「気」とは生きるために必要なエネルギーで、自律神経機能に関わっている要素です。
気が足りない状態を「気虚(ききょ)」、気の流れが滞っている状態を「気逆(きぎゃく)」と呼びます。
気のバランスが崩れることで現れる更年期症状は、以下のとおりです。
- 疲労感
- 息切れ
- 冷え
- 頻尿
- 不安感
- イライラ
- ほてり
- のぼせ
- 急な発汗(ホットフラッシュ)
- 不眠
女性の場合、加齢にともなって起こる「腎虚(じんきょ)」が原因で、気逆が起こりやすいです。
「腎」は、成長・発育・生殖などに関わる泌尿器・生殖器・腎臓などの機能で、腎気が衰えた状態を腎虚と呼びます。
「血」は全身に栄養を運んで、身体を潤す働きがある要素です。
血が十分に巡っていれば、精神状態も安定するでしょう。
血が不足した状態を「血虚(けっきょ)」、血の流れが滞っている状態を「瘀血(おけつ)」と呼びます。
血の異常によって起こる更年期症状は、以下のとおりです。
- 動悸
- 息切れ
- 手足の冷え
- 頭痛
- 月経異常
「水」は唾液や汗、リンパ液などの水分で、肌や関節などに潤いを与える要素です。
水が足りない状態を「陰虚(いんきょ)」、水の流れが悪い状態を「痰湿(たんしつ)」と呼びます。
水に異常が生じている時の更年期症状は、以下のとおりです。
- 吐き気
- めまい
- 耳鳴り
漢方によってバランスがとれれば、不快な症状の改善が期待できます。
更年期障害には、症状や体質に合わせてさまざまな漢方薬が使用されます。
「更年期障害の漢方は、ツムラ23や25がおすすめ」などという口コミを目にしたことがある人もいるかもしれませんね。
ここからは、ツムラやクラシエで販売されている、更年期障害におすすめの漢方薬を紹介します。
加味逍遙散は、上昇した気を全身に巡らせるとともに、たまった熱を冷やす効果が期待できます。
さらに、血を補うことで気血水のバランスを整えてくれる漢方薬です。
ホットフラッシュやイライラ、不安感、不眠などの精神症状など、幅広い更年期症状に対応できます。
桂枝茯苓丸は、血の滞りを改善することで、のぼせや下半身の冷えを改善する効果があります。
体力が比較的あり、頭痛や肩こり、発汗などがある人にもおすすめです。
ツムラでは25番に当てはまる漢方薬で、クラシエでも購入できますよ。
あまり体力がなく、身体の冷えや疲労を感じやすい人は、当帰芍薬散がおすすめです。
全身に栄養を巡らせたり血行をよくしたりすると同時に、余分な水分を身体から取り除く効果が期待できます。
頭痛や肩こり、めまいなどの症状がある人が服用するとよいでしょう。
ツムラ23番に当てはまり、クラシエでも購入できます。
抑肝散加陳皮半夏は、自律神経系の調節をおこないつつ、身体に血を補って、気血を巡らせる漢方薬です。
イライラが強くて、周りの人に当たってしまう場合におすすめ。
市販では、クラシエのみ購入可能です。
柴胡加竜骨牡蛎湯は、体力が比較的あり、不安感や動悸、頭痛、不眠などに悩まされている人におすすめの漢方薬です。
気のバランスを整える生薬が配合されています。
知柏地黄丸は、腎の機能を補うことで、ホットフラッシュの症状の改善が期待できる漢方薬です。
排尿困難や頻尿などがある人にもおすすめします。
ツムラや医療用の漢方には、知柏地黄丸に対応する漢方薬はありません。
更年期障害に効果を発揮する漢方薬のなかには、ドラッグストアや薬局で処方箋なしで購入できるものも多いため、自己判断で服用し始める人も少なくありません。
更年期に悩む女性は日々忙しいため、手軽な市販薬の服用を検討したいものですよね。
漢方を飲み始めた後、いつまで服用を続けるかも迷うでしょう。
ここからは、更年期障害で漢方を服用したい場合に病院を受診すべきかや、服用を継続する期間について解説します。
更年期障害で漢方を服用する時は、婦人科や漢方内科を受診して医師に処方してもらうのをおすすめします。
なぜなら漢方は、服用する人の体質や症状で適切な処方が異なるためです。
自己判断で選んだ漢方で効果を感じられなかったり、更年期障害の症状が悪化してしまったりすることも。
婦人科を受診していれば、漢方療法で効果がみられなくても、ホルモン補充療法や向精神薬などのほかの治療に切り替えやすいのもメリットです。
漢方は一定期間の服用が必要で、数ヶ月〜半年にかけて服用を続けるケースが多いです。
多くの漢方は、飲み始めてから効果が実感できるまで1ヶ月程度かかることも多いため、すぐに症状が改善しなくても、毎日継続しましょう。
漢方には副作用がないと考える人も多いですが、体質によっては以下に示す副作用が現れる可能性があります。
- 吐き気
- 湿疹
- 倦怠感
- 食欲不振
- かゆみ
- むくみ
- 下痢
漢方治療中に体調の異変を感じたら、すぐに病院を受診してくださいね。
更年期障害は、身体の構成要素である気血水のバランスが崩れることで起こるといわれています。
これらのバランスをとる漢方には、更年期障害のさまざまな症状の改善が期待できるでしょう。
多くの漢方が更年期障害に使われるため、どれを服用したらいいか悩む人も少なくありません。
市販で手軽に購入できるものも多いですが、病院を受診して体質や症状に合った漢方を、医師に処方してもらうことをおすすめします。
- 身体の構成要素である気血水のバランスが崩れると、さまざまな不調が現れる
- 更年期は気血水のバランスが最も崩れやすい時期で、これらを整える漢方が効果的
- 更年期障害には、症状や体質に合わせてさまざまな漢方薬が選択される
- 漢方は服用する人の体質や症状で適切な処方が異なるため、医師に選んでもらうのがおすすめ
- 更年期障害では、数ヶ月~半年にかけて漢方の服用を続けるケースが多い