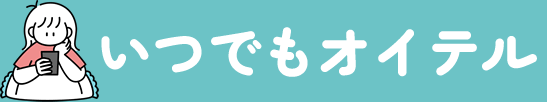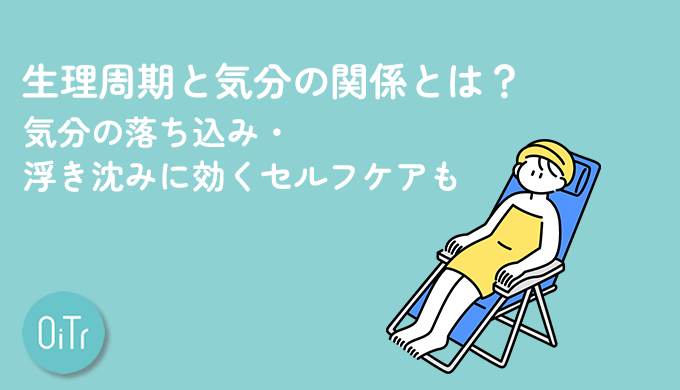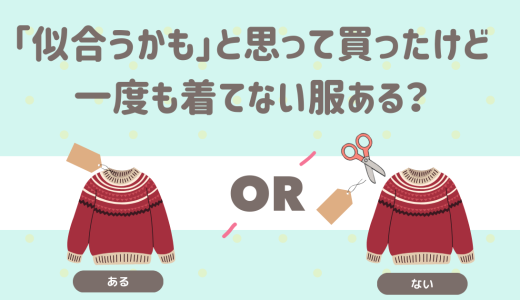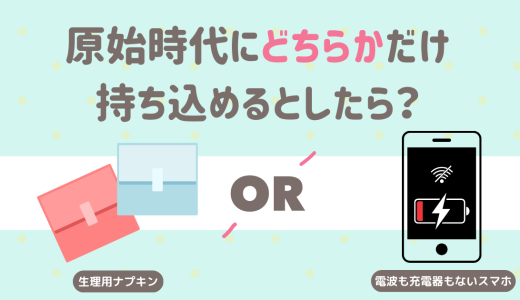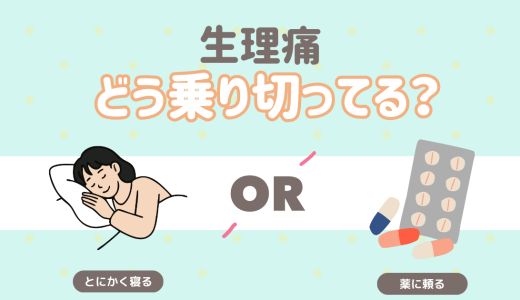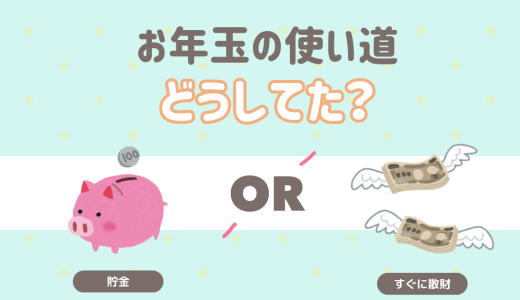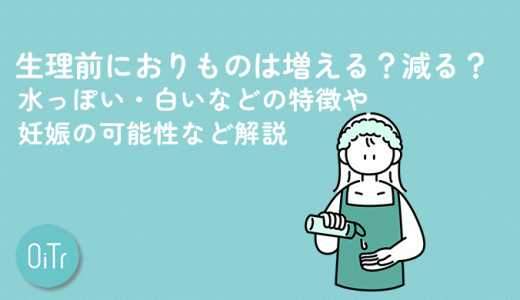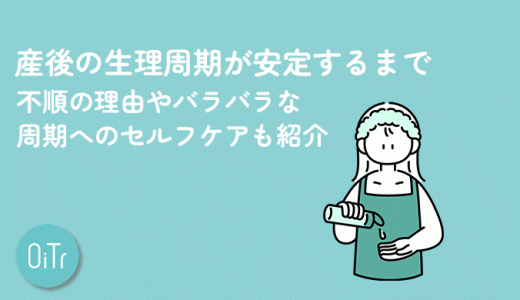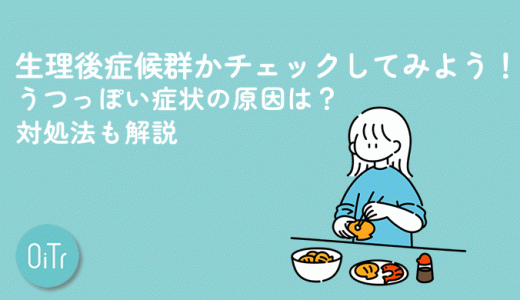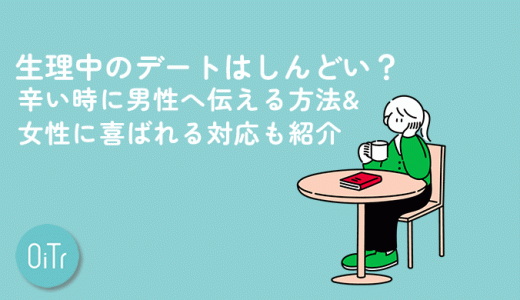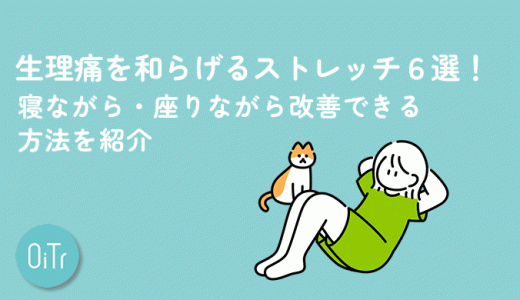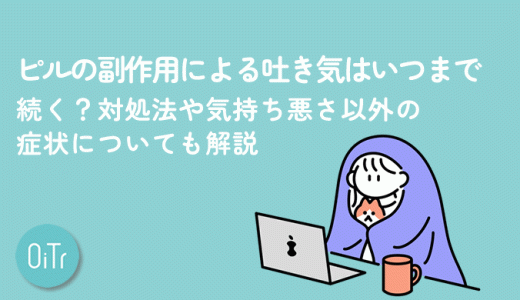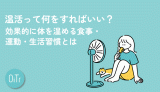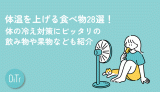生理前になるとイライラしたり、急に気分が落ち込んだりして、モヤモヤすることがあるかもしれません。
「生理が終わってからしばらくは調子がいいのに、生理が近づくにつれてつらい」と感じる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、生理周期と気分との関係や生理周期ごとの気分の特徴、気分の波にやさしく寄り添うセルフケアなど解説します。
受診の目安も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
\アンケート実施中/
結論、生理周期と気分が関係するのは、女性ホルモンの分泌の変化によって自律神経が影響を受けるからです。
女性の気分や体調は、卵巣から分泌される「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」という女性ホルモンに大きく影響を受けています。
これらは月経周期にあわせて分泌量が変動するため、自律神経のバランスも崩れやすくなるのです。
ホルモン分泌は、脳の視床下部がコントロールしています。
この視床下部は自律神経の働きも調整しているため、 ホルモンバランスが乱れると、自律神経にも影響が出て、心身の不調につながることがあるのです。
生理周期は「卵胞期」「排卵期」「黄体期」「月経期」の4つに分けられ、それぞれの時期に分泌される女性ホルモンの量が大きく変動します。
ホルモン分泌の変化にともなって、自律神経や脳の働きにも影響がおよび、気分の浮き沈みや体調の変化が起きやすくなるのです。
ここでは、各時期にみられる気分や身体の特徴を紹介します。
卵胞期は、生理が終わった直後から排卵までの期間を指します。
この時期は、卵胞ホルモンの分泌が徐々に増えていくため、心身ともに安定しやすいのが特徴です。
肌や髪の調子が整ったり、気分が前向きになったりと、身体全体のコンディションが回復してくる人も多いでしょう。
気分や感情に影響を与える「セロトニン」という神経伝達物質の分泌も高まりやすく、集中力ややる気が出やすい時期です。
運動や新しいことへのチャレンジにも前向きになれるでしょう。
排卵期は、成熟した卵子が排出されるタイミングです。
卵胞ホルモンの分泌がピークを迎えたあと急激に減少するため、ホルモンバランスが大きく変動します。
このホルモンの急な変化が、自律神経に影響を与えやすく、気分が不安定になったり、イライラや倦怠感を感じることも。
人によっては排卵痛や腰の重さ、軽い吐き気を感じることがあるでしょう。
黄体期は、排卵後から次の生理が始まるまでの期間で、黄体ホルモンの分泌が活発になる時期です。
黄体ホルモンには、妊娠の準備のために子宮内膜を整えたり、体温を上げたりする働きがあります。
卵胞期・排卵期からのホルモンバランスの変化で、交感神経が強く働きやすく、ストレスを感じやすくなるのです。
イライラや不安感、落ち込みなどの精神的な不調や、眠気やむくみ、胸の張りなどの身体症状がみられることも。
月経期は、子宮内膜が剥がれて経血として排出される期間です。
プロゲステロンの分泌が減少し、ホルモンバランスが大きく変化することで、自律神経にも影響が出やすくなります。
生理痛や、経血量の多さによる貧血傾向もあいまって、体調がすぐれず気分が落ち込みやすい時期。
イライラや無気力、眠気、だるさなどの症状が現れやすく、「とにかく何もしたくない」と感じることもあるでしょう。
生理の終わりに近づくと、卵胞ホルモンの分泌が再び始まり、徐々に気分や体調が回復していく人も多いです。
生理周期にともなう気分の波は、女性ホルモンの変動や自律神経の乱れが影響しています。
イライラや落ち込みがあっても、身体の仕組みによる自然な反応です。
気分のゆらぎと上手に付き合うには、日常生活の中でできるセルフケアをおすすめします。
ここでは、自分のリズムを整えるために取り入れたい習慣をみていきましょう。
気分を安定させるには、規則正しい生活を意識することが大切です。
なぜなら自律神経は睡眠や食事、活動といった生活リズムの影響を受けやすいため。
生活リズムが乱れると、心身のバランスも崩れやすくなります。
- 毎朝同じ時間に起きて朝日を浴びる
- 決まった時間に食事を摂る
- 夜はスマホを控えて早めに眠る
基本的な生活習慣の積み重ねが、自律神経の安定につながりますよ。
気分の波が大きくなっているときほど、意識的にリラックスできる時間を確保しましょう。
- 深く息を吐く
- ぬるめのお風呂に浸かる
- お気に入りのアロマを楽しむ
こうした工夫によって、自律神経の1つである「副交感神経」が優位になり、気分が落ち着きやすくなります。
さらに、睡眠の質を高める工夫も大切です。
- 寝る1時間前にはスマホやPCの使用を控える
- 間接照明を使う
- リラックスできる音楽を聴く
- 寝酒や喫煙、カフェインの摂取を控える
質のよい睡眠も、ホルモンバランスと自律神経の安定に直結します。
心身を労わる時間を意識的に持ちましょう。
気分が落ち込みやすいときや、生理前のイライラがつらいときほど、軽く体を動かすのがおすすめです。
ストレッチやヨガ、散歩など、無理なくできる運動を取り入れましょう。
筋肉の緊張がほぐれ、血流がよくなることで、自律神経のバランスも整いやすくなります。
運動にはストレスをやわらげたり、セロトニンの分泌を促したりする働きもありますよ。
気分の不安定さをやわらげるためには、毎日の食事も大切なセルフケアになります。
バランスのとれた食事は、ホルモンの分泌を整え、心身の土台を安定させてくれるでしょう。
イライラや不安を感じやすいときは、糖質に偏らず、たんぱく質や脂質、ビタミン、ミネラルをバランスよく取り入れるように意識することが大切です。
睡眠を促す「メラトニン」やセロトニンの分泌に欠かせない、鉄分の摂取も心がけましょう。
生理周期による気分の波で生活に支障が出ている場合、病気が隠れている可能性があるため、婦人科の受診を検討するとよいでしょう。
ここからは、考えられる病気や治療法について解説します。
生理前に強いイライラや不安感、落ち込みなどの症状が続く場合、PMS(月経前症候群)や、精神症状が強いPMDD(月経前不快気分障害)の可能性があります。
PMSは、ホルモンバランスの変動によって起こる心身の不調のこと。
PMDDは、抑うつ気分や不安、緊張、情緒不安定、怒り・イライラなどの精神症状が、日常生活に大きな影響を与えるほど強く出るのが特徴です。
生理痛が重くイライラして、生活や仕事に支障をきたす場合「月経困難症」の可能性も考えられます。
月経困難症とは、下腹部痛や腰痛、イライラ、憂うつなどの症状によって日常生活に支障が出る状態のこと。
原因となる明確な病気がない「機能性月経困難症」と、子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が関係する「器質性月経困難症」の2種類があります。
市販薬では十分に対処できないケースもあるため、月経痛や気分のつらさが慢性的に続く時は、早めに婦人科を受診して原因を明らかにすることが大切です。
PMSやPMDD、月経困難症の治療は、人によってさまざまです。
たとえば、ホルモンバランスを安定させる「低用量ピル」や「黄体ホルモン製剤」が用いられることがあります。
精神症状が強い場合は、抗不安薬や抗うつ薬を服用することも。
漢方薬やカウンセリングなどもあるため、医師と相談して自分に合ったケア方法を探しましょう。
ホルモンバランスがゆらぐのは自然な生理現象であり、それにともなって感情が変動するのも当たり前のこと。
自分の周期や傾向を知り、生活習慣やセルフケアでできる範囲から整えていくことが、気分の安定にもつながります。
症状がつらいときはひとりで抱えこまず、婦人科で相談することも大切な一歩です。
- 生理周期で気分に波があるのは、ホルモンバランスと自律神経の変化が関係している
- 各周期(卵胞期・排卵期・黄体期・月経期)によって、気分や体調に特徴がある
- セルフケア(生活リズム・睡眠・運動・食事)で気分の波をやわらげられる
- PMSやPMDD、月経困難症が隠れている場合もあるため注意が必要
- つらさを感じたら、早めに婦人科で相談し、自分に合った対策を見つけよう