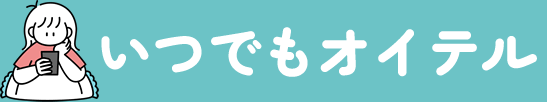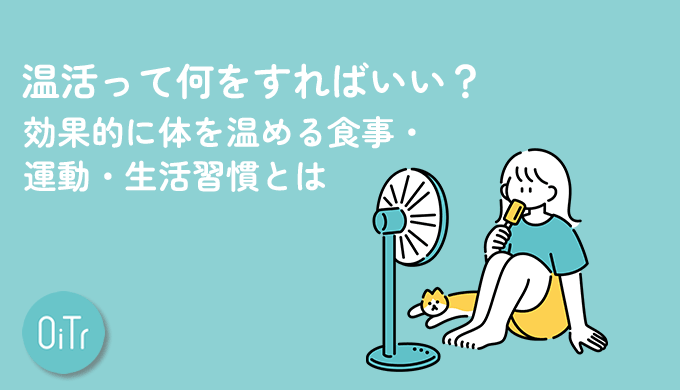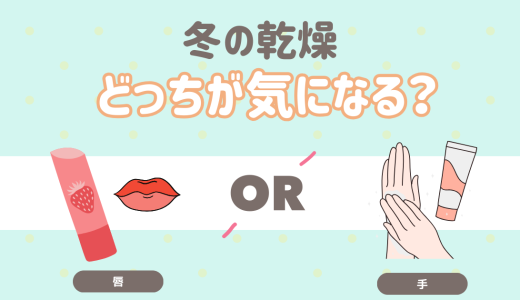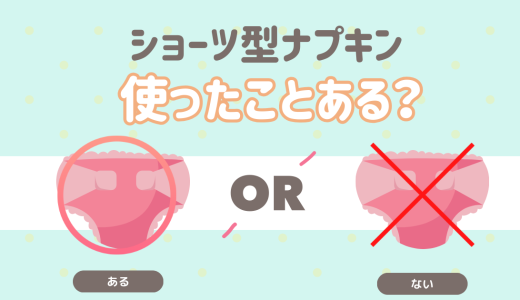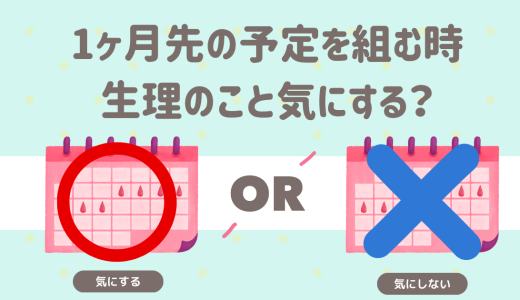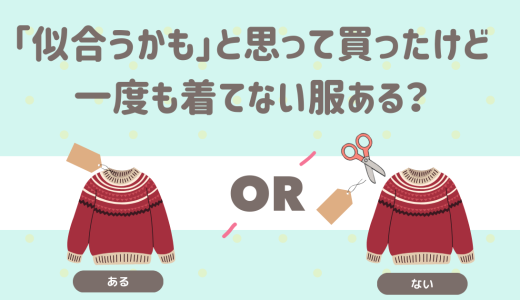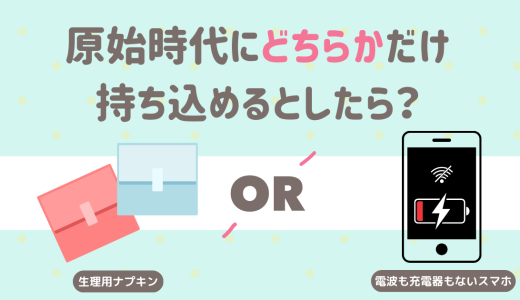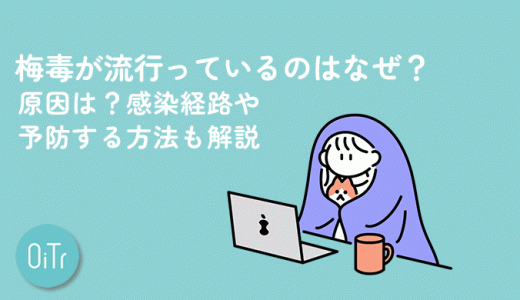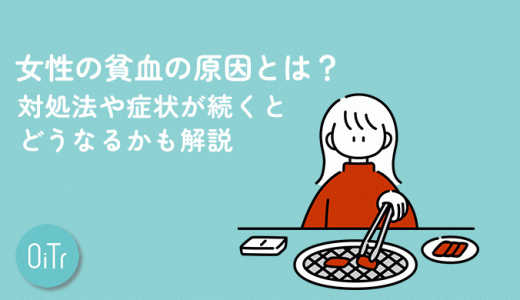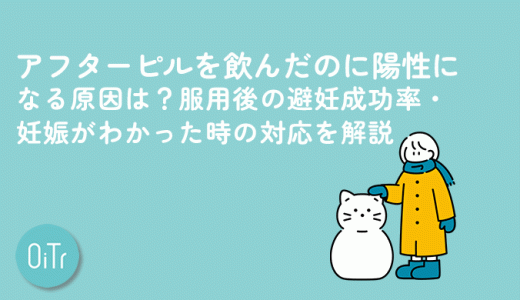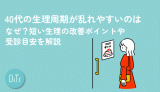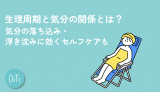「温活がいいって聞くけど、実際に何をすればいいのか分からない」と悩む人も多いのではないでしょうか。
冷えを放っておくと、代謝の低下や不調の原因にもつながるため注意が必要です。
この記事では、食事・運動・生活習慣の3つの視点から、具体的な温活方法を解説します。
日々の暮らしに無理なく取り入れて、体の内側からじんわりと温まる感覚を手に入れましょう。
\アンケート実施中/
温活とは、体を内側から温めて基礎体温を上げ、冷えによる不調を改善しようとする習慣のことです。
特に女性は筋肉量が少なく、血流が滞りやすい傾向があるため、冷え性に悩む方が多いと言われています。
また、運動不足や冷たい飲み物、ストレスによる自律神経の乱れも、体温を保つ力を弱める原因のひとつです。
そこで、温活を通じて血行が良くなれば、基礎代謝が高まり、むくみや生理痛の軽減、睡眠の質向上、肌の調子など、心と体のさまざまな面でうれしい変化が期待できます。
温活を続けるうえでは、体を内側から温めて血流や代謝をサポートする食材や食べ方を意識することが、大切なポイントのひとつです。
ここでは、温活に役立つ食事のコツをご紹介します。
温活を意識する際は、栄養バランスの整った食事を基本にすることが大切です。
とくに、筋肉の材料となるタンパク質や、腸内環境を整える発酵食品、体を内側から温める根菜類などを意識して摂るようにしましょう。
肉や魚、大豆製品に加えて、納豆やみそを取り入れることで、冷えにくい体づくりをサポートできます。
また、薬膳の考え方では、しょうがやにんにく、かぼちゃ、シナモンなどの「温性」や「熱性」の食材は、冷えが気になる方におすすめです。
温活を意識するなら、主食であるごはんやパンもしっかり食べることが大切です。
炭水化物は体を動かすエネルギー源であり、体内で熱を生み出すためにも欠かせません。
とくに朝食を抜いてしまうと体温が上がりにくくなり、一日中冷えを感じやすくなってしまいます。
ごはんに味噌汁や煮物を添えたり、全粒粉のパンと温かいスープを組み合わせたりすることで、体を内側から温める食事を意識してください。
また、糖質を控えすぎるとエネルギー不足を招くおそれがあるため、適量を守りながら、温かい調理法や食材との組み合わせを意識して取り入れるとよいでしょう。
唐辛子やしょうがは、温活を代表する食材として知られています。
唐辛子に含まれるカプサイシンや、しょうがに含まれるショウガオールには、血流を促して体を内側から温める働きがあるのです。
とくにしょうがは、加熱することで成分が変化し、より高い温活効果が期待できます。
市販のチューブや粉末でも活用できますが、生のしょうがをすりおろして使うと、より効果的です。
ただし、唐辛子は胃腸への刺激が強いため、使いすぎには注意し、適度な量で毎日の食事に上手に取り入れてみてください。
温活を意識するなら、冷たい飲み物や体を冷やす食材の摂り方にも注意が必要です。
冷たい水や氷入りの飲み物を頻繁にとると、内臓が冷えて血流が悪くなり、体温の低下につながるおそれがあります。
また、トマトやきゅうり、スイカなど夏が旬の食材は「涼性」や「寒性」に分類され、冷えやすい体質の方には不向きでしょう。
これらを食べる場合は、加熱調理をしたり、温性の食材と組み合わせたりする工夫が必要です。
さらに、カフェインの過剰摂取も自律神経の乱れを引き起こしやすいため、コーヒーや緑茶は量を調整しながら楽しむことをおすすめします。
温活を効果的に行うには、筋肉を動かして熱を生み出すことも大切です。
ここでは、日常に取り入れやすい温活向けの運動を紹介します。
ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、全身の血流を支える重要な部位です。
とくに下半身の血液を心臓に押し戻すポンプの役割があるため、筋力が落ちると血行が悪くなり、足先から全身に冷えが広がりやすくなります。
そこで、次の動きを取り入れ、毎日少しずつでもふくらはぎを鍛えましょう。
- 姿勢を整える
- ゆっくりかかとを上げる
- つま先立ちでキープ(3〜5秒)
- ゆっくりかかとを下ろす
- 10回×3セット繰り返す
日常の動きの延長でできるエクササイズですが、継続することで血流が改善され、体の内側からじんわりと温まりやすくなります。
スクワットは、太ももやお尻など大きな筋肉を効率よく鍛えられる運動で、温活にも効果的です。
なかでも椅子を使ったスクワットは、運動が苦手な方でも始めやすい方法になります。
椅子の背もたれに手を添えたまま、背筋を伸ばしてゆっくり腰を落とし、ひざが90度になる位置で止めてから元に戻してください。
太ももに負荷がかかっていることを意識しながら行うのがポイントです。
朝・昼・晩に10回ずつ取り入れるだけでも、下半身の筋力アップに役立ち、日々の温活習慣として効果が期待できます。
ホットヨガは、室温38〜40℃・湿度55〜65%ほどの高温多湿な環境で行うヨガで、体を芯から温めながら筋肉を伸ばせるのが特徴です。
通常のヨガよりも発汗量が多く、血流や代謝の促進、デトックス効果が期待できます。
また、深い呼吸とポーズを連動させることで、自律神経を整える効果もあり、冷えの根本改善を目指したい方におすすめです。
筋肉がこわばりやすい冷え性の方でも、温かい室内で行うことで無理なく体を動かせる点も魅力といえるでしょう。
定期的に通うことで、気温や環境に左右されにくい体づくりにつながります。
体を冷やさないためには、日々の過ごし方にもひと工夫が必要です。
ここでは、冷えにくい体をつくるための生活習慣のポイントを紹介します。
朝起きた直後は、体温が低くなっているうえに、寝ている間の発汗によって水分も不足しています。
この状態で冷たい水を飲むと、内臓がさらに冷えてしまうおそれがあるため、白湯をゆっくりと飲みましょう。
白湯は胃腸を穏やかに温め、体の内側から血流を促す効果が期待できます。
また、代謝が高まりやすくなるため、体を目覚めさせる意味でもぴったりです。
飲む量の目安はコップ1杯程度で、40〜50℃くらいの飲みやすい温度に調整しましょう。
毎朝のルーティンとして取り入れることで、無理なく温活を続けやすくなります。
温活を意識するなら、朝食を抜かずにきちんと食べることが大切です。
睡眠中に低下した体温を上げるには、エネルギー源となる食事の力が欠かせません。
とくにごはんやみそ汁、卵や納豆などをバランスよく組み合わせた朝食は、体を内側から温めるのに適しています。
冷えが気になる方は、温かいスープや温性の食材を積極的に取り入れると効果的です。
忙しい朝でも、手軽に食べられる内容で構わないので、毎日の習慣として続けてみてください。
湯船にゆっくり浸かることは、温活の基本ともいえる習慣です。
シャワーだけでは体の表面しか温まらず、深部体温はなかなか上がりません。
38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かることで、血行が促されて体の芯から温まりやすくなります。
また、入浴には副交感神経を優位にする働きもあり、リラックス効果や睡眠の質の向上にも効果的です。
とくに冷えを感じやすい手足がじんわり温まってくると、全身がほぐれる感覚を得られやすくなるでしょう。
好みに応じて、温浴効果のある入浴剤を取り入れるのもおすすめです。
冷えを感じやすい部位を重点的に温めることも、効果的な温活のひとつです。
とくに首・手首・足首は、太い血管が皮膚の近くを通っているため、ここを温めることで全身がぽかぽかしやすくなります。
ネックウォーマーやレッグウォーマー、湯たんぽやカイロなど、さまざまなタイプのアイテムを活用して、外出先や就寝中でも手軽に冷え対策を取り入れましょう。
お腹や腰まわりの冷えが気になる方は、腹巻きやあたたかい下着を取り入れるのもおすすめです。
冷えを感じる方にとって、温活は冷え症を根本から見直すための大切な習慣です。
身体を内側から温める食事、代謝を高める運動、血流を整える生活習慣の3つを意識することで、無理なく冷えの改善が目指せます。
また、冷えの改善とともに自律神経が整えば、心身のコンディションも安定しやすくなるでしょう。
いきなり完璧を目指す必要はないため、できることから少しずつ取り入れ、自分の体に合った温活を見つけていきましょう。
- バランスの良い食事や下半身を中心とした適度な運動で内側から体を温めよう
- 寝起きの白湯や朝食で朝の体温を上げる習慣をつくることも大切
- 毎日の湯船習慣や温活アイテムで常に保温を意識しよう