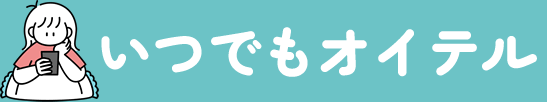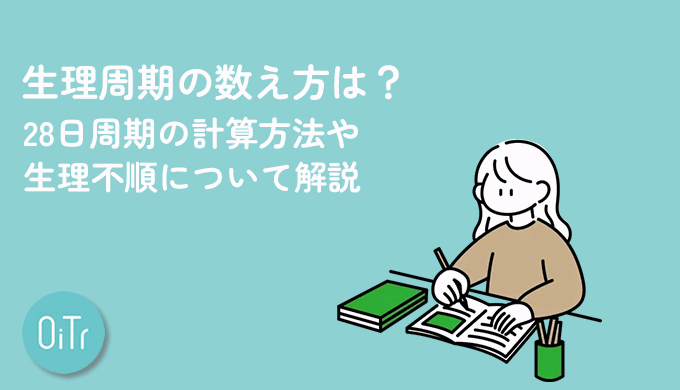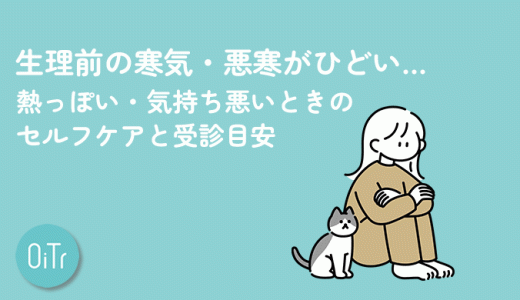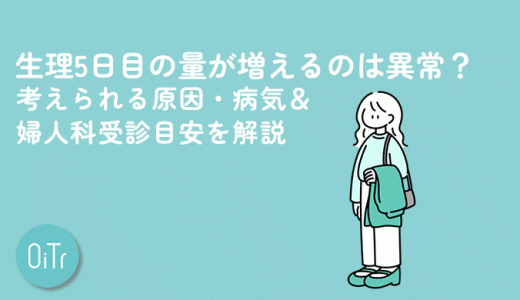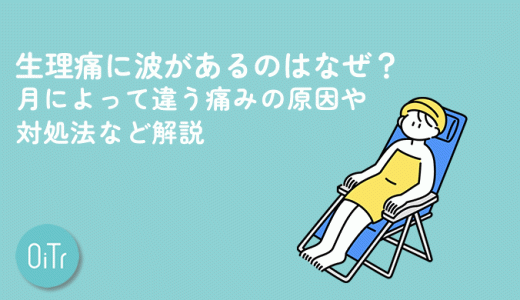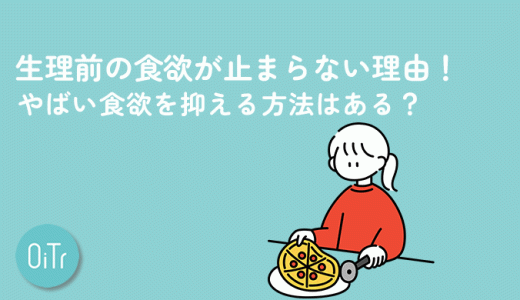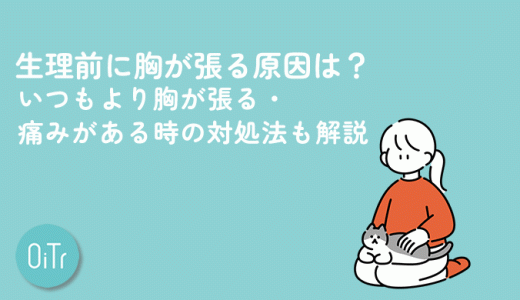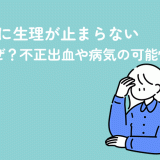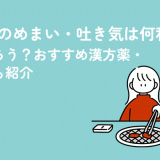生理周期がわかると、事前に生理用ナプキンの準備をできたり、旅行の予定を立てやすかったりと、さまざまなメリットがあります。
しかし、生理周期を把握したくても、いつから数えるのかわからない人も多いのではないでしょうか。
今回は、生理周期の数え方を28日周期の場合に当てはめて解説するとともに、生理不順の種類についても紹介します。
みんなの本音がわかる!
アンケート実施中
月経周期の数え方は、前の月経開始日から次の月経開始日の前日までの日数です。
たとえば、4月1日に前回の生理が来て、4月29日に次の生理が始まった場合、28日周期とカウントできます。
ただし生理周期は、ホルモンバランスやストレスなどの影響を受けて変化するため、1回だけではなく複数回のデータを取り、平均値から生理周期を調べるのがおすすめです。
基礎体温を測定したり、生理周期を自動で計算できるアプリを使ったりするのもよいでしょう。
基礎体温の正しい測り方は、以下の記事でくわしく解説しています。
\あわせて読みたい/
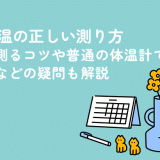 基礎体温の正しい測り方丨うまく測るコツや普通の体温計でもいいかなどの疑問も解説
基礎体温の正しい測り方丨うまく測るコツや普通の体温計でもいいかなどの疑問も解説
生理周期は、4つの期間に分けられます。
1回の生理周期の中で、女性ホルモンの分泌が大きく変わるため、さまざまな心身の変化を感じるでしょう。
ここからは、生理周期を構成する4つの時期について解説します。
卵胞期とは、脳の指令によって、女性ホルモンの1つである卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌量が増えている時期のことです。
卵巣で卵子となる原始卵胞が生育を始めるとともに、子宮内膜が厚くなっていきます。
基礎体温を測定すると低温を示すのも、卵胞期の特徴の1つ。
副交感神経の働きが活発なため、気分も安定しやすい時期です。
新陳代謝が活発になり、血行がよくなるため、ダイエットにも最適。
肌の潤いや髪のツヤを感じられるでしょう。
卵胞が十分に育つと、脳から黄体形成ホルモンが大量に分泌され、その24時間〜36時間以内に排卵が起こる排卵期を迎えます。
基礎体温で見ると、少し低下したあとに急上昇して高温期に入る時期です。
排卵日やその直後は、最も妊娠しやすい時期。
妊活中などで排卵日を知りたい場合は、排卵検査薬を使うのがおすすめです。
検査開始日は、生理周期や生理開始日から計算できます。
生理周期が規則的なら、前回の生理開始日に生理周期の日数を足して17を引くと、排卵検査薬を使用し始める日に当てはまりますよ。
例えば、生理開始日が3月26日で生理周期が28日であれば、以下のように計算します。
| 検査薬の使用日: 26 + 28 – 17 = 37 ⇛ 3月37日 = 4月6日 |
排卵が終わってから生理が始まるまでの期間を、黄体期と呼びます。
排卵が終わった卵胞が黄体と呼ばれる状態に変わり、女性ホルモンの1つである黄体ホルモンが主に分泌される時期です。
子宮内膜は、卵子が着床しやすいように変化します。
黄体ホルモンが優位となる黄体期は、次のような心身の変化がみられるでしょう。
- 基礎体温が上昇し、いつもより暑い・ほてると感じる
- おりものの量が減り、粘度が高く白っぽく変わる
- 胸が張る
- むくみやすくなる
- 体重が増える
- 肌が荒れやすくなる
- イライラや気分の落ち込みを感じる
生理の3日〜10日前から、PMS(月経前症候群)に悩まされる人も。
月経期は、受精卵の着床が起こらなかった場合、子宮内膜が剥がれ落ち、月経血として体外に排出される時期です。
卵胞ホルモンや黄体ホルモンは急激に減少するとともに、基礎体温は低下して低温期に入ります。
生理期間は生理痛を感じたり、肌荒れを起こしたりする人が多いでしょう。
生理予定日を1週間以上過ぎても生理が来ない場合や、基礎体温を測定していて高温期が続く場合は、妊娠の可能性があります。
妊娠検査薬を使用して陽性だった場合は、できるだけ早く婦人科クリニックを受診しましょう。
自身の生理周期を知ることで、さまざまなメリットが得られます。
自身の生理周期を知り、日々の生活に活かしてくださいね。
生理周期がわかれば、ホルモンバランスの変化がわかります。
排卵日や生理前の体調不良、生理開始日を前もって知れるため、旅行などの予定が立てやすくなったり、妊活中のサポートになったりするでしょう。
大事な予定と生理が重なる場合、低用量ピルや中用量ピルで生理日を移動することも可能です。
生理周期がわかっていれば、生理の遅れから妊娠の可能性に気づきやすくなります。
早い段階から婦人科を受診したり、パートナーと話したりすることが可能です。
妊娠検査薬を使用するタイミングが早かったり遅かったりすると、妊娠の有無を正確に測定できません。
日頃から生理周期を把握することが、妊娠の早期発見に役に立つでしょう。
生理周期は、子宮頸がんや子宮筋腫、卵巣の異常など、さまざまな原因で乱れるものです。
生理周期を把握しておくことで、病気の早期発見・治療につながります。
ストレスによっても生理不順になるため、生活習慣の見直しにも効果的です。
正常な生理周期は25日〜38日とされています。
24日以内に生理が来たり、39日以上生理が止まっていたりする場合は、できるだけ早く婦人科を受診しましょう。
ここからは、生理不順の種類や治療法を解説します。
生理周期が39日以上3ヶ月の場合、稀発月経に分類されます。
体質によって排卵に時間がかかるパターンや、過度なダイエットやストレスで稀発月経になるパターンがあるでしょう。
ホルモンバランスの乱れや卵巣機能のトラブルによって無排卵となり、稀発月経になるケースは無月経を引き起こしたり、不妊につながったりするため、治療が必要です。
生理周期から24日以内の場合は、頻発月経と呼ばれる状態です。
排卵がある場合(排卵性)と排卵がみられない場合(無排卵性)に分けられます。
排卵がある場合は、卵胞期が短くなったり、黄体機能不全という病気が隠れていたりするでしょう。
無排卵月経は、経血量が少ないまま、出血がダラダラと長引くのが特徴です。
卵胞期の短縮による頻発月経や無排卵月経は、思春期や更年期前・閉経前の女性によくみられるため、治療の必要がないケースも多いでしょう。
しかし、黄体期の短縮による頻発月経は、不妊症や流産の原因となる可能性があるため、治療をおこなうのがおすすめです。
無月経とは、妊娠以外で生理が3ヶ月以上止まった状態をさします。
無理なダイエットや肥満、ストレスなどでホルモンバランスが崩れることで起こるケースが多いです。
ほかにも、脳下垂体の腫瘍や内科系の病気で引き起こされることもあります。
不整周期月経とは、生理周期のうち最も短い時と長い時の差が7日以上のケースをさします。
たとえば、前の月は26日周期で、次の月は40日周期などが当てはまるでしょう。
- 無理なダイエット
- 運動不足
- 睡眠不足
- 強いストレス
こうした理由から、ホルモンバランスが乱れて、生理周期が乱れることがあります。
不整周期月経でも、毎回排卵が起きていればそこまで心配はいりませんが、排卵が起きていない場合は不妊や生活習慣病、更年期のような症状に悩まされることも。
できるだけ早めに婦人科を受診しましょう。
卵胞ホルモンと黄体ホルモンを配合した低用量ピルを服用すると、生理不順が改善しやすくなります。
ホルモンバランスが一定の状態に保たれるため、生理にまつわるトラブルが起こりにくくなるでしょう。
生理不順以外にも、生理痛によって日常生活に支障が出る「月経困難症」やPMSに悩んでいる人は、婦人科で相談してピルの処方を検討してもらうとよいですよ。
生理周期の数え方は、生理開始日から次の生理の前日までの日数と、意外と簡単なものです。
ホルモンバランスやストレスの影響を考えて、複数の生理周期のデータをとり、平均値を出すとよいでしょう。
生理周期は、女性ホルモン分泌の変化によって生まれ、4つの時期に分かれます。
生理周期の把握は、自身のホルモンバランスの変化による体調不良の予測や、妊娠の可能性や病気に気づくきっかけにつながるでしょう。
生理周期が極端に短かったり、長かったりする場合は、できるだけ婦人科を受診してくださいね。
- 生理周期の数え方は、前回の生理開始日から次の生理開始日の前日を数えたもの
- 複数回データをとり、平均値を出すのがおすすめ
- 生理周期を把握することで、体調不良に気づいたり、旅行の予定を立てやすかったりといったメリットを得られる
- 生理不順の種類は、稀発月経、頻発月経、無月経、不整周期月経に分けられる
- 生理不順の治療には低用量ピルが使われることが多い