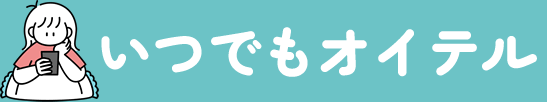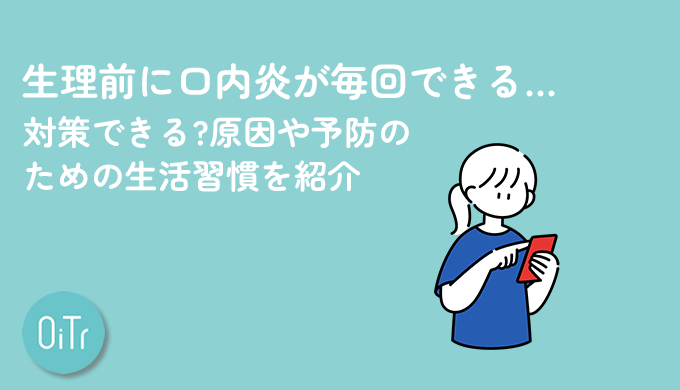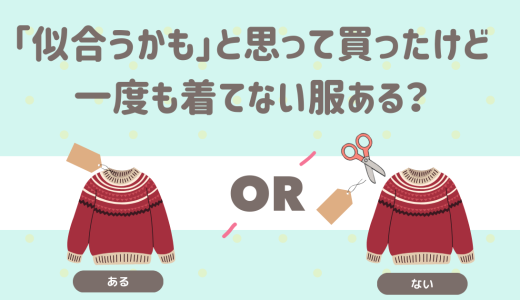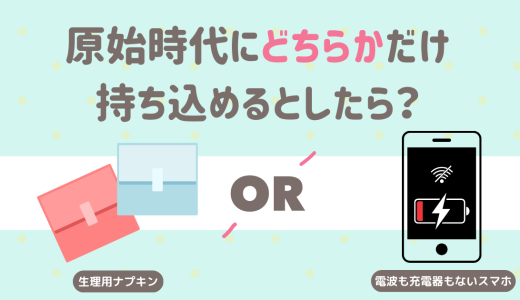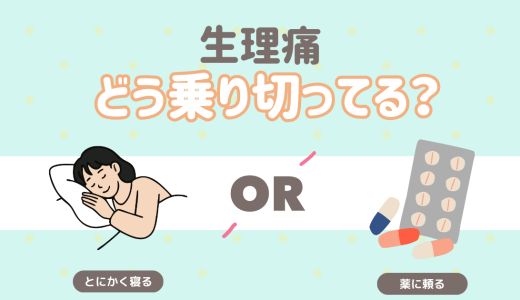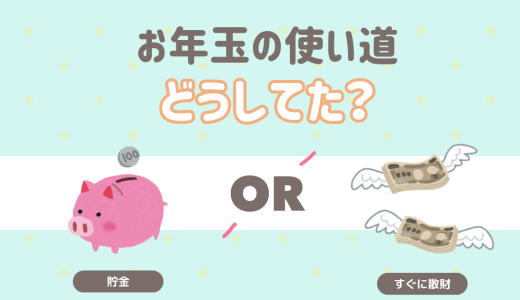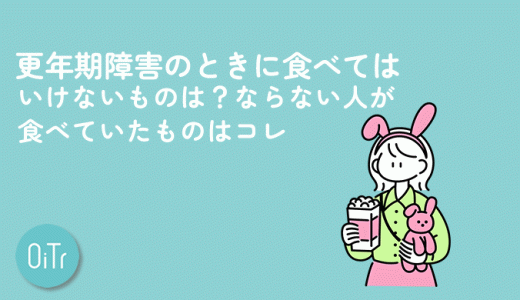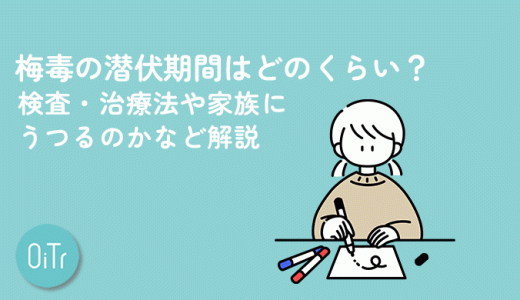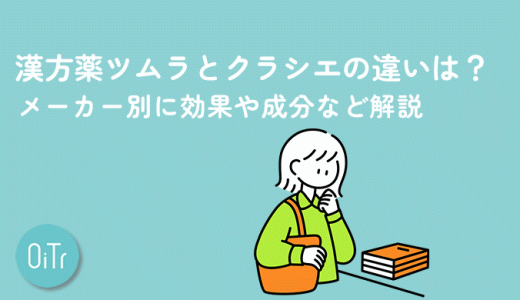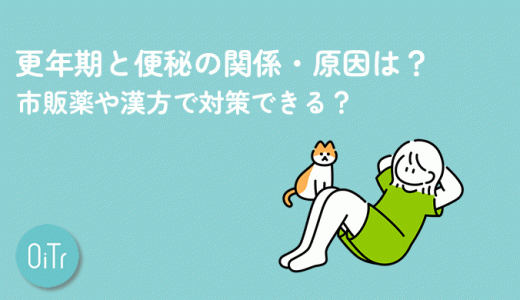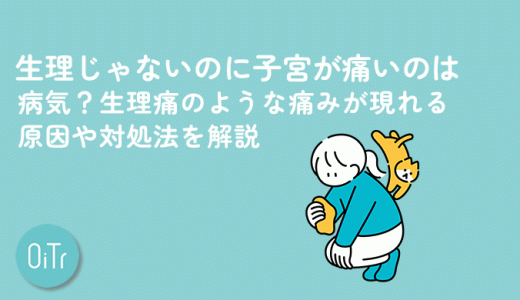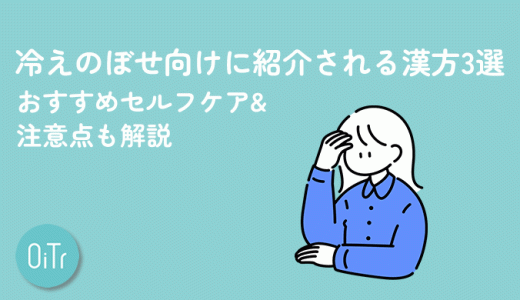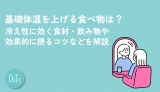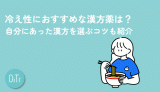「生理前になると、決まって口内炎ができてしまう……」
生理前の口内炎は、ホルモンバランスの崩れや栄養不足などが理由で起こると考えられており、適切な対策をすれば、早期の治癒と予防が期待できます。
この記事では、生理前に口内炎ができやすい理由から、できてしまった時の効果的な治し方、そして二度とくり返さないための予防法までを詳しく紹介します。
\アンケート実施中/
生理前に口内炎ができやすいとは言われているものの、メカニズムは完全に明らかになっていません。
しかし、おもにホルモンバランスの変化、自律神経の乱れ、栄養不足という3つの要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
生理前は、女性ホルモンのひとつであるプロゲステロン(黄体ホルモン)が急激に増える時期です。
このホルモンの変動は体内の免疫力に影響を与え、口の粘膜の抵抗力が弱まることで、口内炎ができやすくなると考えられています。
また、エストロゲン(卵胞ホルモン)の減少によって皮膚や粘膜が乾燥しやすくなり、口内炎といった形でトラブルを招くこともあります。
生理前は、ホルモンバランスの変化にともなって、自律神経も乱れやすくなります。
自律神経が乱れると、ストレスを感じやすく、血行も悪くなりがちです。
血流が滞ることで、口のなかの粘膜に十分な栄養や酸素が行き届きにくくなり、ダメージを受けやすくなるのです。
その結果、粘膜の回復が遅れてしまい、口内炎ができやすくなると考えられています。
生理中は、経血の影響で鉄分が失われやすい状態です。
また、生理前は身体がデリケートになりやすく、ビタミンB群(とくにビタミンB2やB6)の消費量が増えるほか、食欲不振で栄養が偏ることも。
ビタミンB群は、粘膜の修復や再生に深くかかわっているため、不足すると口内炎ができやすくなったり、治りにくくなったりします。
「今ある口内炎をなんとかしたい!」といったときに試してほしい、できるだけ早く治すための具体的な対策を6つご紹介します。
市販の口内炎治療薬は、痛みをやわらげたり、治りを早めたりするのに効果的です。
おもな市販薬の種類は、以下のとおりです。
| 薬のタイプ | 特徴 |
|---|---|
| パッチ | ・患部を覆い、刺激から保護しながら薬効成分を届ける・食事の邪魔になりにくく、剥がれにくい |
| 塗り薬 | ・患部に直接塗って炎症を抑えたり保護したりする |
| スプレー | ・口内全体に広がり、広範囲の口内炎や塗りにくい場所に適している |
| 内服薬 | ・身体の内側から体質の改善をしたい方に向いている・疲れや栄養不足が原因と思われる口内炎に効果を示しやすい |
迷った場合は、薬剤師や登録販売者に相談して、症状やライフスタイルにあったものを選びましょう。
ビタミンB2やB6は粘膜の健康を保ち、再生を促す重要な栄養素です。これらが不足すると、口内炎が治りにくくなってしまいます。
以下の食材を意識的に摂取すると良いでしょう。
| 栄養素 | 多く含まれる食材 |
|---|---|
| ビタミンB2 | ・レバー・牛乳・卵・納豆 |
| ビタミンB6 | ・鶏むね肉、・まぐろ・バナナ・にんにく |
毎日の食事に取り入れることを意識し、難しい場合はサプリメントの活用も検討してみてください。
口内炎があるときは、患部を刺激しないことが大切です。
以下のような飲食物は痛みが強くなるだけでなく、治癒を遅らせてしまう恐れがあるため避けてください。
- 辛いもの、香辛料の強い食べ物
- 熱すぎる・冷たすぎる飲食物
- 酸味の強いもの(レモン、お酢など)
- 硬いもの(煎餅、フランスパンなど)
やわらかく消化のよい食事を、ぬるめの温度でとるように心がけましょう。
口内の細菌が増えると、口内炎が悪化する可能性があるため、食後や就寝前にはていねいに歯磨きをして、口のなかの清潔を保ちましょう。
- 刺激の少ない歯磨き粉を選ぶ
- やわらかい歯ブラシを使い、口内炎に触れないように注意する
- 殺菌作用のあるマウスウォッシュや、うがいで口のなかを清潔にする
ケアのあとは、口内の乾燥防止のため、専用の保湿剤を使用すると雑菌の繁殖を防ぐ効果が期待できます。
こうしたこまめな工夫が、治りを早める手助けとなります。
疲れや寝不足が続いていると、身体の免疫機能が低下し、治癒力も落ちてしまいます。
とくに生理前は、ホルモンバランスの影響で体調を崩しやすい時期です。
身体の休息を促すために、以下のような対策を取り入れてみましょう。
- 22時までに就寝する
- 昼寝を20分ほどとる
- スマートフォンやパソコンを就寝前に見ない
- カフェインを控える
無理をせず、身体をしっかり休めることが口内炎の回復につながります。
口内炎があると、つい舌や指で触ってしまいがちですが、これが悪化の原因になることがあります。
刺激によって傷が広がったり、細菌が入り込んだりするリスクがあるため、できるだけ触れず、自然に治るのを待ちましょう。
治癒を早めるには、我慢も大切です。
生理前の口内炎で悩まされたくない方は、日頃の生活習慣の見直しが大切です。
とくに生理前は、より意識的にこれから紹介する対策を取り入れましょう。
バランスの取れた食生活は、生理前に崩れがちなホルモンバランスや自律神経の乱れを整え、口内炎の発生を予防する効果が期待できます。
以下を意識的に摂取してみてください。
| 栄養素 | 多く含まれる食材 |
|---|---|
| ビタミンB群 | ・豚肉・納豆・卵・乳製品 |
| ビタミンC | ・ブロッコリー・パプリカ・いちご・キウイ |
| 鉄分 | ・ほうれん草・小松菜・ひじき・赤身肉 |
| 亜鉛 | ・牡蠣・牛肉・豚レバー・ナッツ類 |
カフェインやアルコールの過剰摂取は、口内を乾燥させたり、栄養素の吸収を妨げたりするため、生理前は控えめにすると良いでしょう。
生理前は、ホルモンバランスの変化で身体が疲れやすく、ストレスも感じやすくなります。
心身を整えるには、以下の工夫での休息とリラックスが欠かせません。
- 質の良い睡眠を十分にとる
- 好きな音楽を聴く、湯船にゆっくり浸かるなどリラックスできる時間を作る
- ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を取り入れる
ストレスを溜めない仕組みづくりによって、自律神経の乱れを抑え、免疫力低下の防止につながります。
日頃から歯磨きや舌磨きを習慣づけて、口腔内を清潔に保ち続けることが口内炎予防に大切です。
とくに夜寝る前は丁寧なケアをおこなうことで、口内炎が形成される理由のひとつである細菌の繁殖を防ぎます。
歯磨きやうがいなどで口のなかを清潔にしたあとは、保湿も忘れずにおこないましょう。
口のなかの乾燥は雑菌が増える原因にもなるため、口腔内専用の保湿剤や保湿ジェルを活用してみてください。
身体が冷えると血行が悪くなり、免疫力が下がります。
とくに生理前は冷えやすくなるため注意が必要です。
- 腹巻きや湯たんぽを活用する
- 温かい飲み物を積極的にとる
- シャワーだけで済ませず湯船につかるなどで身体を内側から温めましょう。
これらの工夫で身体が芯から温まり、血行が改善されて口内炎の予防にもつながります。
体質改善を目指すなら、漢方やサプリメントの活用も選択肢のひとつです。
生理前の不調に合わせた漢方薬は、根本からの改善をサポートしてくれることがあります。また、食生活だけでは補いきれない栄養素は、サプリメントで補うのも有効です。
ただし、漢方やサプリメントは、体質や体調によって合う・合わないがあります。
使用する際は、医師や薬剤師に相談すると安心です。
ほとんどの口内炎は、できてから数日~1週間程度で自然に治ります。
しかし、なかには病院での診察が必要なケースもあります。
以下のような場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
- 口内炎が2週間以上治らない
- 数が増えたり、大きくなったりする
- 強い痛みや発熱をともなう
- 再発をくり返す
これらの症状が見られる場合は、生理以外の原因で口内炎ができている、別の病気が隠れているなどが考えられます。
たとえば、一言で「口内炎」と言っても、ホルモンバランスの乱れで起こるアフタ性口内炎だけでなく、ウイルス性口内炎、カタル性口内炎、ニコチン性口内炎などさまざまです。
口腔外科、歯科、皮膚科、または婦人科などで相談してみましょう。
生理前にできる口内炎は、単なる口のトラブルではなく、ホルモンバランスの変化や自律神経の乱れなど、女性の身体ならではのデリケートな変化が影響しています。
紹介した「早く治す対策」と「防ぐための生活習慣」の実践で、つらい口内炎の悪循環を断ち切り、生理前でも快適に過ごせるようになるでしょう。
- 生理前の口内炎は、ホルモンバランス、自律神経、栄養不足が原因の可能性がある
- できてしまった口内炎は、市販薬や栄養補給、刺激を避けて早めに対策する
- 普段からの食生活や睡眠、ストレスケアで予防する
- 口腔ケアや冷え対策も口内炎予防に有効である
- 症状が続く場合は、早めに医療機関を受診する