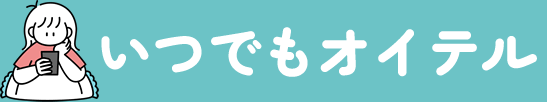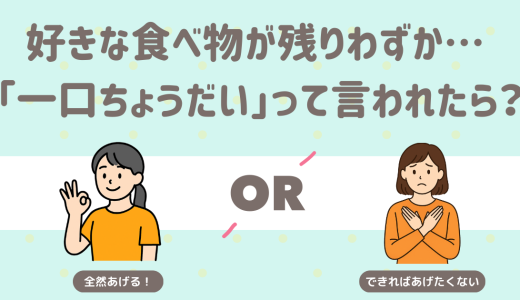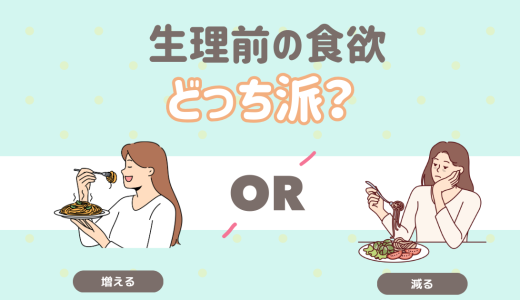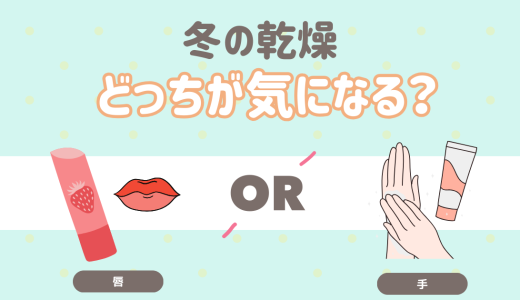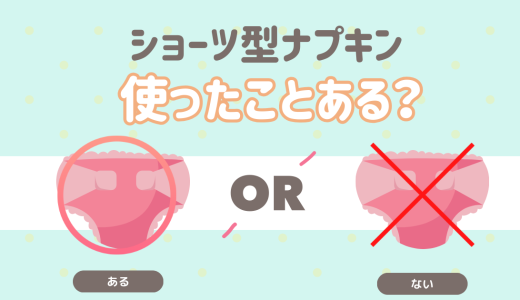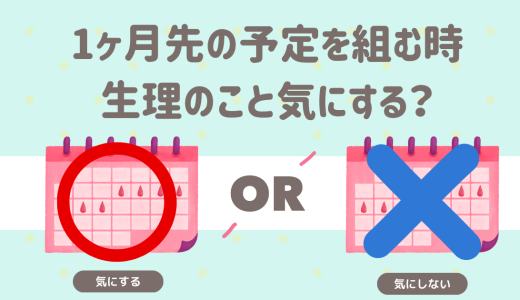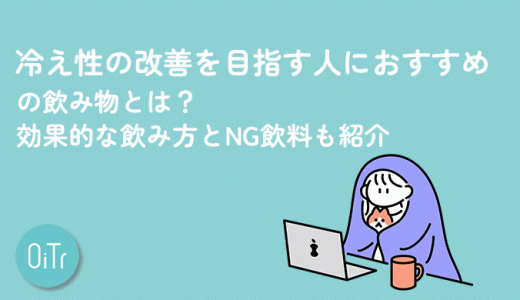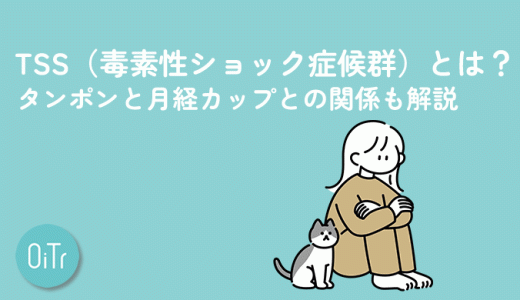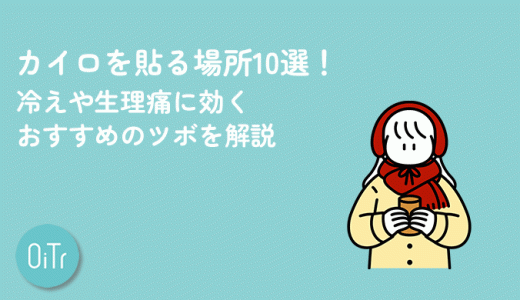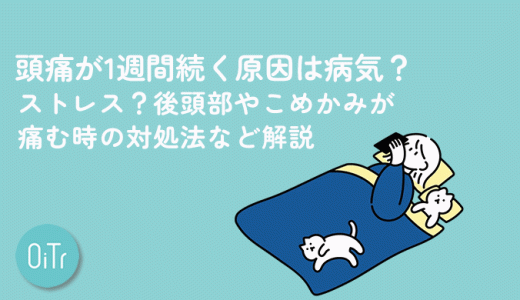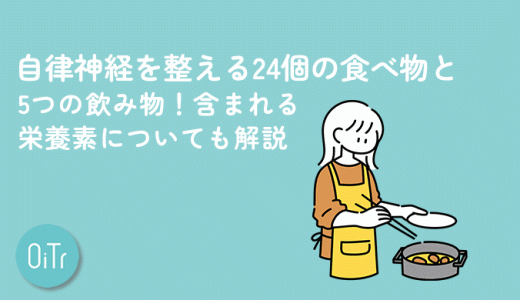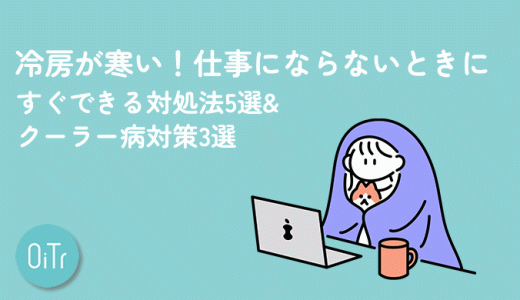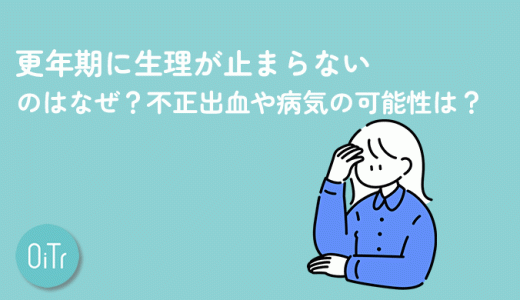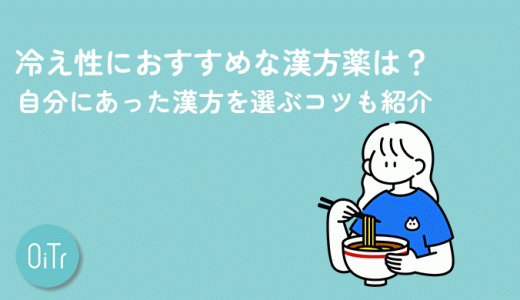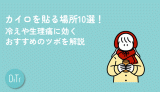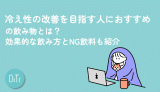冷え性を根本から改善するには、体質に合った食べ物を選び、毎日の食事に取り入れることが大切です。
この記事では、冷えのタイプ別におすすめの栄養素や食材を詳しく解説するとともに、体を温めやすくする食べ方のコツや、続けやすい食生活の工夫も紹介しています。
体の内側から冷え対策を始めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
\アンケート実施中/
冷え性を改善するには、血行や代謝を内側から整える栄養素を意識することが大切です。
とくに体温を生み出す「筋肉量」や「血流」を保つうえで、日々の食事が重要な役割を果たします。
ここでは、冷え性対策に欠かせない代表的な栄養素を見ていきましょう。
たんぱく質は筋肉の材料となり、体内で熱をつくるために欠かせない栄養素です。
とくに加齢や運動不足によって筋肉量の減少が起こると、体温が下がりやすくなるため、冷えを感じやすくなります。
そのため、朝・昼・晩の食事でしっかり補給することが、体温維持に大切です。
また、肉や魚、大豆製品などに含まれる良質なたんぱく質は、筋肉の維持だけでなく、代謝や免疫力のサポートにも役立ちます。
冷えが気になる方は、食事のたびに意識して取り入れるようにしましょう。
鉄分は、血液中で酸素を運ぶヘモグロビンを構成する栄養素です。
鉄が不足すると、体のすみずみに酸素が届かず、細胞が熱を生み出せなくなってしまいます。
とくに女性に多い「鉄欠乏性貧血」は、手足の冷えや疲れやすさの原因になることも少なくありません。
レバーや赤身肉、貝類、青のりなどを意識してとるとともに、鉄の吸収を助けるビタミンCもあわせてとると効率的です。
冷えやすい方は、鉄不足による体温低下の可能性も考えてみましょう。
ビタミンEは、毛細血管の血流を促し、体のすみずみまで温かい血液を届けるのを助けてくれます。
冷え性の原因のひとつである血行不良にアプローチできる栄養素として、積極的にとりたい成分のひとつです。
アーモンドやかぼちゃ、ほうれん草、魚卵などに多く含まれており、毎日の食事の中で取り入れやすい栄養素といえます。
抗酸化作用もあるため、老化や生活習慣の乱れが気になる方にもおすすめです。
ビタミンB群は、糖質や脂質・たんぱく質をエネルギーに変換する働きがあり、体の内側から「体熱」を生み出すために不可欠です。
とくにB1やB2は、食べたものをしっかりエネルギーに変えて、基礎代謝を維持するうえで役立ちます。
豚肉や玄米、レバー、大豆製品などに多く含まれており、冷えのタイプが「全身型」や「下半身型」の方は意識してとりたい栄養素です。
脳の働きや神経機能の維持をサポートするビタミンB1は、ストレスによっても消費されやすいため、生活習慣が乱れがちな方は、とくに意識して取り入れましょう。
亜鉛やマグネシウムは、体内のさまざまな酵素の働きを助け、代謝をスムーズに保つミネラルです。
とくにマグネシウムは、筋肉の収縮やリラックス、自律神経の調整にもかかわっており、冷え性の根本改善につながると考えられています。
亜鉛は牡蠣やレバー、マグネシウムは大豆や海藻、ナッツ類に多く含まれており、いずれも現代人に不足しやすい栄養素です。
冷えだけでなく、疲れやすさやだるさがある方は積極的に取り入れてみましょう。
冷え性を和らげるには、体質や冷えのタイプに合った食べ物を選ぶことが大切です。
同じ冷え性でも、血行不良が原因の方もいれば、筋肉量や代謝の低下、腸内環境の乱れなど、背景は異なります。
冷えの原因に応じて、食事から体の内側にアプローチしていきましょう。
- 四肢末端型冷え症➔血行促進を意識して
- 下半身型冷え性➔筋肉量アップと血行促進を意識して
- 全身型冷え症➔エネルギー代謝の底上げを意識して
- 内臓型冷え症➔腸内環境と自律神経の働きを意識して
- 混合型冷え症➔全体的な代謝サポートと血流改善を意識して
しょうがは薬膳の世界でも「温性」に分類され、「ジンゲロール」「ショウガオール」などの辛味成分には、血流を促進し、体を内側から温める働きがあります。
冷え性対策としては、おろして汁物や炒め物に加えるほか、はちみつと一緒にお湯に溶かして飲む方法もおすすめです。
とくに「四肢末端型冷え症」の方に向いており、温活に欠かせない定番の食材といえるでしょう。
にんにくには、独特の香りのもとである「アリシン」が含まれており、血液をサラサラに保つ効果があるとされています。
血管を拡張させて血流を促すため、冷え性のなかでも血行不良が主な原因となるタイプの方におすすめです。
加熱しても有効成分がある程度残るので、炒め物やスープの風味付けに使いやすいのもメリットといえるでしょう。
玉ねぎもにんにくと同様、「アリシン」を含む食材です。
血液の流れをスムーズにし、毛細血管までしっかり血を巡らせるサポートをしてくれます。
冷えによる肩こりや手足の冷たさが気になる方は、積極的に取り入れてみてください。
効率よく摂取するには生のままサラダにするのがおすすめ。
独特な辛味が苦手な場合はスープや煮込み料理にするなど、毎日の食事に取り入れやすい点も魅力です。
サバやイワシなどの青魚には、EPAやDHAといった不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。
これらの成分は、血液をさらさらに保ち、血管の柔軟性を保つ働きがあるため、血流の改善に役立つのです。
とくに「四肢末端型冷え症」の方に向いており、日常的に取り入れたい冷え対策食材のひとつといえるでしょう。
良質なたんぱく質も含まれているため、筋肉量の維持にもつながります。
かぼちゃは、抗酸化作用のあるビタミンEを豊富に含む食材で、血流を改善することで体の末端まで温かさを届ける効果が期待できます。
また、食物繊維やβ-カロテンも含まれており、栄養バランスの良さも魅力です。
煮物やスープ、グラタンなど調理の幅が広く、温かい料理に取り入れることで冷え対策にもなります。
にんじんに多く含まれるβ-カロテンには、血流を整え、体の末端まで酸素や栄養を届ける働きがあるとされています。
また、抗酸化作用もあるため、冷えとあわせて疲れやすさや肌荒れが気になる方にもおすすめの野菜です。
加熱すると甘みが増して吸収率も高まるため、スープや煮物など温かい料理で取り入れてみましょう。
ごぼうは水溶性と不溶性、両方の食物繊維を含んでおり、腸内環境を整えるのに役立ちます。
腸の働きがよくなることで自律神経のバランスが整い、代謝もスムーズになるのです。
とくに「内臓型冷え症」の方におすすめで、きんぴらや味噌汁の具など、温かい調理法で取り入れると、体の内側からポカポカしやすくなります。
黒豆は良質なたんぱく質に加えて、ポリフェノールを多く含むのが特徴です。
血流改善と代謝促進の両面にアプローチでき、冷え性対策として心強い存在といえます。
煮豆や炊き込みご飯、スープに取り入れれば、栄養価の高い温活メニューに早変わりするのも嬉しいポイントです。
甘すぎない調味で仕上げると、血糖値への影響も抑えられます。
キムチやぬか漬け、味噌などの発酵食品には、乳酸菌や酵母などの有用菌が豊富に含まれています。
これらの菌は腸内環境を整える働きを持ち、自律神経のバランスを整えるサポートにもなるのです。
ただし、納豆やヨーグルトなど一部の発酵食品には体を冷やす性質もあるため、温かいスープや鍋料理などと組み合わせて取り入れると、体への負担を抑えながら効果的に活用できます。
豚肉には、糖質をエネルギーに変え、体の内側から冷えを改善するビタミンB1が豊富に含まれています。
とくに脂肪分が少ないヒレ肉や赤身は、「全身型冷え症」の方に適した食材です。
炒め物・蒸し料理・スープなどにすれば、油を使いすぎずヘルシーに仕上がり、毎日の献立に取り入れやすく栄養バランスの面でも優秀といえます。
レバーは鉄分とビタミンB群を同時にとれる、冷え性対策に優れた食材です。
鉄分は血液の材料となるヘモグロビンの生成を助け、体のすみずみまで酸素と熱を運ぶサポートをします。
また、ビタミンB群が糖や脂質の代謝を助けるため、冷えやすい体質の根本的な改善が期待できるでしょう。
とくに「全身型」や「貧血による冷え」に悩む方にはおすすめです。
もち麦は水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく含む穀物で、腸内環境を整えることで自律神経の安定にもつながり、冷えの根本改善が期待できます。
また、糖質の吸収がゆるやかで血糖値の急上昇を防ぐため、日々のエネルギー代謝を安定させる効果も。
白米に混ぜて炊いたり、スープに加えたりと、毎日の食事に無理なく取り入れやすいのが大きな魅力といえます。
ブロッコリーにはビタミンB群がバランスよく含まれており、エネルギー代謝をスムーズに保つことで冷え性改善に役立ちます。
また、鉄やビタミンC、葉酸なども豊富に含まれているため、女性に多い「貧血型冷え」や「全身型冷え症」の対策にも効果的です。
スープや温野菜として取り入れることで、体を冷やさず栄養を効率よく吸収できます。
納豆は良質なたんぱく質を含むだけでなく、血栓予防に役立つ酵素「ナットウキナーゼ」を含む発酵食品です。
この酵素が血液をさらさらに保ち、血行を促進してくれるため、末端の冷えにも効果が期待できます。
また、女性ホルモンに近いとされる大豆由来のイソフラボンやビタミンK2なども豊富で、冷えに限らず、女性の体を内側から支えてくれる食材です。
卵は、体の熱をつくり出す筋肉の材料となる良質なたんぱく質をバランスよく含む食材です。
加熱しても栄養価がほとんど変わらず、冷えの原因となる筋肉量の減少を防ぐうえで、日々の食事に欠かせない存在といえます。
また、ビタミンB群や鉄分も含まれているため、「下半身型」や「全身型」の冷え性対策にも有効です。
調理法のバリエーションも豊富なので、飽きずに取り入れられます。
冷え性を改善するには、食材の選び方だけでなく、日々の「食べ方」そのものにも目を向けることが大切です。
ここでは、冷え対策をより効果的にするための実践的な食事のポイントを紹介します。
体を内側から温めるには、食材そのものだけでなく、調理法にも気を配ることが大切です。
冷たいものは胃腸に負担をかけ、体温の低下を招きやすくなるため、なるべく温かい料理を選びましょう。
スープや煮物、蒸し料理などは、食材の栄養も逃しにくく、冷え性改善に適した調理法といえます。
また、食事の最初に温かい汁物をとることは、体を内側から温める習慣としておすすめです。
冷え性対策では、体を冷やしやすいとされる食材の摂りすぎに注意が必要です。
たとえば、生野菜や果物、白砂糖、カフェイン飲料などは体を冷やす性質をもつため、とくに寒い季節や体調が不安定なときには控えめにするとよいでしょう。
ただし、完全に避けるのではなく、温かいスープや味噌汁、薬味をプラスするなどの工夫で、体を冷やさない食べ方に変えることが可能です。
体を温める食材などとのバランスを意識して取り入れましょう。
冷えを改善するには、食事を抜かずに1日3回しっかりと食べることも大切です。
とくに朝食を抜いてしまうと、体温が上がりづらくなり、午前中ずっと冷えたまま過ごす原因になります。
また、空腹時間が長くなることで代謝も落ちやすくなり、筋肉量の減少や血流の悪化にもつながってしまうのです。
毎食を適量・適切なタイミングでとることで、体内リズムや自律神経が整い、冷えにくい体づくりにつながっていきます。
冷え性の改善には、日々の食事に体を温める食材や栄養素を取り入れることが大切です。
筋肉量を保ち、血流や代謝を整える食べ物を意識して選ぶことで、冷えにくい体づくりが少しずつ実現できます。
また、冷えのタイプに合った食材を選ぶと、より効果的な対策につながっていくのです。
栄養バランスのとれた食事や温かい調理法、規則正しい食習慣を心がけて、冷えに悩まない毎日を目指していきましょう。
- 冷え性は、筋肉量・血流・代謝に関わる栄養素を日々の食事から補うことで、内側から改善が期待できる
- 冷えのタイプ(末端型・内臓型など)に合わせて、相性の良い食材を選ぶことが重要
- 温かい料理を意識し、体を冷やす食材とのバランスを考えながら、無理なく続けられる食習慣をつくる