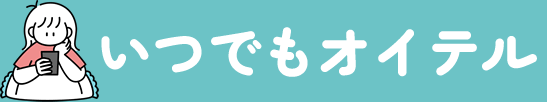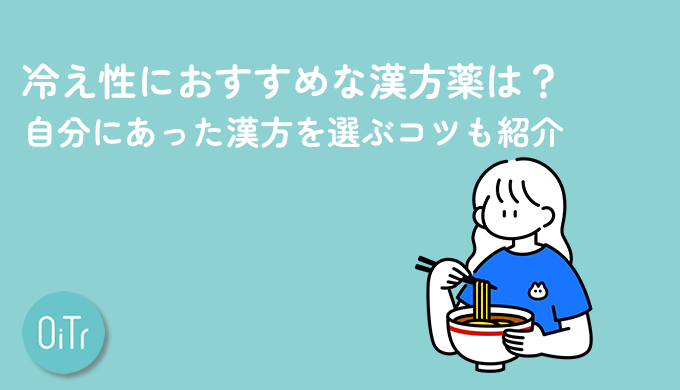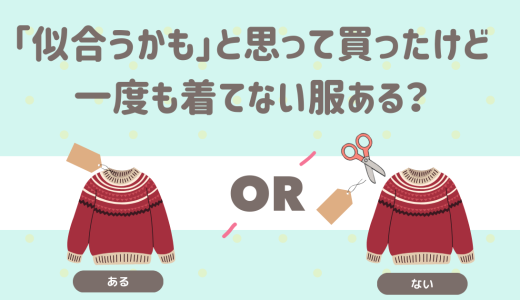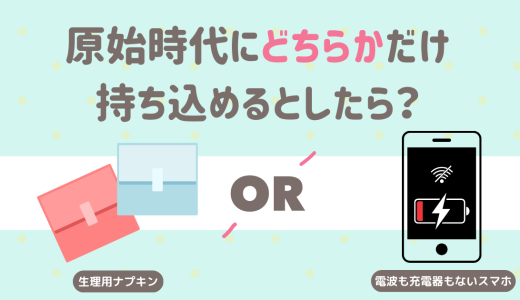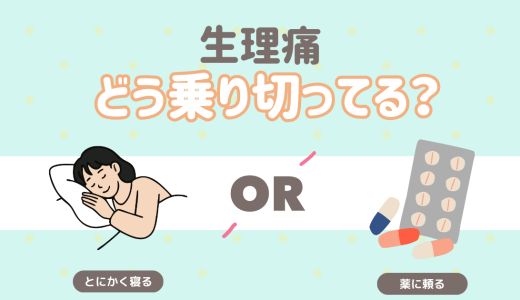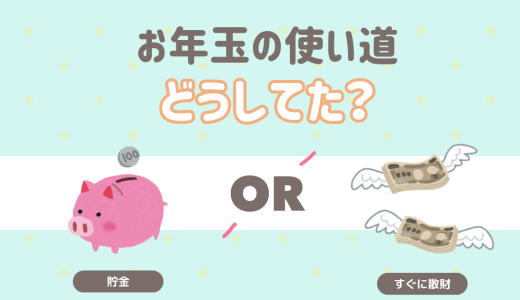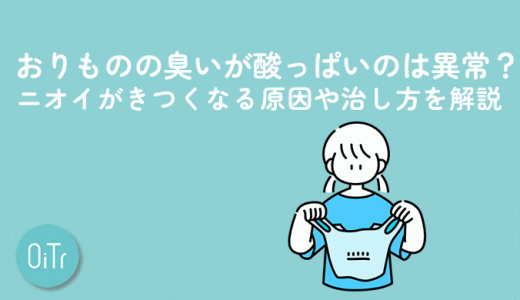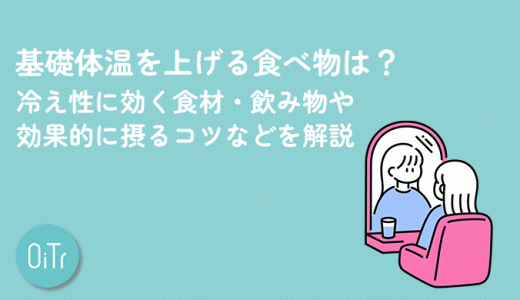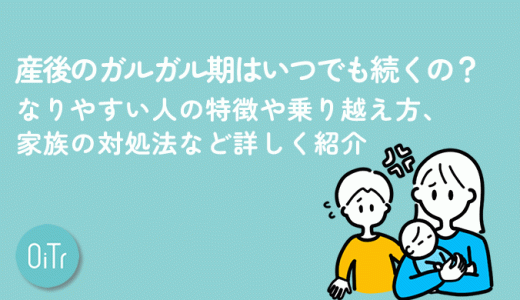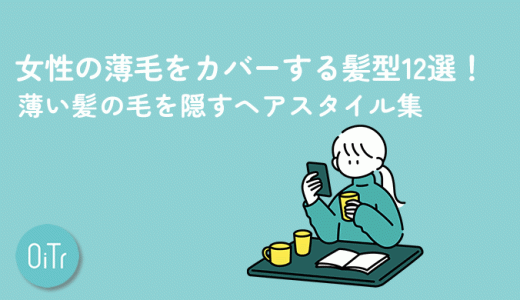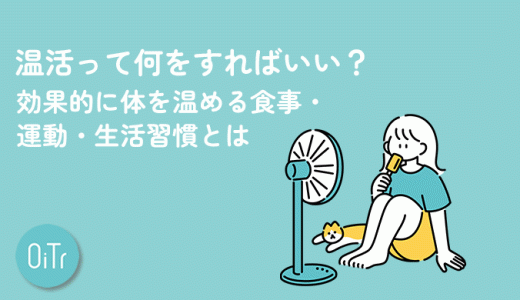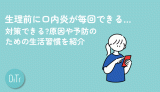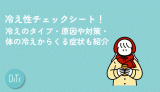「冷え性に一番効いたと言われる漢方はどれ?」「口コミで人気の漢方薬を試してみたい」と考える人は多いのではないでしょうか。
ドラッグストアや通販では、たくさんの漢方が売られているため、どれを選ぶか迷うこともあるでしょう。
この記事では、冷え性に効果的とされる代表的な漢方薬と、それぞれの特徴や選び方を紹介します。
漢方を選ぶ時のポイントや、服用にあたっての注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。
\アンケート実施中/
「この漢方が自分には合っていた」「長年悩んでいた冷えが楽になった」と口コミなどでよく名前が挙がる漢方薬はあります。
どれも冷え症の原因にアプローチする効果が期待できるため、体質や症状に合えば効果を実感できるでしょう。
ここからは口コミで話題にのぼることが多い漢方薬のなかでも、代表的な漢方薬を紹介します。
身体を温めて、熱を作るのを手助けすることで、手足の末端を温めるとともに、冷え症による頭痛や腰痛が気になる人に用いられる漢方薬です。
体力は中等度以下で「手足の冷えがつらくて眠れない」「冷えるとお腹が痛くなる」などを訴える人に使われ、ツムラ漢方の38番として知られています。
クラシエから第2類医薬品としても販売されていますよ。
身体が冷えるだけでなく、月経前に下腹部が張ってつらい人や、肩こりや頭重感もあって血の巡りが悪い人には、桂枝茯苓丸が使われます。
血流を促して「瘀血(おけつ)」と呼ばれる血のめぐりが気になる人に使われることが多く、冷えや月経トラブルを抱える人に選ばれやすい漢方です。
体力が中程度以上ある人向けで、冷えとともにのぼせや肌荒れ、月経痛、月経不順をともなうタイプに選ばれることが多いでしょう。
ツムラやクラシエから市販薬としても販売されており、ドラッグストアなどで手に入りやすいのも魅力です。
冷えやすく、むくみやすい人や、月経が不安定で疲れやすい人に使われる漢方です。
虚弱体質で冷えを感じやすい女性に処方されることが多いでしょう。
ツムラやクラシエなどから市販薬としても販売されています。
ツムラ漢方では、23番として知られているでしょう。
女性ホルモン分泌の乱れによる冷え性がある人や、イライラや不安感がつらくて眠れない人に使われる漢方です。
自律神経の乱れや、月経前の不調が気になる人に選ばれやすいでしょう。
PMS(月経前症候群)や更年期障害にも処方されることがある漢方です。
体力が中程度で、ストレスの影響を受けやすいタイプに処方・推奨されることがあります。
ツムラやクラシエから市販の商品も出ていますよ。
漢方薬は、冷え性そのものを直接治すというよりも、身体の内側からバランスを整え、冷えの背景にある体質やバランスの乱れに働きかけるという特徴があります。
冷えの背景にある身体の状態を整えることで、結果的に冷えの感じ方がやわらぐことも。
ここから、漢方の考え方と冷え性の原因、その関係性について解説します。
漢方医学では、冷え性をはじめとした心身の症状は「気(き)・血(けつ)・水(すい)」の異常が関係していると考えられています。
気血水の特徴は、以下のとおりです。
- 気:エネルギーや生命力を巡らせる力
- 血:栄養を含む血液の流れ
- 水:体内の潤いや代謝に関わる水分
これらのバランスが乱れることで、身体の末端まで温かさが届かず、手足の冷えや内臓の冷えにつながるとされています。
女性は、月経の影響などで血が少なくなり、全身に熱を届けられなくなったり、お腹の血流が滞りやすかったりすることから冷えを感じやすいと考えられていますよ。
漢方は、気血水のバランスを整えることで知られ、血流や自律神経、ホルモン分泌などにも関係すると考えられています。
冷え性は、単に「寒いから冷える」というだけではなく、血の巡りが滞って身体の末端や内臓まで十分な温かさが届きにくくなったり、自律神経が乱れて血管の収縮や拡張がうまく調整できず、体温のコントロールが難しくなったりすることも関係しているのです。
漢方薬は、体内のバランスの乱れに着目し、血流や神経、ホルモンの働きに関わるとされるため、結果的に冷え性の緩和を目指したい方に用いられることも少なくありません。
冷え性といっても、症状の出方や体質は人それぞれです。
月経不順や更年期などの不調をともなう場合もあり、冷えのタイプによって選ばれる漢方薬は変わってきます。
ここからは、タイプ別に冷え性向けの漢方の選び方をみていきましょう。
「足先が氷のように冷たくて眠れない」という末端の冷えに悩んでいる人は、血流が滞りやすく、熱が身体の中心から末端まで届きにくい状態かもしれません。
漢方では、こうした冷えを「血行不良」や「体を温める力の不足」として捉え、その体質に応じた処方を選びます。
このタイプに用いられることが多いのが、当帰四逆加呉茱萸生姜湯や当帰芍薬散です。
「上半身はのぼせるほど熱いのに、太ももやお尻、足先だけひんやりする」という下半身だけが冷えるタイプは、血流が滞っている可能性があります。
デスクワークや運動不足、姿勢の乱れなどが原因となりやすく、女性に多くみられる冷えタイプの1つです。
桂枝茯苓丸は、血の巡りに着目した処方で、骨盤まわりの不調や冷えとともに、月経痛・月経不順・肌荒れなどの不調にも用いられることがあります。
全身の冷えを感じる人は、気血の不足やエネルギーの巡りの低下が関係している可能性があります。
こうしたタイプは、冷えだけでなくむくみや貧血、月経不順などをともなうことも。
当帰芍薬散は血を補って巡りを整えるとされ、虚弱体質・冷え・むくみを抱えがちな女性に使われることが多いです。
冷えとともに生理不順がある人や、更年期に入ってから冷えがつらくなった人は、自律神経や女性ホルモンのバランスの乱れが深く関係していると考えられます。
加味逍遙散は、気の巡りを整えながら血流を促すとされ、冷えや倦怠感、情緒不安定などに選ばれることが多い漢方です。
「自分の冷え性に効く漢方を選びたい」と思っても、さまざまな疑問によって躊躇している人も少なくないでしょう。
ここからは、冷え性向けの漢方を選ぶ際によくある疑問とその答えを解説します。
漢方薬は「なんとなく身体によさそう」と思われがちですが、体質に合っていないものを服用すると、効果が出ないだけでなく、逆に体調を崩すことがあります。
たとえば、暑がりな人が身体を温める作用が強い漢方を飲むと、のぼせや発汗、頭痛などの不調を感じるでしょう。
漢方は自分に合っているかどうかがとても重要なため、同じ冷え性でも選ぶべき処方は人によって異なります。
症状が悪化したり、飲み始めて不調を感じたりした場合は、すぐに服用を中止して医師・薬剤師に相談してください。
漢方が合わない時の症状については、以下の記事でくわしく解説しています。
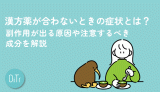 【医師監修】漢方薬が合わないときの症状とは?副作用が出る原因や注意するべき成分を解説
【医師監修】漢方薬が合わないときの症状とは?副作用が出る原因や注意するべき成分を解説
漢方は一部を除いて飲んで、すぐに劇的な効果が出るタイプの薬ではありません。
身体の内側からバランスを徐々に整えていくため、効果を実感するまでには1ヶ月〜3ヶ月程度かかることが多いとされています。
特に冷え性のように慢性的な不調は、少しずつ体質を変えていく過程が必要です。
ただし体質に合った処方であれば、2週間程度で体調の変化を感じることも。
1ヶ月程度服用しても症状がよくならない場合は、薬が身体に合っていない可能性があるため、医師や薬剤師に相談しましょう。
他の薬と成分が重複したり、作用がぶつかったりすることもあるため、注意が必要です。
体調不良があっても、自己判断で漢方薬を追加するのは避けて、医師や薬剤師に相談ましょう。
冷え性に一番効いた漢方薬は、人によって違います。
なぜなら冷えの原因や体質、ライフスタイル、ホルモンの状態などは一人ひとり異なるためです。
体質に合わないものを服用すると、効果が出ないばかりか、体調を崩してしまうおそれも。
市販薬で試してみるのもひとつの方法ですが、症状がつらい場合や迷った時は、医師や薬剤師に相談するのがおすすめです。
効果の実感には個人差があり時間がかかる場合もありますが、自分の体質に合う漢方を飲み続けることで、徐々に体調の変化を感じられるでしょう。
- 冷え性には体質や症状に合わせた漢方薬の選択が大切
- 手足・下半身・全身など冷えのタイプ別に選ぶ処方が異なる
- 体質に合わないと副作用が出ることもあるため注意が必要
- 自己判断せず、医師や薬剤師に相談しながら選ぶのがおすすめ