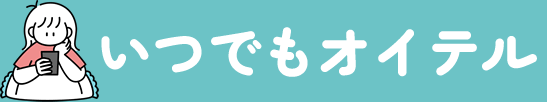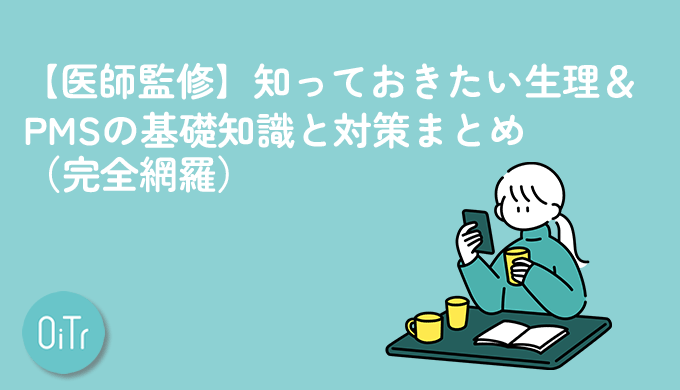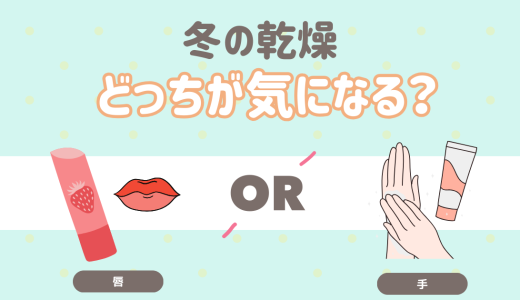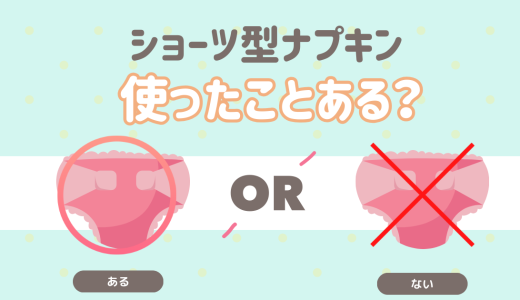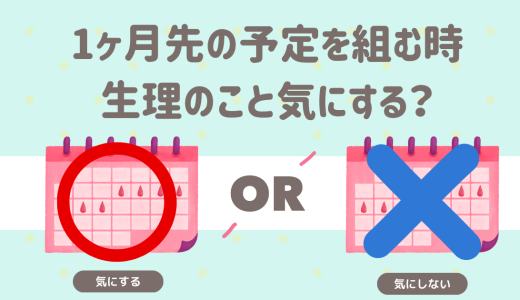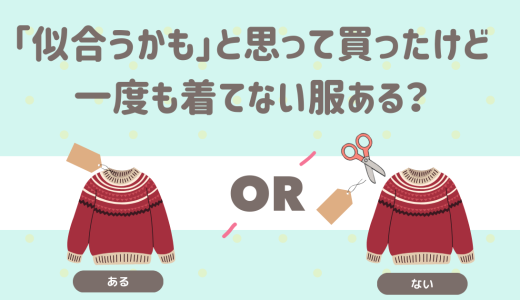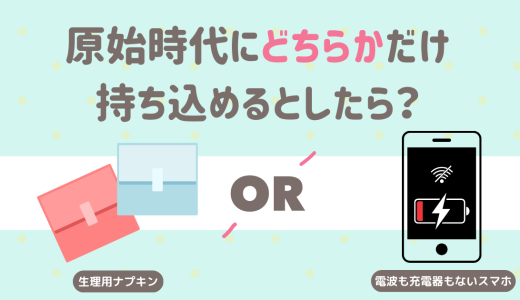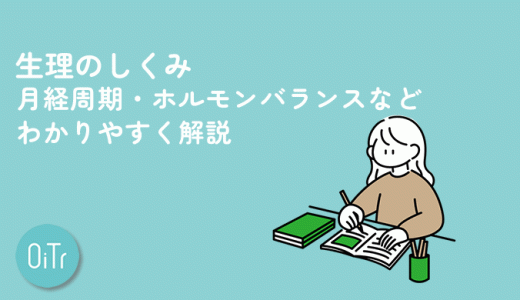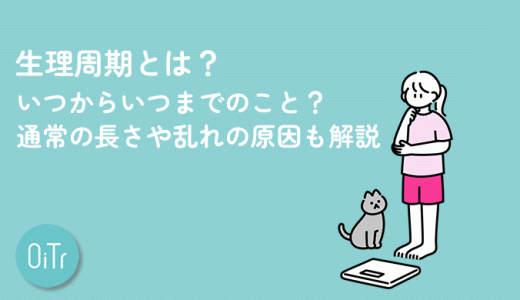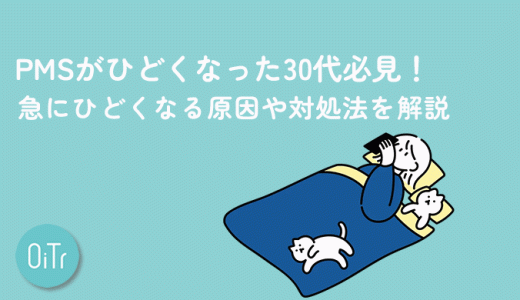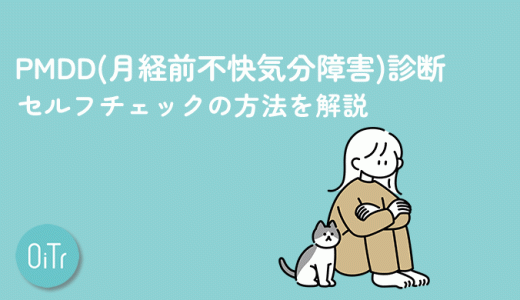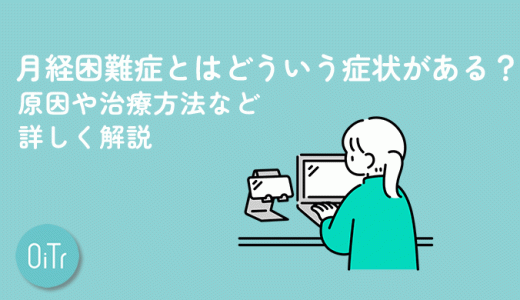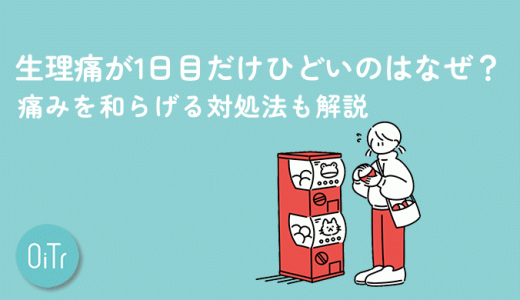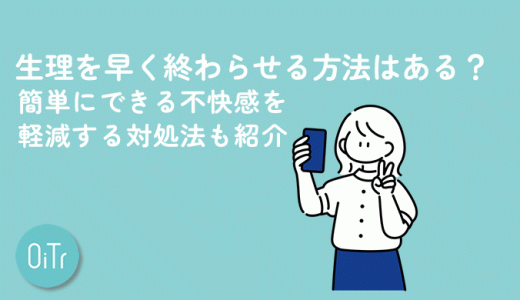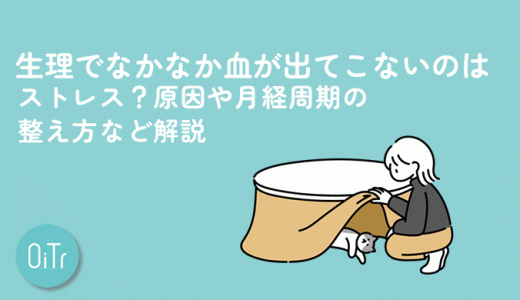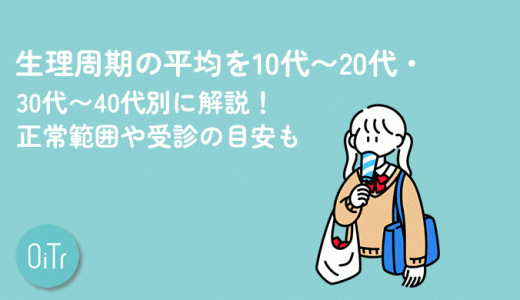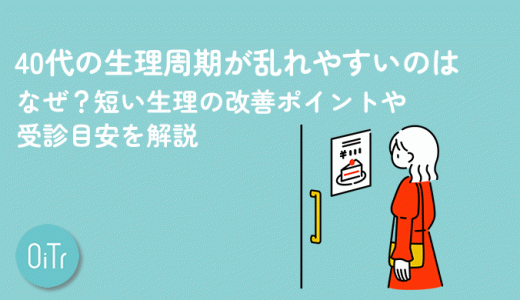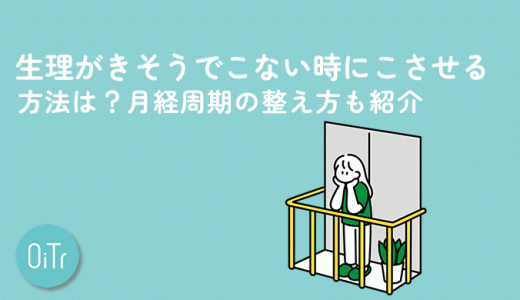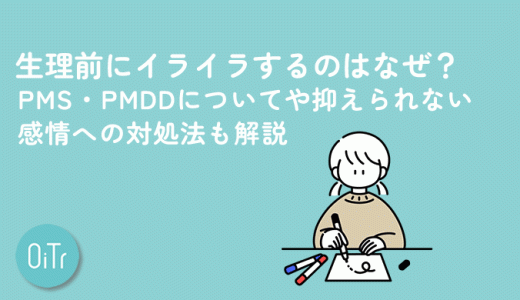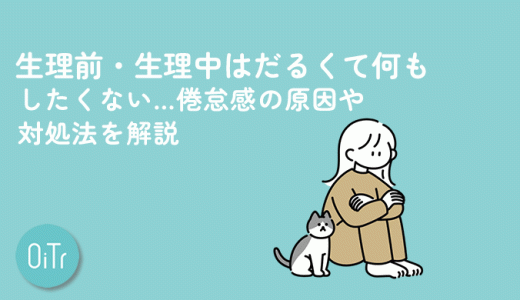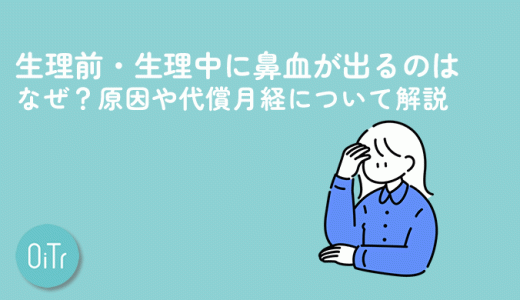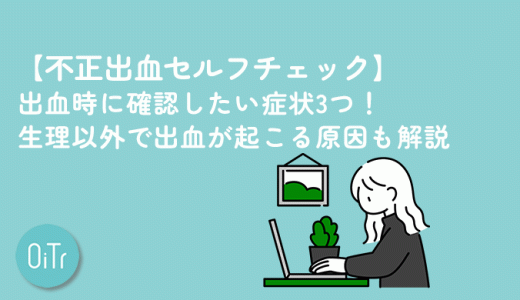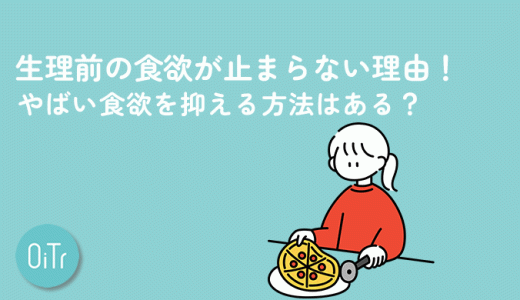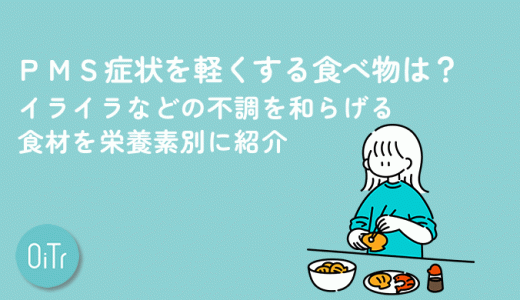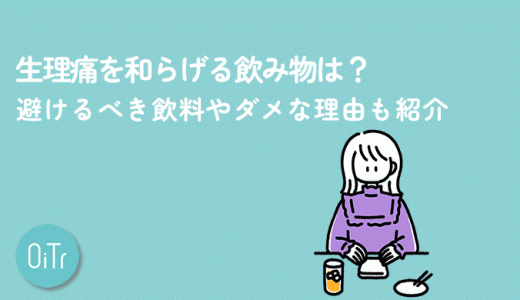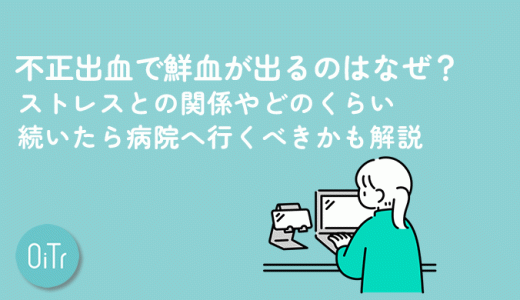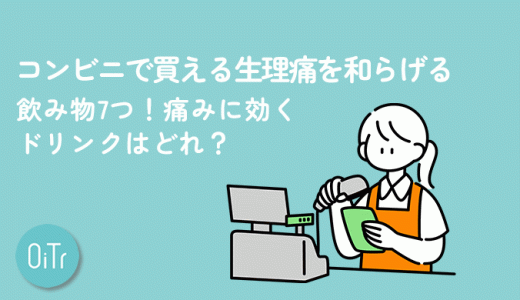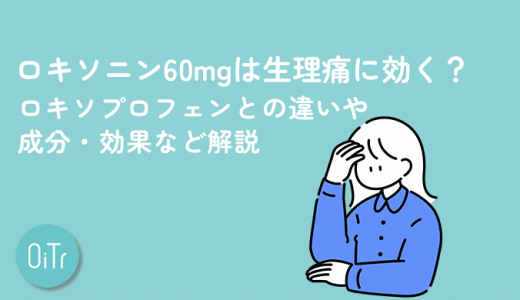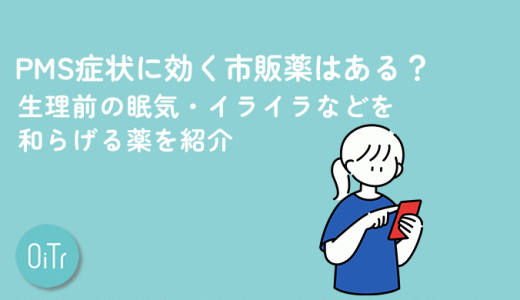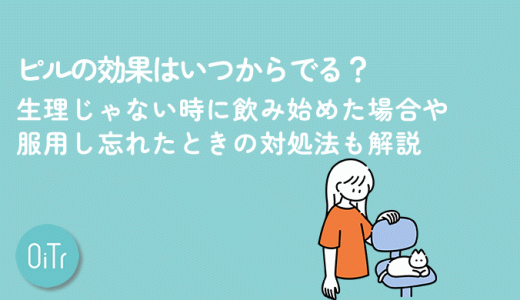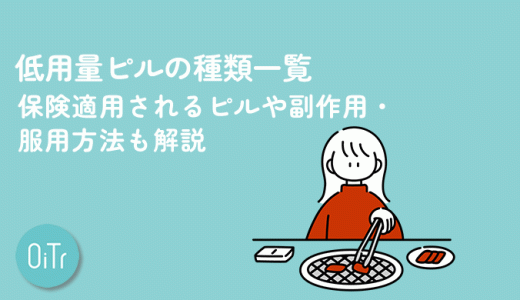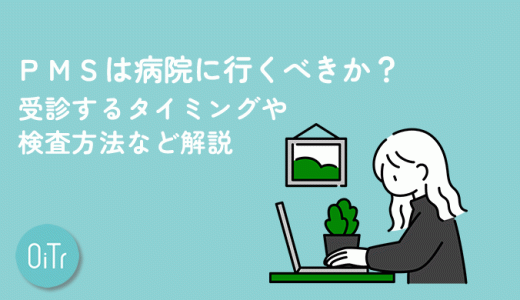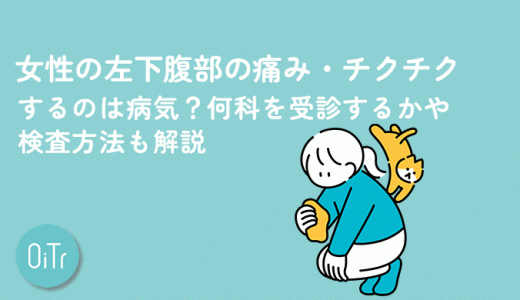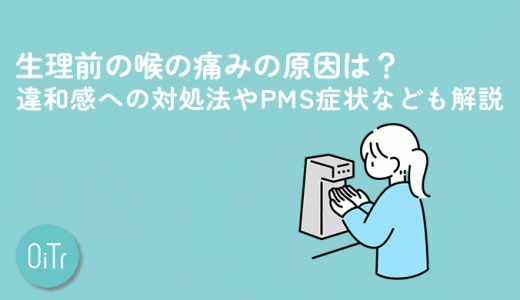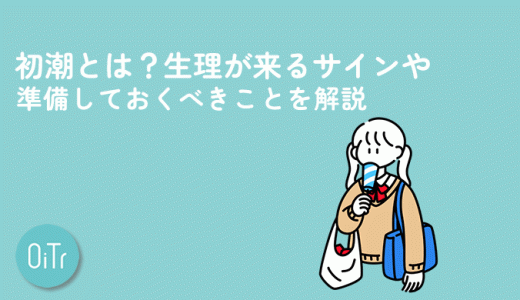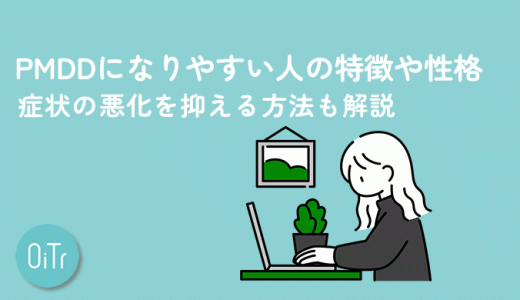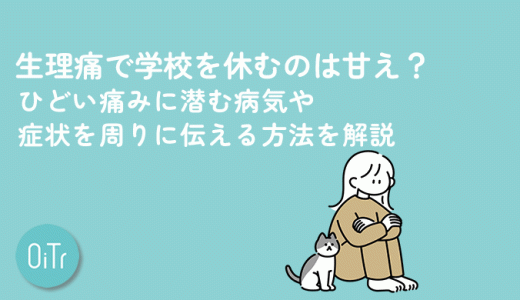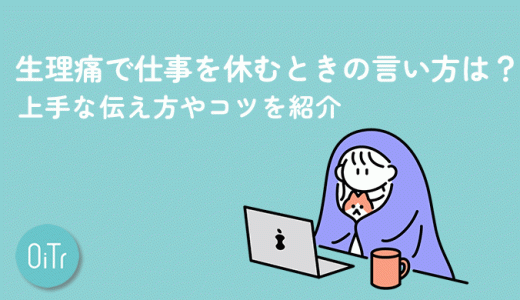沢岻 美奈子 医師
プロフィール
日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医。女性ヘルスケア認定医。神戸にある「沢岻美奈子女性医療クリニック」と恵比寿「Takushi clinic」の院長。子宮がんや乳がん検診、骨粗鬆症検診まで女性特有の病気の早期発見のための検診を2013年の開院以来数多く行なっている。
https://takushiminako.com/
この記事は、生理があるすべての年代の女性を対象に、PMS(月経前症候群)と生理に関する基本的な知識から、具体的な症状、セルフケア、そして医療機関での対処法までを網羅的に解説します。
月経前や月経中の不調に悩む方が、自身の症状を理解し、適切な対策を見つけるための一助となることを目指します。
\アンケート実施中/
PMS(月経前症候群)は、生理前に現れる身体的・精神的な不調の総称です。
一方、生理(月経)は子宮内膜が剥がれ落ち、血液とともに体外へ排出される現象を指します。
多くの女性が生理前や生理中に何らかの不調を感じており、これらは女性ホルモンの変動と密接に関連しています。
このガイドでは、これらの現象を理解し、より快適な日常生活を送るための情報を提供します。
PMS(Premenstrual Syndrome:月経前症候群)は、生理が始まる3~10日前から現れるさまざまな身体的・精神的な症状で、生理が始まると症状が軽くなったり消失したりするものを指します。
日本産科婦人科学会によると、月経のある女性の約70~80%が月経前に何らかの症状を自覚しており、そのうち5.4%が日常生活に支障をきたすほどの重いPMSに悩んでいるとされています。
PMSはれっきとした疾患であり、適切な診断と治療によって症状を緩和することが可能です。
なぜ起こるのか?原因と仕組み
PMSの原因は完全には解明されていませんが、最も有力な説として、排卵後に分泌される女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)の急激な変動が関係していると考えられています。
排卵から生理が始まるまでの期間(黄体期)にはこれらのホルモンが多く分泌されますが、黄体期の後半に分泌量が急激に減少することで、脳内のホルモンバランスや神経伝達物質に影響を与え、PMSの症状を引き起こすと考えられています。
また、ホルモン変動だけでなく、ストレス、食生活、生活習慣、遺伝的要因などもPMSの発症や悪化に関与しているとされています。
真面目、几帳面、我慢強い、完璧主義といった性格的傾向を持つ人もPMSの症状が出やすい傾向にあると言われています。
PMSと似た疾患(PMDD・月経困難症など)
PMSと似た症状を持つ疾患には、PMDD(月経前不快気分障害)や月経困難症などがあります。
- PMDD(月経前不快気分障害)
PMDDはPMSの中でも、特に精神的な症状が著しく強く現れる場合に診断されます。
抑うつ気分、不安感、情緒不安定、怒りっぽさなどが顕著で、日常生活に重大な支障をきたすことが特徴です。
PMSと同様に、生理が始まると症状は軽減または消失します。
PMDDは「うつ病性障害」の一つとして位置づけられています。 - 月経困難症
月経困難症は、生理中に起こる病的な状態を指し、強い下腹部痛や腰痛、吐き気、頭痛、疲労感、イライラなどの症状が見られます。
PMSが生理前の症状であるのに対し、月経困難症は生理中の症状が中心となる点が異なります。
月経困難症には、子宮に原因となる病気がない「機能性月経困難症」と、子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が原因で起こる「器質性月経困難症」があります。
PMSの症状は200種類以上とも言われ、個人差が大きく、同じ人でも月によって症状や程度が異なることがあります。
- 乳房の張りや痛み
- 身体のだるさ、倦怠感
- 日中の眠気、または不眠
- 頭痛、頭重感
- 腹痛、下腹部痛、お腹の張り
- むくみ、体重増加
- 食欲不振または過食、特定の食べ物への渇望
- ニキビや肌荒れ
- めまい、動悸、のぼせ
- 肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛
- 下痢や便秘
- イライラ、怒りっぽくなる
- 情緒不安定、急に涙が出る
- 憂鬱な気分、気分が落ち込む、絶望感
- 不安感、緊張感
- 無気力になる、やる気が出ない
- 集中力や判断力の低下
- 混乱、落ち着かない
- 人との関わりを避ける、引きこもりたくなる
PMSは初経を迎える10代から閉経を迎える50歳前後まで、生理のある女性であれば誰にでも発症する可能性がありますが、特に20代から30代に多く見られるとされています。
- 10代
初経を迎えたばかりの思春期頃から症状が出始めることがあります。
学業や部活動への影響が懸念される場合があります。 - 20代
全体的に症状を自覚する人が多く、精神症状よりも身体症状を強く訴える傾向が見られることがあります。 - 30代
ココロの症状として怒りっぽさやイライラが増える傾向があります。
妊娠・出産経験や子育て、仕事の有無も症状に影響を与えることがあり、出産経験のある女性の方が精神症状を強く感じやすいという報告もあります。 - 40代以降(更年期)
更年期に近づくと、女性ホルモンの分泌量が減少し始めるため、PMSと更年期症状が混在し、区別がつきにくくなることがあります。
生理周期の乱れと共に、イライラや疲れやすさ、頭痛、むくみなど、PMSと共通する症状が現れることがあります。
閉経後はPMSはなくなると考えられます。
自分の症状がPMSによるものかを知るために、症状を記録する「PMS日記」をつけることが推奨されます。
以下の項目が生理が始まる1~2週間前に現れ、生理開始後4日以内に軽減または消失し、かつ日常生活に影響を及ぼしているかを確認しましょう。
- イライラしやすい、怒りっぽくなる
- 憂鬱な気分になる、気分が落ち込む
- 不安感がある、緊張が解けない
- 理由もなく悲しくなる、涙が出る
- 集中力が低下する、やる気が出ない、無気力になる
- 情緒不安定になる、感情の起伏が激しい
- 人と会いたくない、引きこもりたくなる
- 乳房の張りや痛み
- 頭痛、頭重感
- 身体のだるさ、疲れやすい
- むくみ、体重増加
- 腹痛、下腹部痛、お腹の張り
- めまい、動悸、のぼせ
- 食欲の異常(過食または食欲不振)
- 眠気または不眠
- 肌荒れ、ニキビ
- 腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛
これらの項目が複数当てはまり、3ヶ月以上続いている場合はPMSの可能性が高いです。
特に、仕事や学校、家事に支障が出るほど症状が重い場合は、無理をせず医療機関を受診しましょう。
PMSの症状は、日常生活の改善によって緩和が期待できます。
主食、主菜、副菜を揃え、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
- ビタミンB6
精神症状の緩和、貧血やむくみ対策に役立つとされています。カツオ、マグロ、レバー、バナナ、鶏肉などに多く含まれます。 - カルシウム
イライラや気分の落ち込み、むくみ対策に良いとされています。乳製品、小魚、小松菜、ひじき、豆腐などに豊富です。 - マグネシウム
気分改善、身体症状の軽減に効果がある可能性があります。ナッツ類、ほうれん草、豆、海藻類、玄米などに多く含まれます。 - ビタミンE
利尿作用があり、頭痛やむくみ対策に良いとされています。
- カフェイン
イライラや不眠を悪化させる可能性があるため、コーヒー、紅茶、チョコレートなどの摂取は控えめにしましょう。 - アルコール
気分の浮き沈みを増長させる可能性があるため、過度な摂取は避けるべきです。 - 塩分
体内の水分貯留を促し、むくみを悪化させるため、塩分の摂りすぎに注意しましょう。 - 糖分
血糖値の急激な上昇と下降は、イライラや過食を増悪させる可能性があります。
白砂糖を多く含むお菓子などは控え、複合炭水化物(玄米、全粒粉パンなど)を選ぶと良いでしょう。
- 有酸素運動
ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、軽い有酸素運動はPMSの緩和に効果的です。
血行促進、むくみ解消、ホルモンバランスの安定、気分転換、ストレス軽減が期待できます。
週に1回1時間程度からでも、無理のない範囲で継続することが大切です。 - ストレッチやヨガ
体の緊張をほぐし、リラックス効果を高めます。
特に骨盤周りの血流改善にもつながり、PMS症状の緩和に役立ちます。
- 十分な休息と睡眠
睡眠不足はPMSの精神症状を悪化させる要因となります。
質の良い睡眠を確保するため、毎日決まった時間に就寝・起床し、寝る前のスマホやテレビ視聴を控える、リラックスできる環境を整えるなどの工夫をしましょう。 - 自分なりのストレス発散法
アロマテラピー、半身浴、マッサージ、趣味に没頭する、友人と話すなど、自分に合ったリラックス方法を見つけ、積極的に取り入れましょう。
ストレスを溜め込まないことが、PMS症状の軽減につながります。 - 禁煙
喫煙は血流を悪くし、自律神経の乱れを引き起こすため、PMSを悪化させる原因となります。
禁煙を心がけましょう。
PMSの時期や症状の傾向を把握するために、症状日記(PMSダイアリー)をつけることをおすすめします。
日付、生理周期、経血量、体重、基礎体温、具体的な症状(いつ、どんな症状が、どの程度現れたか)などを記録することで、自分の体のリズムを客観的に知り、症状の予測や対処計画を立てやすくなります。
これにより、「いつ何に苦しむかわからない」という不安感が軽減され、PMS期間をより落ち着いて過ごせるようになります。
セルフケアで症状が改善しない場合や、日常生活に支障が出るほど症状が重い場合は、医療機関を受診することを検討しましょう。
- チェストベリー配合薬(例:プレフェミン)
PMSに特化した市販薬で、チェストベリーという西洋ハーブの成分が女性ホルモンバランスを整え、乳房の張り、頭痛、イライラ、気分の落ち込みなどの症状を緩和します。1日1回1錠の服用で、3周期(約3ヶ月)継続することで効果が期待できます。 - 鎮痛薬
頭痛、腹痛、腰痛などの痛みが強い場合に一時的に症状を和らげます。ロキソニンSなどが代表的です。 - 漢方薬
体質や症状に合わせて選ばれます。- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
下腹部痛、冷え、生理痛、精神不安、イライラなどに。比較的体力がある人向け。 - 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
足腰の冷え、生理不順、貧血傾向、むくみ、だるさ、めまいなどに。体力が少ない人、痩せ型の人向け。 - 加味逍遙散(かみしょうようさん)
のぼせ、イライラ、精神不安、疲れやすさなどに。自律神経を調整し、血行促進効果も期待できます。体力が中等度以下の人向け。 - 命の母ホワイト
11種類の生薬が血行を促進し、自律神経や女性ホルモンの乱れによる不調(ヒステリー、冷え、貧血、肌荒れなど)を改善します。
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
- 低用量ピル
排卵を抑制し、女性ホルモンの変動を最小限に抑えることでPMSの症状を軽減します。避妊効果も期待できます。多くのPMS症状(身体的・精神的)の改善に効果があるとされています。 - 黄体ホルモン製剤
黄体ホルモンのみを含む薬で、子宮内膜の増殖を抑制し、生理そのものを止めることでPMS症状を抑えます。不正出血の副作用が出やすいですが、低用量ピルよりも吐き気が出にくい場合もあります。
セルフケアを試しても症状が改善しない、あるいは仕事や学業、人間関係に支障が出るほど症状が重い場合は、我慢せずに婦人科を受診しましょう。
自分の感情をコントロールできない、無気力で起き上がれないといった深刻な精神症状がある場合は、心療内科や精神科への受診も検討することが大切です。
婦人科では、まず詳細な問診が行われます。
症状の種類、発症時期、生理周期、妊娠・出産歴、生活環境などが確認されます。
PMSの診断は、症状日記の記録に基づき、月経周期との関連性や症状の再現性を確認することが重要です。
他の疾患(うつ病、甲状腺疾患など)の可能性を除外するために、血液検査や超音波検査が行われることもあります。
診断が確定すると、カウンセリングや生活指導に加え、症状に応じた薬物療法が提案されます。
低用量ピルによるホルモン調整、漢方薬による体質改善、鎮痛薬や精神安定剤などによる対症療法が主な治療法です。
受診する際は、自分の症状を具体的に、そして正直に伝えることが重要です。
PMS日記をつけている場合はそれを持参し、医師に見せることで、より正確な診断と適切な治療につながります。
内診に抵抗がある人もいるかもしれませんが、PMSの相談でいきなり内診台での診察となることは稀です。
まずは問診でじっくり話を聞いてもらえるので安心しましょう。
オンライン診療も選択肢の一つとして活用できます。
PMSの症状は、年代やライフステージによって変化し、それぞれに特有の悩みや工夫が見られます。
- 10代(思春期)
初経を迎える頃からPMSの症状が出始めることがあり、学業や部活動への集中力低下、イライラなどで悩むことがあります。 - 20~30代(性成熟期)
PMSの症状が最も多く現れる年代です。仕事や恋愛、結婚、出産といったライフイベントが重なり、ストレスによって症状が悪化することもあります。特に育児中は、精神的な余裕がなくなり、イライラや怒りっぽさが顕著になるケースも報告されています。 - 40代(更年期移行期)
更年期に近づくと、生理周期が乱れ始め、PMSと更年期症状が混在して区別がつきにくくなることがあります。体のほてり、イライラ、不安感などが重なり、より複雑な不調を感じることがあります。
PMSの症状は、日常生活におけるさまざまな場面で影響を及ぼします。
- 仕事や学校
集中力の低下、倦怠感、イライラなどにより、仕事や学業のパフォーマンスが低下することがあります。周りの人にPMSであることを理解してもらうことで、無理のないスケジュール調整や業務分担が可能になる場合があります。 - 家族やパートナー
情緒不安定やイライラによって、家族やパートナーとの関係に摩擦が生じることがあります。自身のPMSの症状や特性を事前に共有し、理解を求めることが大切です。互いの体調を気遣い、サポートし合うことで、精神的な負担を軽減できます。 - 男性ができること
PMSについて知識を持ち、パートナーの不調に寄り添うことが重要です。具体的な原因を追求するのではなく、「調子が悪い」という事実を受け止め、休息できる環境を整える、家事や育児をサポートするなど、できることから協力しましょう。
- 他の薬と併用しても大丈夫ですか?
- 服用中の薬の成分と同じものが含まれている場合、過剰摂取となり副作用が強く出るおそれがあるため、併用は避けることが望ましいです。市販薬を服用する場合は、薬剤師に相談してください。
- 市販薬はどのぐらい服用し続けるべきですか?
- 薬にもよりますが、1ヶ月程度服用し続けて症状が改善しない場合は、薬が合っていない可能性があります。薬剤師や医師に相談し、薬の変更を検討しましょう。
- なかなか効果が得られない場合はどうしたらいいですか?
- PMSの症状が深刻で日常生活に支障が出ている場合は、なんらかの疾患が隠れているおそれがあります。速やかに婦人科を受診してください。低用量ピルなどの処方薬が有効な場合もあります。
- PMSの症状に個人差があるのはなぜですか?
- PMSの原因はホルモンバランスだけでなく、個人の性格、ストレス、生活習慣など様々な要因が複雑に絡み合っているため、症状の出方には大きな個人差があります。
生理やPMSは、多くの女性が経験する自然な体の変化ですが、その症状は時に日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
一人で抱え込まず、家族やパートナー、友人、そして専門家である医師や薬剤師に相談することが重要です。
適切な知識とサポートを得ることで、毎月の不調を乗り越え、より快適な日々を送ることができるでしょう。
この記事は、生理とPMSに関する基本的な情報を網羅した記事として、あなたの健康的な生活をサポートします。
PMSや生理の症状は多岐にわたり、一人ひとりの状況に合わせた対処法を見つけることが大切です。
より詳細な情報や個別の症状に特化した対策については、今後公開される関連個別記事をご参照ください。
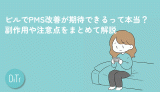 ピルでPMS改善が期待できるって本当?副作用や注意点をまとめて解説
ピルでPMS改善が期待できるって本当?副作用や注意点をまとめて解説 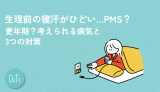 生理前の寝汗がひどい…PMS?更年期?考えられる病気と3つの対策
生理前の寝汗がひどい…PMS?更年期?考えられる病気と3つの対策 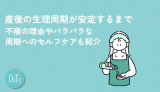 産後の生理周期が安定するまで|不順の理由やバラバラな周期へのセルフケアも紹介
産後の生理周期が安定するまで|不順の理由やバラバラな周期へのセルフケアも紹介 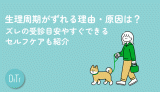 生理周期がずれる理由・原因は?ズレの受診目安やすぐできるセルフケアも紹介
生理周期がずれる理由・原因は?ズレの受診目安やすぐできるセルフケアも紹介 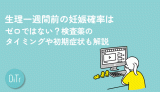 生理一週間前の妊娠確率はゼロではない?検査薬のタイミングや初期症状も解説
生理一週間前の妊娠確率はゼロではない?検査薬のタイミングや初期症状も解説 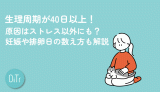 生理周期が40日以上!原因はストレス以外にも?妊娠や排卵日の数え方も解説
生理周期が40日以上!原因はストレス以外にも?妊娠や排卵日の数え方も解説 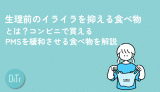 生理前のイライラを抑える食べ物とは?コンビニで買えるPMSを緩和させる食べ物を解説
生理前のイライラを抑える食べ物とは?コンビニで買えるPMSを緩和させる食べ物を解説 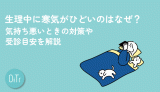 生理中に寒気がひどいのはなぜ?気持ち悪いときの対策や受診目安を解説
生理中に寒気がひどいのはなぜ?気持ち悪いときの対策や受診目安を解説 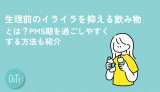 生理前のイライラを抑える飲み物とは?PMS期を過ごしやすくする方法も紹介
生理前のイライラを抑える飲み物とは?PMS期を過ごしやすくする方法も紹介 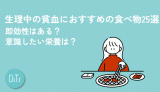 生理中の貧血におすすめの食べ物25選!即効性はある?意識したい栄養は?
生理中の貧血におすすめの食べ物25選!即効性はある?意識したい栄養は?